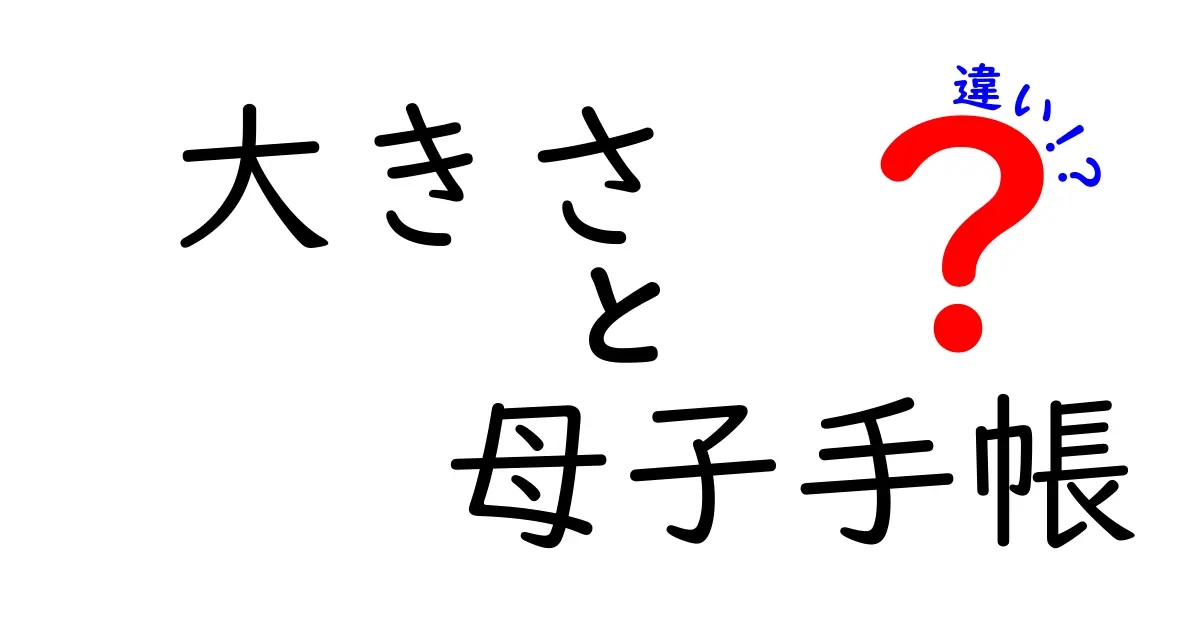

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:大きさと違いが意味すること
大きさの話題は見た目だけでなく、日常の使い勝手にも直結します。母子手帳は妊娠中〜子どもの成長を記録する大切な冊子です。自治体によってサイズや厚さ、挟み方などが異なる場合があります。ここでは「大きさ」という要素がどんな影響を与えるのかを、中学生にもわかる言葉で解説します。
まず知っておきたいのは、「サイズが違っても中身は同じ情報を保険証・受診票の代わりに使える」という点です。
ただし、体感できる差はあります。
例えば、ポケットに入る小さめの冊子は外出時の携帯性に有利です。一方、資料や写真が多く挟みたい場合はある程度の厚みがある方が整理しやすくなります。
この章では、大きさが実際の使い勝手にどう影響するのかを、現場の視点と一般的な目安を組み合わせて説明します。
サイズの実例と使い勝手の違い
自治体ごとにサイズは異なることが多く、A6相当、B6相当、A5相当などの表現が使われることがあります。
A6サイズ(約105×148 mm)は携帯性に優れる一方、記録スペースが限られ、写真・検査結果のプリントを多く挟みにくいことがあります。
一方、B6サイズ(約128×182 mm)は中間のサイズで、持ち歩きと資料の整理のバランスが取りやすいという声が多いです。
A5サイズ(約148×210 mm)は情報量が多い分、成長記録や保健師のメモをたくさん載せられますが、かさばるためバッグの中で場所を取ることがあります。
表紙の耐久性やファイル機能の有無も使い勝手に影響します。
以下の表はサイズの違いと特徴をまとめたもの。
このように、サイズの違いは持ち歩きやすさと中身のバランスに影響します。
ただし、どのサイズを選ぶべきかは「自分と家族の生活スタイル」によって変わるため、自治体窓口で実物を見せてもらうのが一番良い方法です。
なお、手帳そのものの基本機能はどのサイズでも共通しています。出生情報・予防接種の記録、健診のデータ、医療機関の受け取り時に必要な情報が統合され、管理の仕方が簡単になる点は変わりません。
友だちと学校帰りに母子手帳のサイズの話をしていたとき、彼は『サイズが違うと中身まで違うの?』と尋ねた。私は答えた。『中身は基本的には同じ情報を記録するけれど、サイズが違うと見開きの使い勝手や持ち歩きの快適さが変わるんだ。小さめの手帳はポケットに入るので急いで提出が必要なときに便利。大きめの手帳は写真や検査結果を多く挟めて、家で整理するには向いている。どのサイズを選ぶかは、家族が日常どのように手帳を使うかによるんだ。』





















