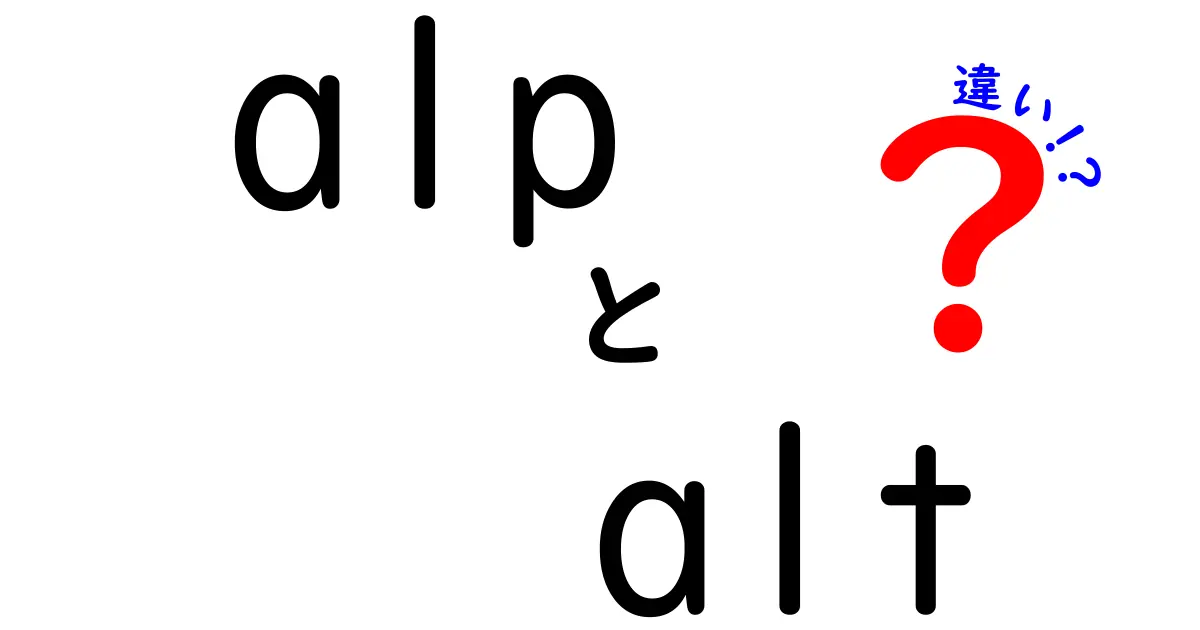

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ALP(アルカリ性ホスファターゼ)とALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)の基本
このセクションでは ALP と ALT の基本をしっかり押さえます。
ALP は「アルカリ性ホスファターゼ」という酵素で、肝臓だけでなく骨や腸など体のいろいろな場所に存在します。血液検査でこの値が高いと、胆道のトラブルや骨の成長・代謝の問題を示していることがあります。
ALT は「アラニンアミノトランスフェラーゼ」と呼ばれ、主に肝臓に多く存在します。肝細胞が傷つくと血液中に流れ出して ALT の値が上がります。つまり ALT は肝臓の“細胞の状態”を反映しやすい指標です。
この背景から、ALP が高い原因は骨の成長期や胆道障害など複数、ALT が高い原因は肝臓の障害などが典型的です。医師はこれらの数値を見て、次に何を調べるべきかを判断します。
この違いを知っておくと、検査結果を見たときに「何が原因で高いのか」を自分なりに考えるヒントになります。
数値の見方と日常のケースでの判断ポイント
ALP と ALT の「正常値」は施設ごとに異なる場合が多く、検査を受けるときは必ず検査報告書の基準範囲を確認してください。
ここで紹介する値は、学校の教科書的な目安としての一般的な範囲です。ALP はおおよそ 30–115 U/L、ALT はおおよそ 7–56 U/L というのが標準としてよく使われますが、年齢や性別、妊娠中かどうか、子どもの成長段階などで変動します。
ALP が高いときは、骨の成長期・骨代謝の活発化、胆道障害、肝疾患の可能性を同時に考えます。ALT が高い場合は、肝炎・脂肪肝・薬物性肝障害・アルコールの影響などが原因として挙げられます。いずれも単独で病気を断定することはできず、ほかの検査値や症状と合わせて判断します。
検査結果を受け取ったら、医師の説明をよく聞き、生活習慣の改善や必要な追加検査を順序よく進めることが大切です。以下の表は代表的な違いをまとめたものです。
ある日、学校の友だちが健康診断の話題を持ち出しました。ALT が少し高かったらしく、心配している様子でした。私は「ALTは肝臓の細胞の状態を示す指標だから、軽い炎症や一時的な影響でも上がることがあるよ」と伝えると、友だちは安心したようでした。一方、ALPは骨の成長や胆道の働きと深く関係しているので、若い人は成長期で高く出ることも珍しくないと説明しました。数値だけで一喜一憂せず、医師の説明と生活習慣の改善を一緒に考えることが大切だと実感しました。結局、検査結果は体全体のサインの一部。焦らず、適切な時期に再検査を受けることが大切です。





















