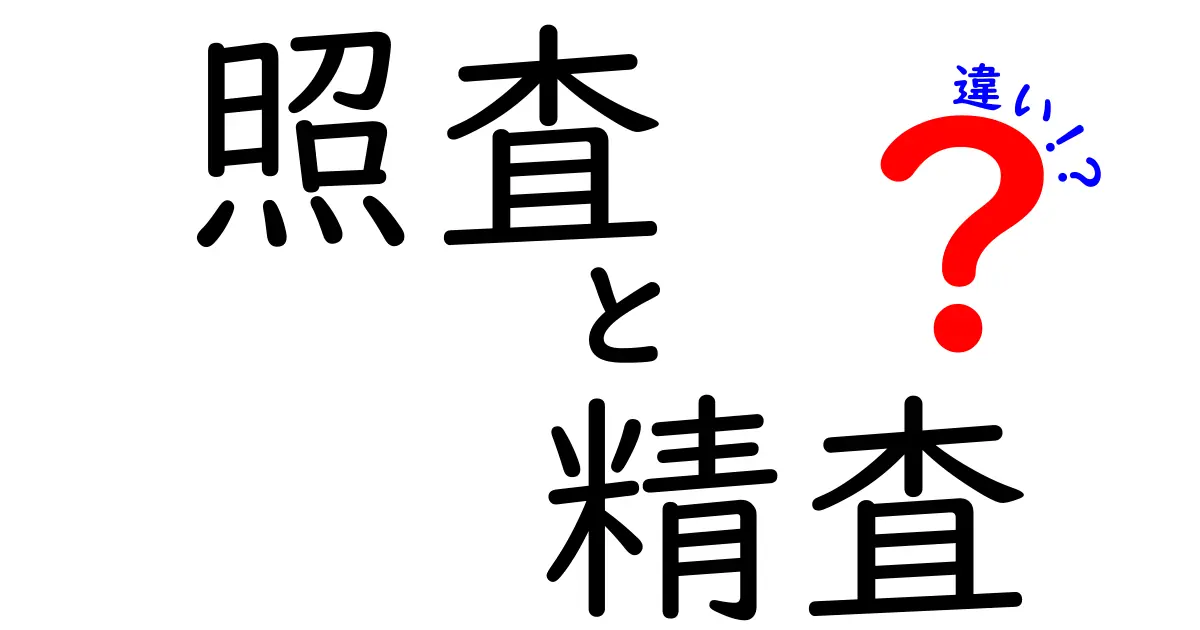

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
照査と精査の基本的な意味を理解しよう
日常や仕事の中でよく使われる言葉に「照査(しょうさ)」と「精査(せいさ)」があります。どちらも物事をよく調べることを意味していますが、実は意味や目的に違いがあるのです。
まず、「照査」とは、資料やデータなどが正しいかどうか、間違いがないかをチェックする作業を指します。たとえば、書類の数字が合っているか、情報が漏れていないかをざっと確認する場面などで使います。
一方、「精査」は、もっと詳しく、深く調べることを意味します。問題がないか注意深く細かい部分まで調べたり、理由や原因を探ったりする時に使われます。
つまり、「照査」はざっと間違いがないかの確認で、「精査」は詳しく調べて問題点を見つけることが特徴なのです。
照査と精査の具体的な使い方と違いを見てみよう
実際の仕事の場面で「照査」と「精査」はどのように使われるのでしょうか?
たとえば、会社での会計報告書を作成したとします。まずは「照査」として、記入ミスや数字の食い違いがないか簡単にチェックします。ここで大きな誤りがなければ次の段階へ進めます。
次に「精査」の段階では、数字の背景を調べたり、取引内容を詳しく分析したりします。何故その数字になったのか、問題や疑問点がないかを念入りに調べる作業です。
以下の表でその違いをまとめました。
| 項目 | 照査 | 精査 |
|---|---|---|
| 目的 | ミスや間違いのチェック | 詳細な原因や問題の発見 |
| 調査の深さ | 表面的、ざっくり | 詳細に、深く |
| 作業の例 | 書類の数字合わせ、誤記の確認 | データの背景分析、矛盾点の発見 |
| 使う場面 | 初歩的なチェック段階 | 重要な分析や問題解決の場面 |
照査と精査を使い分けるポイントと注意点
「照査」と「精査」は似ているようで違うため、仕事や日常で混同しないように注意しましょう。
ポイントは、チェックの深さと目的をはっきりさせること。
・まずは「照査」で間違いがないか簡単に見て、問題があれば「精査」で詳しく調べる。
・「照査」の段階で問題がなければ「精査」は必要ないこともあります。
また、使い方としては、報告書や契約書のレビュー、品質管理などいろんな分野で使われます。だから、相手に伝える時はどのような調査をするのか具体的に説明することが大切です。
正確に伝え、適切に使うことでミスの防止や信頼アップにつながります。
「照査」という言葉、一見難しそうですが、実は「チェックする」という意味の仕事用語です。驚くべきことは、照査だけで終わらず、もし違和感があれば次の段階「精査」に移るんです。つまり、照査は“ざっと見て問題なさそうかを探る”感じで、面白いのは、これって日常の生活でも使えるんですよね。例えば、宿題を終えた後に「照査」として間違いがないか確認し、もっと詳しく調べたい時は「精査」に相当する行動に変わります。仕事だけじゃなく、普段の生活でも役立つ言葉なんですよ!
次の記事: 照査と調査の違いを徹底解説!仕事内容や目的をわかりやすく比較 »





















