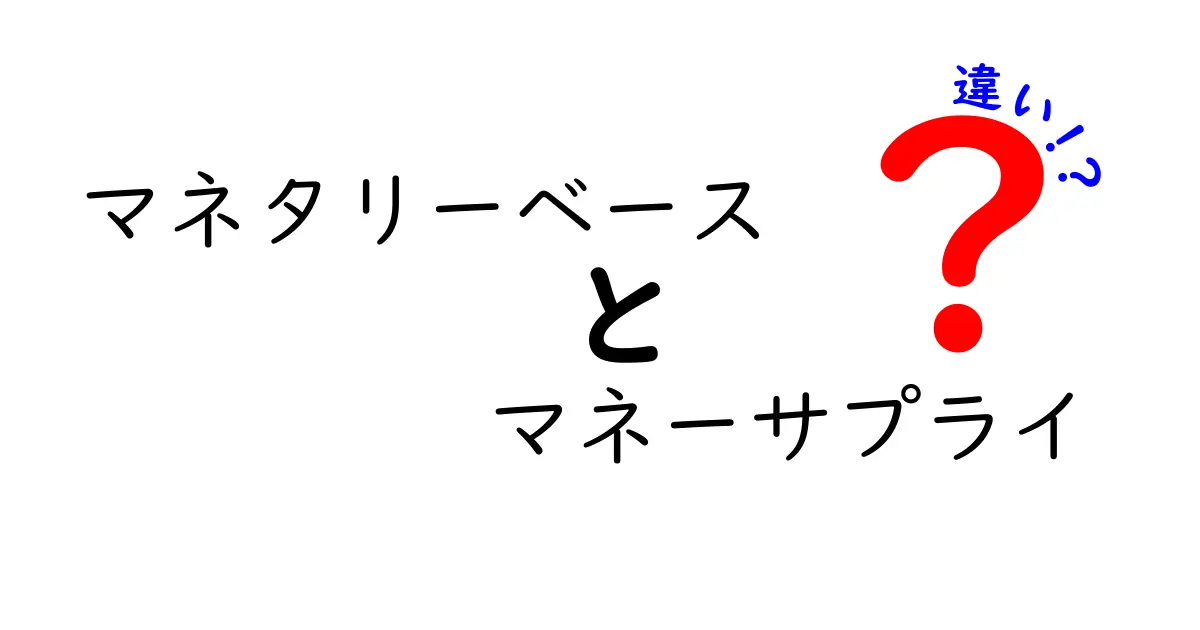

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
マネタリーベースとマネーサプライとは何か?基本の理解を深めよう
まず、「マネタリーベース」と「マネーサプライ」は、どちらもお金の量に関する言葉ですが、その意味や範囲には大きな違いがあります。
マネタリーベースとは、中央銀行が市場に直接供給しているお金のことを指します。具体的には、紙幣や硬貨の現金のほか、銀行が中央銀行に預けている預金準備金の合計です。これは中央銀行の直接的なコントロール下にある非常に限られたお金と言えます。
一方、マネーサプライとは、私たちが普段の生活で使うことができるお金の総量で、現金だけでなく銀行の普通預金や定期預金など、銀行を通じて世の中に流通しているあらゆる種類の通貨の合計を含みます。つまり、マネタリーベースはマネーサプライの中に含まれるが、その一部にすぎないということです。
具体的な違いを表で比較してみよう
文章だけではわかりにくいので、下の表でそれぞれの特徴を比較してみましょう。
なぜこの違いが重要なのか?金融政策と経済の関係
マネタリーベースは「基礎的なお金の量」として中央銀行が増やしたり減らしたりすることができます。たとえば、景気が悪くなったときに中央銀行はマネタリーベースを増やして、市場にお金を流し、経済を刺激しようとします。
しかし、実際に世の中にあるお金の総量、つまりマネーサプライは銀行の貸出などが影響して動きます。マネタリーベースが増えても、銀行が貸し出しを控えればマネーサプライはあまり増えません。そのため、単にマネタリーベースを見るだけでは経済全体のお金の量を理解することは難しいのです。
この違いを理解することで、ニュースなどでよく聞く金融政策の効果や経済の動きをより深く学べるようになります。
今回は「マネタリーベース」について少し深掘りしましょう。これは実は、私たちが普段目にするお札や硬貨だけでなく、銀行が中央銀行に預けている「準備預金」も含まれます。たとえば、銀行はお客様から預かったお金の一部を中央銀行に預けて保管しています。この部分が増減すると、銀行が貸し出せるお金の量にも影響を与えて、結果的に経済全体のお金の量に大きな動きをもたらすんです。だから、「マネタリーベース」は単純に現金のことだけと思うのはちょっと違うってこと、知っていると金融ニュースも面白く見られますよ!
前の記事: « ベーシススワップと通貨スワップの違いとは?わかりやすく解説!





















