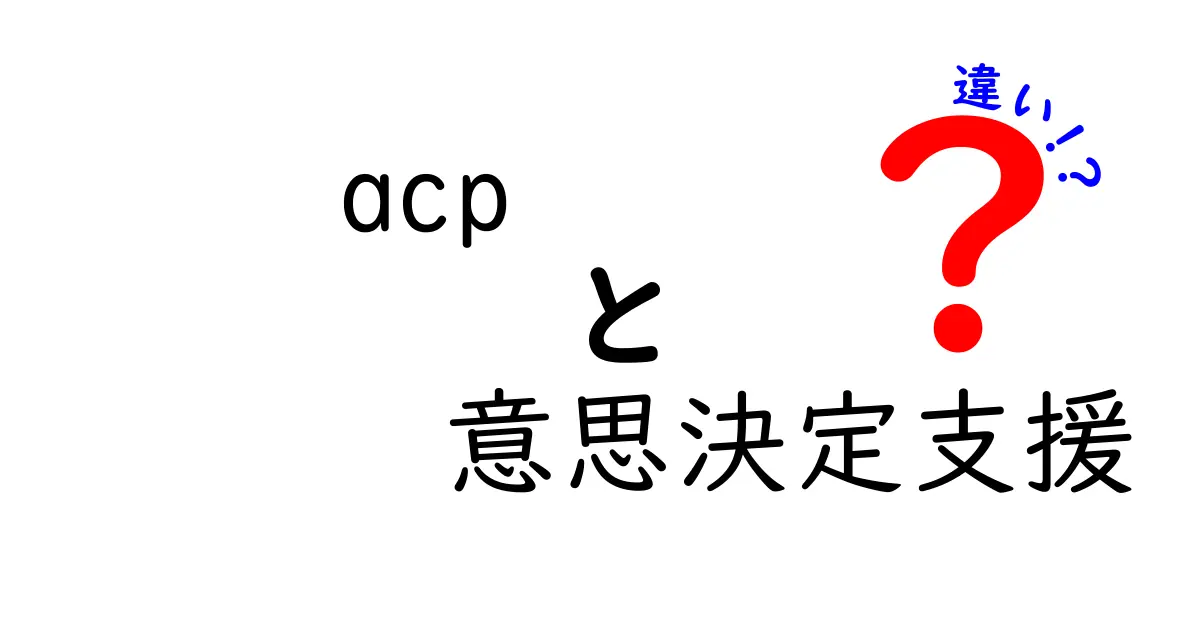

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:acpと意思決定支援の違いを正しく理解する
acpと意思決定支援は似ているようで、目的と場面が違います。医療の現場では、患者の価値観を大切にすることが求められますが、その実現には具体的なやり方が必要です。本記事では、やさしい言葉で両者の違いを解きほぐします。まずは結論から言うと、acpは将来の医療の方向性を事前に整理するための会話と記録のセットであり、意思決定支援は現在の選択肢を患者と家族が理解し納得して決めるための支援プロセスです。ここを押さえると、混同しがちな用語を正しく使い分けられるようになります。
この違いを知ることは、患者中心のケアを実現する第一歩です。
どうしても場面ごとに違いがあると感じることがありますが、基本は「情報を伝え合い価値観を確認する」こと、そして「あなたの希望を医療の現場が尊重する」ことです。
そもそもacpとは何か
acpとはAdvance Care Planning の略で日本語では前もって決めておく医療計画と訳されることがあります。病名や治療の難易度が上がる場面で、患者本人・家族・主治医が対話します。ここで大事なのは患者の意思が最優先であることと情報の提供と理解の促進です。acpには法的な文書化が含まれることもありますが、必須ではなく、対話と記録を通して関係者が共通理解を持つことが主目的です。
実務では、希望する治療の範囲や、延命措置をどう扱うか、在宅療養の意向、緊急時の対応などを網羅的に話し合います。状況の変化に応じた見直しも特徴の一つです。
意思決定支援とはどんな場面で使われるのか
意思決定支援は患者や家族が難しい医療の選択を迫られたときに使われます。情報を平易な言葉で説明し、選択肢の利点と欠点を並べ、患者の価値観を整理します。例えば慢性疾患の治療方針、手術の可否、治療を続けるべきかどうかの判断など、状況は多岐に変わります。具体的には情報提供、価値観の明確化、代替案の検討、理解の確認、決定の支援というステップを踏み、最終的な決定を患者自身が下せるようサポートします。
このプロセスの鍵は「どの情報をどう伝えるか」「どう理解を確かめるか」「誰が関与するか」です。医師だけが決めるのではなく、患者・家族・専門職が協力して意思決定を行います。意思決定支援は治療内容以外の日常の選択にも適用され、患者の生活の質を大切にする視点を育てます。
違いを整理して使い分けるコツ
実務上は acp と意思決定支援を区別して使い分けることが重要です。acp は未来志向の話し合いと記録、意思決定支援は現在の選択を支える具体的な手続きです。混乱を避けるコツとして、場面を基準にすると良いです。末期医療の話題には acp が適しており、治療選択を含む日常の決定には意思決定支援が有効です。さらに、場面に応じて関係者の役割を明確にすることも大切です。患者本人の希望を中心に据え、家族はサポート役として情報の整理と感情の支えを担当します。
友達と雑談しているような口調で深掘り雑談を続けよう。acp とは未来を見据えた対話のセットで、病気の進行を待つだけでなく“どう生きたいか”を本人の価値観で決めていく作業だよ。対して意思決定支援は今この瞬間の選択をしっかり理解してもらい、納得して進むための手続きや話し合いの進め方を整える働き。つまり acp が長期の道案内、意思決定支援が今この一歩を後押しする役割。二つを組み合わせると、患者さんの意思が医療現場にきちんと反映され、家族の不安も和らぐことが多いんだ。
前の記事: « 立証責任と証明責任の違いを一目で理解する完全ガイド
次の記事: 政令と省令の違いを徹底解説!中学生にもわかる法律の仕組み入門 »





















