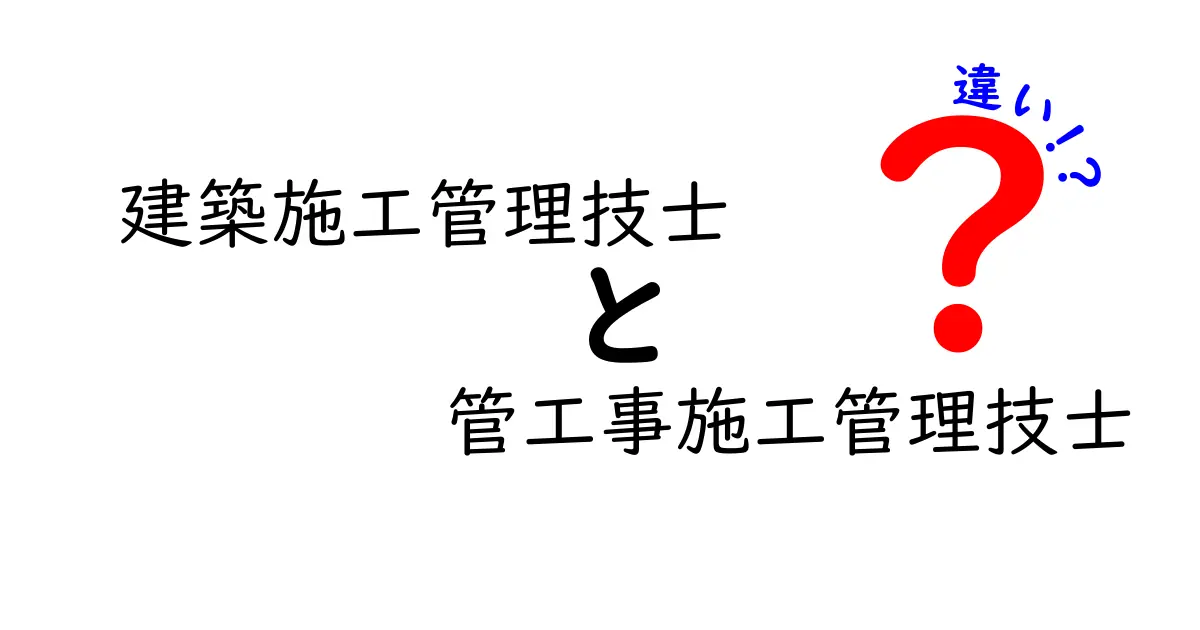

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
建築施工管理技士と管工事施工管理技士の違いをわかりやすく解説
建築施工管理技士とは建築工事全般の品質・安全・工程を管理する専門家です。現場の監督として、施工計画を立て、協力業者と連携し、材料の品質を確保します。対して管工事施工管理技士は水道・配管・ガスなどの管工事を専門に監督します。どちらも現場の“作業を安全・確実に進める”役割を担いますが、対象となる工事の種類や必要な知識・法規が異なります。現場には両方の知識が混在することもあり、実務では協調が欠かせません。現場での安全管理、品質管理、工程管理は両資格に共通しますが、実務で重視されるポイントは変わります。これは学習段階での計画にも影響し、将来のキャリアパスにも影響します。
本記事では「建築施工管理技士」と「管工事施工管理技士」の違いを、実務の観点・試験の観点・取得の道のりという3つの観点から分かりやすく解説します。特に現場で働く若手の方や、これから新しい資格を取りたいと考えている人にとって、どちらを選ぶべきかの判断材料になるよう、実例を交えながら説明します。
そもそもこの2つの資格は何を目指すのか
建築施工管理技士は建築物の大規模・小規模を問わず、建築工事全体の統括を担います。工程管理・品質管理・安全管理の3つの基本機能を統括し、現場の全体像をつかむ能力が要求されます。建築の設計・構造・仕上げ・法規制の知識を横断的に使いこなす力が求められ、現場の“連携力”が重要です。これに対して管工事施工管理技士は水道・ガス・暖房・衛生設備といった管工事の専門領域を監督します。現場での配管の配置・耐震・防火・排水設計の遵守、材料選定、施工手順の適正化など、管工事特有の技術と法規、施工計画の実務力が中心となります。つまり、対象工事の種類とそこに関わる法令・技術が大きく違うのです。現場の規模や業種によっては、両資格を併せて持つことが強みになります。
両者の目的は“建設物を安全に作り上げること”という共通点がありますが、学ぶべき範囲と現場での重視点が異なるため、取得後のキャリアや就業先の選択にも影響します。
業務範囲と現場での役割の実務の差
建築施工管理技士の業務範囲は、建物全体の施工計画を作成し、工程表を管理し、品質・安全・コストの総合的なバランスを取ることです。現場では監督として現場監理、協力業者の作業の指示・検査・是正指示を出します。設計図と施工の整合性を確認し、施工計画の遅延を防ぐために資材の発注・物流・現場の人員配置などを調整します。また、建築基準法や労働安全衛生法、建設業法といった法規の遵守を徹底します。
一方、管工事施工管理技士は管工事に特化した現場監理を担います。配管ルートの適正化、耐震・防水の確保、水質・衛生設備の適合性、排水計画の適切性など、専門分野の知識を活かして施工方法を決定します。現場では配管の適正長さ・勾配・接続部の継ぎ目処理など、細かな技術的判断も求められます。
実務では、両資格は時として同じ現場で協力します。例えば高層ビルや病院・学校のような大型施設では、建築の監理と管工事の監理を同時進行で進める必要があり、両者の連携が不可欠です。現場写真を共有し、変更指示を迅速に出すためのコミュニケーション能力も重要です。
現場の実務では、分野の違いを理解したうえで互いを補完する関係が理想的です。
資格の難易度と取得の道筋
資格の難易度は個人の経験・学習方法によって異なりますが、一般には「実務経験を積みながら資格試験に挑戦する人」が多いです。建築施工管理技士の試験は建築全般にわたる知識を問う傾向があり、構造・施工技術・法規・安全など幅広い分野の知識を総合的に問われます。試験対策としては過去問演習・模擬試験・講習会の受講が有効です。
管工事施工管理技士は管工事の専門分野の知識を問う形式が中心で、配管設計・衛生設備・排水・衛生法規・施工計画の理解が要点になります。専門的な用語や測定値、現場での適用例を覚えることが鍵です。どちらの試験も、現場の実務経験が学習の土台となり、技術とマネジメントの両方を兼ね備えた人材として評価されます。
取得の道筋としては、まず所属する建設業者や教育機関での研修を受け、次に実務経験を適切に積んでから試験に挑むパターンが一般的です。試験日は年度ごとに設定され、合格発表までの期間は長めです。合格後は登録申請を行い、正式な資格として業務に従事します。受験料・受験資格の要件・実務年数は時期によって変更されることがあるため、最新情報を公式サイトで確認することが大切です。
ケーススタディ:現場での実務の連携ポイントとよくある誤解
大規模施設の建設現場では、建築施工管理技士と管工事施工管理技士が同じ現場に入ることが多いです。たとえば病院の新築工事を想定すると、建物の構造や内装が先行工事として進む一方で、給排水・衛生設備の工事は並行して進みます。このような場合、現場監督としてのあなたは、技術的な専門用語を共有できるコミュニケーションが求められます。枝分かれする設計変更が生じた場合には、どの変更が他の工程に影響するかを迅速に判断し、関係者へ適切に伝える必要があります。
よくある誤解としては「管工事は後回しでよい」や「建築だけ見ていれば安全」といったものがありますが、実際には水回りの設計ミスは建物全体の安全性に直結します。配管の勾配、排水の流れ、水圧の安定性は設計と施工の正確さに大きく左右します。現場ではこのような連携をとるための定例会議、図面の共有、変更点の追跡が欠かせません。
このような実務を通じて、どちらの資格も現場の“実務力”の証明になります。あなたが現場で活躍するためには、専門知識だけでなく、日々の報告・連絡・相談の徹底や、問題が起きたときの迅速な対応力が最も重要になるのです。
友だちと喫茶店で管工事施工管理技士の話をしていた。やっぱり“管”ってつくと水道とか水回りのイメージが強いけど、実は現場の“縦横のつなぎ役”なんだよね。配管の設置場所を決めるだけじゃなく、安全基準や検査の手順まで把握しておかないと、後で大騒動になる。資格名が長いのは専門性が高いからで、覚える語彙も現場用語が多い。だからこそ、現場で使える実践的な知識を積むことが大事。





















