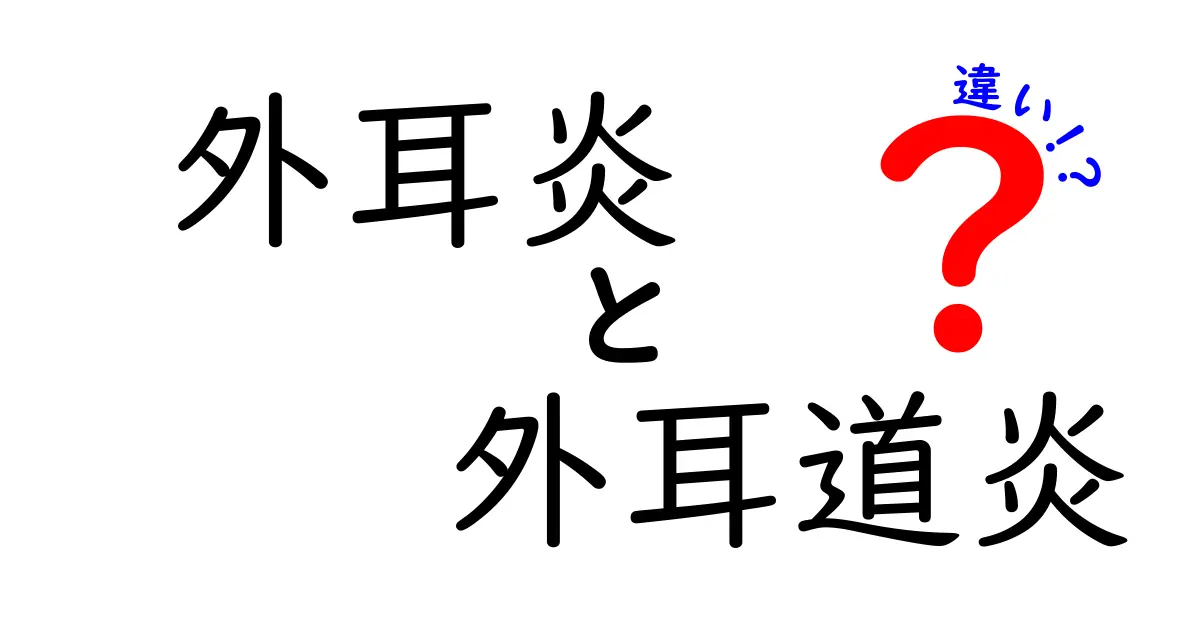

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
外耳炎と外耳道炎の違いをわかりやすく解説します
耳の痛みやかゆみを感じたとき、私たちはすぐに「耳が炎症しているのかな」と思います。しかし実際には外耳炎と外耳道炎は似ているようで状況や原因が少し異なることがあります。外耳炎は耳の外側全体、つまり耳介(耳の外側の部分)やその奥の外耳道を含む広い範囲の炎症を指すことが多いです。一方で外耳道炎は特に外耳道(鼓膜の外側を取り巻く細い管)の炎症を指す専門的な言い方です。どちらも痛みや腫れ、膿のような分泌物が出ることがあり、難しく感じることが多いですが、位置や原因を把握することで対処法も変わってきます。本記事では、違いを見分けるコツ、日常生活での対応、医療機関を受診するべきサインを、初心者にも分かりやすい言葉と具体的な例を添えて解説します。
この話題を知っておくと、耳のトラブルが起きたときに適切な対応がしやすくなります。
定義と基本的な違い
まず最初に押さえておきたいのは、外耳炎と外耳道炎の「場所」と「原因」が少し違うという点です。外耳炎は耳の外側の広い範囲に炎症が及ぶことを指し、耳介の皮膚が赤く腫れたり、外耳道も炎症の一部として含まれることが多いです。外耳道炎は外耳道だけが炎症している状態を意味します。つまり治療の焦点は「炎症の場所」にあり、痛みの感じ方や処置の仕方が少し異なることがあります。どちらも耳の中を観察する機会が必要で、自己判断だけで薬を使い分けるのは避けた方が安全です。若い子どもや高齢者、糖尿病の方などは炎症が広がりやすいので特に注意が必要です。
このような背景を理解しておくと、どの情報が自分に合っているのか判断しやすくなります。
原因とリスク要因
外耳炎と外耳道炎が起こる原因はさまざまです。水泳後の湿った耳が長時間続くと外耳道の皮膚がふやけ、細菌やカビが繁殖しやすくなるため、外耳道炎になりやすくなります。特に夏場はプールや海水浴の後に症状が出やすいです。耳を強くこすったり、耳かきの使い方が乱暴だったりすると、耳の皮膚の薄い部分が傷つき、細菌が侵入して炎症が広がることもあります。また、アレルギー性の皮膚炎や湿疹がある人は、耳の皮膚のバリア機能が低下して炎症が起きやすくなります。糖尿病や免疫力が低下している人は、炎症が長引くリスクが高まることがあります。これらの要因は単独で起きても炎症につながりますが、複数が重なると悪化しやすい点に注意が必要です。
日常の管理としては、耳を濡れたまま放置しないこと、耳かきや刺激の強い洗浄が習慣化していないか振り返ること、そして異常を感じたら早めに受診することが大切です。
症状の見分け方と診断
症状は外耳炎・外耳道炎のどちらでも起こり得ますが、場所によって痛みの感じ方や発生部位が異なります。痛みが強く、耳の周りの腫れや赤みが広がる場合は外耳介の炎症を含む外耳炎の可能性が高いです。耳の奥の細い管(外耳道)のみが痛む、痒みが強い、耳垢の異常な増加や膿のような分泌物がある場合は外耳道炎の可能性が高くなります。医師は耳の中をのぞく検査(耳鏡検査)を行い、必要に応じて分泌物を採取して細菌やカビの種類を調べます。検査結果に応じて薬の選択が変わり、細菌性には抗生剤、カビ性には抗真菌薬が使われることが多いです。自己判断で市販薬を使い続けると症状が悪化する場合があるため、症状が続く場合は必ず受診しましょう。
受診のタイミングとしては、痛みが2~3日経っても改善しない、耳の腫れが広がる、発熱を伴う、聴覚に著しい変化がある場合は急いで受診してください。
治療とセルフケア
治療の基本は「清潔と薬物療法の組み合わせ」です。医師の指示に従い適切な耳薬( drops などの局所薬)を使用します。抗生物質の薬が処方される場合もありますが、自己判断で薬を中止したり、別の薬に変えたりするのは避けるべきです。痛み止めは必要に応じて使いますが、特に小児の場合は医師の指示に従い適切な量を守ってください。日常生活では耳を乾燥させることが重要です。シャワーやお風呂の際には耳を水に濡らさないよう工夫し、入浴後は優しく乾かしましょう。耳かきは絶対に避け、外耳道を傷つけないよう注意します。強い力で耳を触らないこと、イヤホンや耳栓の長時間使用も控えめにします。炎症が広がると中耳炎に移行するリスクもあるため、症状が改善しない場合は再診が必要です。
また、感染性ではなくアレルギー性の炎症が背景にある場合もあるため、生活環境の見直し(ダニアレルゲン、花粉、化粧品成分の見直しなど)も役立つことがあります。医師と相談のうえ、適切な治療計画を立てましょう。
予防と受診の目安
予防の基本は“耳を清潔に、過度な刺激を避ける”ことです。耳を水に長時間曝露させない工夫、耳かきを使いすぎない、湿度の高い環境を避ける、耳の皮膚を乾燥させた状態を保つ、肌の乾燥を防ぐ保湿を適切に行うなどが大切です。特に水泳をよくする人は、耳の防水ケアや耳の乾燥を意識することが重要です。風邪や花粉症、アレルギー体質の人は耳のトラブルが悪化しやすいので、症状が出たら早めに対処します。受診の目安としては、痛みが強い、耳の腫れが広がる、聴覚が低下する、膿や血の混じった分泌物が続く、発熱がある場合などはすぐ医療機関を受診してください。重症化を避けるためにも、早めの受診と正確な診断が大切です。
このように日頃のケアと早めの受診を組み合わせることで、長引く炎症を避け、耳の健康を守ることができます。
小ネタ記事のテーマは“外耳道炎の意外な原因”です。ある日、友だちがシャワーの後に耳を洗いすぎて痛みを訴えました。普通は“汗や水が原因”と考えがちですが、実は日常のちょっとした習慣が大きく影響することがあります。例えば、洗顔のときに耳の周りをこすりすぎると皮膚のバリアが壊れ、細菌が侵入しやすくなります。また、耳かきの角度や力加減、耳穴の乾燥を防ぐ保湿の使い方なども大切です。私たちはつい“耳の中は清潔第一”と考えがちですが、実は“湿度と皮膚の健康”が炎症を作る大きな要因になることが多いのです。シャワーの後は外耳道を過度に濡らさず、使用する道具も清潔に保ち、必要なら医師の指示を仰ぐ――このささやかな心がけが、外耳道炎の予防につながるという雑談風の教訓です。
この話を友達と共有すると、日常の小さな工夫が健康を守る力になると気づくはず。
前の記事: « 前庭と耳石器の違いをやさしく解説|めまいの謎とバランス感覚の秘密
次の記事: 有毛細胞と聴細胞の違いを徹底解説!聴覚の仕組みを身近に理解しよう »





















