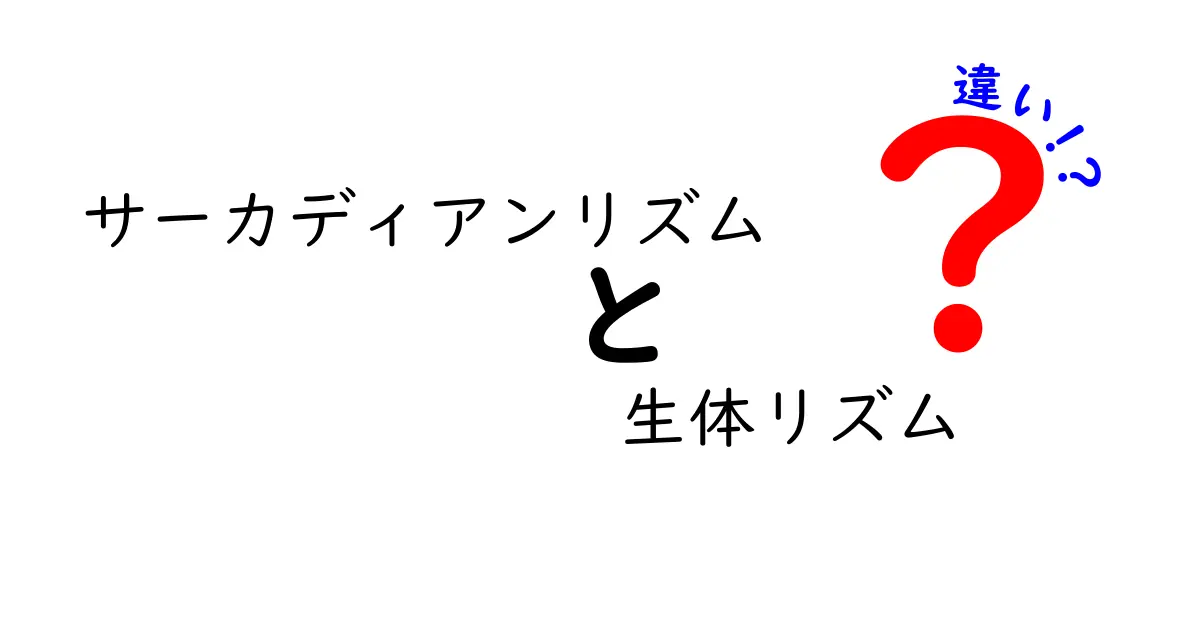

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サーカディアンリズムと生体リズムの違いとは
サーカディアンリズムとは体内時計の中でも約24時間で繰り返されるリズムのことを指します。私たちの眠気や起床のタイミングを決める大切な仕組みで、体温やホルモンの分泌といった生体のさまざまな動きと深く関係しています。日光の明暗を手掛かりにしてこのリズムを少しずつ整えようとする働きがあり、光の刺激が強い朝は目が覚めやすく、夜になると眠気が強くなるよう調整されます。こうした日課は学校生活や部活、友人との時間にも影響します。生体リズムはもっと広い意味の言葉で、睡眠覚醒以外にも体温の変動、内分泌のリズム、あらゆる生体の周期を含みます。つまりサーカディアンリズムは生体リズムという大きな枠組みの中の一つの周期であり、24時間に近い日周期が特徴です。もしこの差を覚えておくと、昼間の活動が増え夜の眠りが深くなるように生活を設計できる点が分かります。
この違いを実感するには日常の観察が役立ちます。例えば朝起きてしばらくすると眠気が消え活動的になると感じる人はサーカディアンリズムが適切に機能している証拠です。反対に夜更かしを続けたり光の多い環境で過ごす時間が長くなると、体の内部時計が少しずつずれていきます。ずれが大きくなると昼間に眠気が来たり夜に眠れなくなることがあります。こうした現象は誰にでも起こり得るので、生活習慣を見直すきっかけにしましょう。
この違いを理解することで日常生活の工夫がしやすくなります。サーカディアンリズムは外部からの刺激に応じて変化しますが、破綻させない範囲で自分のリズムを整えることができます。たとえば朝の光をしっかり浴びる時間を確保する、就寝前の強い光を避ける、規則正しい睡眠時間を守るといった基本が効果的です。生体リズム全体を意識することで睡眠の質改善だけでなく日中の集中力や気分の安定にもつながります。ここでは違いの背景と日常への応用を、具体的な生活の場面とともに詳しく解説します。
サーカディアンリズムの仕組みと日常生活への影響
脳の視床下部には体内時計の中心があり、光の刺激を受けるとSCNが情報を受け取り体の他の部分へ指示を出します。日中は体温が高めに保たれ、夜は低くなり、ホルモンの分泌リズムも夜になると眠気を作るホルモンが増えます。これが私たちの活動と眠りのリズムの基本です。光のタイミングがずれるとこの連携が乱れ、眠気の波が不規則になります。つまり朝は光を浴びて覚醒を促し、夜は静かな環境を作ることで時計と体の動きをそろえることが大切です。
この仕組みを生活に取り入れると日々の調子が整いやすくなります。朝は起きたらすぐにカーテンを開けて自然光を取り入れる。昼間は外で活動する時間を増やし夜はスクリーン光を控える。食事の時間も一定に保つ。こうした細かな習慣の積み重ねが体内時計を安定させ、眠りの質を高めます。
さらに学校生活や部活の時間割にも影響することがあります。部活動の練習後に強い光を浴びると眠気回路が一時的に活性化され、眠りの質が落ちることもあります。ここでのコツは就寝1時間前にはリラックスできる環境を作ること、夜遅い練習がある日は翌日の起床時刻を極端に遅らせないことです。自分の体の信号をよく観察して、適切なリズムを見つけていきましょう。
眠りを深くする具体的な工夫と実践例
眠りを深くするには就寝前の刺激を減らすと効果的です。スマホやパソコンの画面から出る青色光は眠りのサイクルを乱しやすいので就寝の30分前には電源を切るか画面を暗くします。代わりに静かな本を読む、軽いストレッチをするなど心を落ち着かせる習慣を取り入れると良いでしょう。部屋の温度を少し涼しく保つと眠りが深くなり、湿度も適度に保つと呼吸が楽になります。朝は太陽光を浴びることで覚醒を強く促し、体内時計をリセットする助けになります。これらの実践を続けると、眠りの質が安定し日中の集中力や気分が改善されることを多くの人が実感します。
また食事のリズムも大切です。夜遅くの食事は消化活動を長く活発にし眠りを妨げることがあります。可能な範囲で夕食は就寝の3時間前までに済ませ、夜間の間食は控えると良いでしょう。適度な運動を日中に取り入れることで睡眠の深さが増します。運動そのものが体温の変動を促し、夜の眠気を作る手助けになります。睡眠日誌をつけて自分の体のリズムを記録するのもおすすめです。自分のパターンを知ると、改善ポイントが見つけやすくなります。
ねえ聞いて サーカディアンリズム って言葉を初めて聞いたとき 眠る時間だけを指してると思ってたんだ でも実は日光の明暗や体温ホルモンの動き全部が連携して ほぼ24時間の周期で体の動きを決めているんだよ 朝日を浴びると目が覚めやすく 夜は強い光を避けると眠りが深くなる そんな生活のコツが詰まってるって感じ だから朝の光を意識して浴びる時間を作るだけで 一日の調子がかなり良くなることが多いんだ 自分のリズムを知ると 眠るコツも食事の時間も自然と決まってくる だから今日から小さな変化を試してみよう 例えば起きる時間を一定にする 夕方以降は画面の時間を減らす これだけで体内時計が整い始めるんだ ちょっとした工夫が大きな効果につながるよ





















