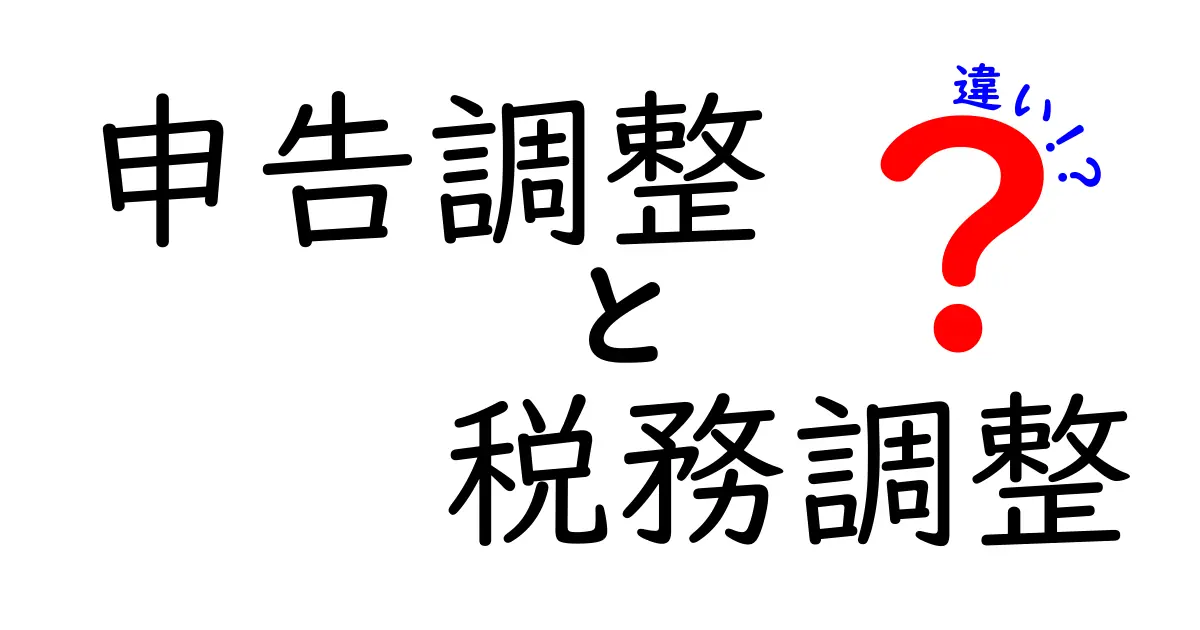

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
申告調整と税務調整の基本とは?
税金の世界でよく耳にする「申告調整」と「税務調整」は、どちらも会社の決算や税金計算に関わる大切な言葉です。この2つの違いを知ることは、税務の基本を理解する上で非常に重要です。
まず、「申告調整」とは、その名の通り、企業が税務署に提出する確定申告で、会計上の利益と税務上の利益を合わせるために行う調整のことです。
たとえば、会計上は経費として計上したけれど、税法上は認められない費用がある場合、その部分を「申告調整」で修正します。
一方、「税務調整」は、税法の規定に基づいて企業が税金を正しく計算するために行う調整全般を指します。
つまり、「税務調整」はもっと広い意味合いを持ち、申告調整もその一部と考えられます。
このように、申告調整は確定申告書作成時の利益調整作業であり、税務調整は税金計算全般のための調整を指す、という基本的な違いがあります。
これから詳しく内容を掘り下げていきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
申告調整の役割と具体的な内容
申告調整は、決算書の利益(会計上の利益)と法人税の計算基準となる所得を調整する作業です。
会計ルールと税法ルールは異なるため、そのまま同じ数字を使うことができません。
例えば、会計上ではある支出を経費として認めていても、税法では認められない場合が多いです。
代表的な例として、「交際費」や「一部の寄付金」などがあります。
こうした費用は、申告調整のときに会計上の利益から除外され、税務上の所得計算に影響を与えます。
具体的には、次のような調整があります。
- 減価償却費の調整:会計と税務で償却方法が異なる場合、調整が必要
- 引当金の調整:将来の費用を見越している引当金の取り扱い
- 交際費の調整:税務上の限度額に応じた調整
- 寄付金の調整:税務で認められる範囲の調整
これらは法人税申告書の「申告調整明細書」に記載され、税務署に提出されます。
つまり、申告調整は税金を計算するために会計上の利益を税法に合わせて修正する作業なのです。
税務調整の意味と役割の広がり
税務調整は、申告調整を含むもっと広い概念です。
税務調整は、税務申告のために必要なすべての調整を指します。
たとえば、損金算入のタイミングや税額控除の適用、さらには法人税以外の地方税や消費税の調整も含まれる場合があります。
会社が税務計算書類を作成するとき、単に申告調整だけではなく、税務上正しい数字を導き出すために多岐にわたる調整が行われます。
以下は税務調整で行われる調整の例です。
- 申告調整(会計利益と税務所得の調整)
- 税額控除の適用計算
- 地方税の計算調整
- 繰越欠損金の控除調整
- その他の税務特別措置の適用調整
こういった多くの調整をまとめて「税務調整」と呼ぶことが多いのです。
つまり、申告調整は税務調整の一部であり、税務調整は税務申告全体で行う調整の総称と考えるとわかりやすいでしょう。
申告調整と税務調整の違いを表で比較
| ポイント | 申告調整 | 税務調整 |
|---|---|---|
| 目的 | 会計利益と税務所得の差異を調整 | 税務申告全体の正確な税額計算 |
| 範囲 | 法人税申告での利益調整に限定 | 法人税だけでなく、地方税などを含む場合もあり |
| 内容の具体性 | 経費の過不足・資産の償却方法などの調整 | 税額控除や欠損金繰越控除など幅広い調整 |
| 役割 | 税金の基礎となる所得の計算 | 正確な納税を行うための総合調整 |
このように、申告調整は税務調整の一部分であり、どちらも税金計算に欠かせない重要な役割を持っています。
両者の違いを正しく理解することで、税務処理の透明性や正確性が高まります。
税務の専門家でなくても、基本用語を正しく把握しておくと税金に関する話がずっと楽になります。
ぜひ今回の内容を参考に、税務の理解を深めてみてくださいね。
「申告調整」という言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は日常にちょっと似たことがあります。例えば家計簿をつけるとき、財布の中に入っているお金とレシートの合計金額が違うことに気づきますよね。その差を調整するように、申告調整も会社の会計上の利益と税法での利益を合わせる“お金のズレの調整”なんです。だから、この調整がしっかりできていないと税金も正しく計算できなくなるので、意外と大事な作業なんですよ。
こんなふうに、税務の話も日常のちょっとした経験に例えると分かりやすくなりますね。
前の記事: « 知らなきゃ損!「8%と軽減税率」の違いを徹底解説





















