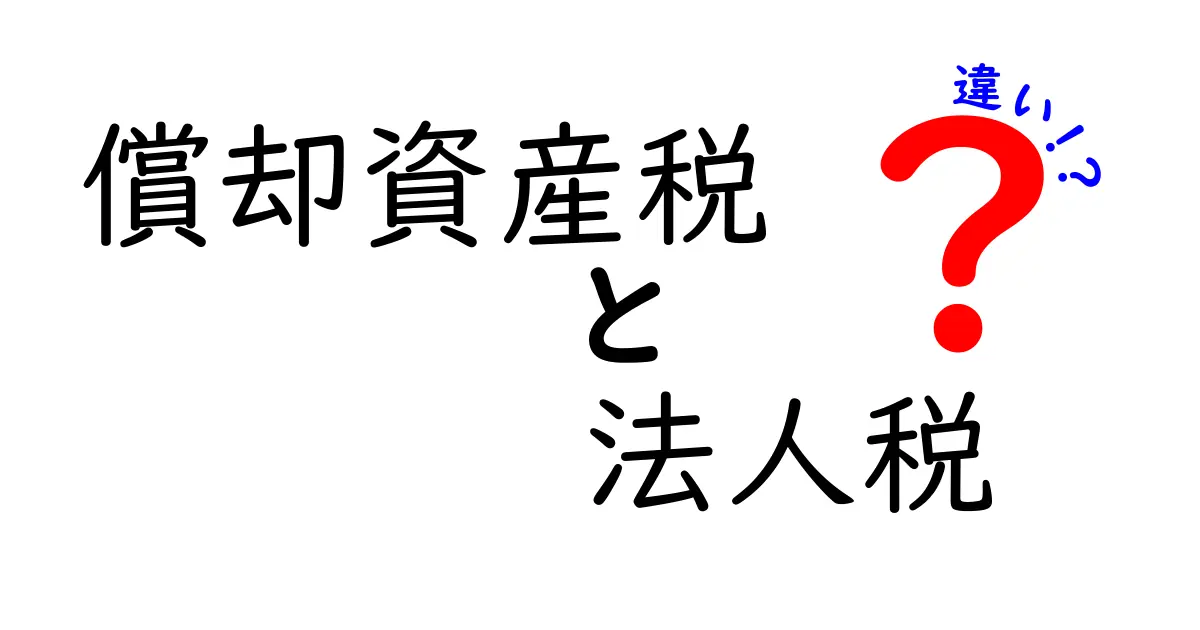

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
償却資産税と法人税の基本的な違いとは?
会社を経営すると、さまざまな税金がかかりますが、その中でも特に混同しやすいのが償却資産税と法人税です。
まず最初に、この二つの違いを簡単に説明します。
償却資産税は、会社が所有している建物や機械、車両などの資産に対して課される地方税で、資産の価値に基づいて毎年払います。一方、法人税は、その会社が1年間で稼いだ利益に対してかかる国の税金です。収入や支出から利益を計算し、その利益に対して税率をかけて計算します。
このように、償却資産税は "資産の価値" に対して、法人税は "利益" に対してかかるというのが最大の違いです。
では、この二つの税金がどんな仕組みで、会社経営にどう影響するのか詳しく見ていきましょう。
償却資産税の特徴と計算方法
償却資産税は、会社や個人事業主が持っている事業用の固定資産に対してかかる税金で、地方自治体が徴収します。対象となるのは建物の一部以外の機械や器具、車両、工具などが一般的です。
計算方法は、まずその資産の「評価額」を出します。この評価額は、購入価格だけでなく経年劣化による価値の減少を考慮して計算されます。
具体的には以下のようなステップです。
- 資産の取得価額(購入費用)をもとに価値を評価する
- 年数の経過により減価償却(価値の減少)を考慮する
- 評価額に対して一定の税率(おおよそ1.4%程度)をかけて税額を決める
例えば、機械の評価額が100万円なら、償却資産税は約1万4千円です。
会社は、この税金を毎年申告し、それに基づき税金を支払います。
このように、資産価値に基づく税金なので、利益が出ていなくても課税されることが特徴です。
法人税の特徴と計算方法
法人税は、会社が1年間で得た利益にかかる国の税金です。利益は、会社の売上から経費や税金などを差し引いて出します。
計算の流れは以下の通りです。
- 売上や収入の合計を出す
- 原材料費、人件費、賃貸料などの経費を差し引く
- その結果出た利益に対して法人税率をかける
たとえば、利益が500万円で法人税率が約23%とすると、納める法人税は約115万円になります。
法人税は国税で、利益が出た場合にのみ課されるので、赤字の場合は基本的に支払い義務はありません。
また、税率や控除も複雑で、会社の規模や経営状態によって変わることもありますので、専門家のサポートも大切です。
償却資産税と法人税の違いをまとめた表
ここで、わかりやすく償却資産税と法人税のポイントを比較した表をご紹介します。
| ポイント | 償却資産税 | 法人税 |
|---|---|---|
| 課税対象 | 事業用の固定資産(機械・工具・車両など) | 会社の1年間の利益 |
| 課税主体 | 地方自治体 | 国(国税) |
| 課税タイミング | 毎年固定資産の価値に基づく | 利益が出た場合のみ |
| 税率 | 資産評価額の約1.4%前後 | 約23%(会社の規模・状況により変動) |
| 税金の計算基準 | 資産の価値(減価償却考慮) | 利益(収入-経費) |
| 支払い義務 | 資産を所有していれば基本的に毎年必要 | 利益が出なければ不要 |
このように、両者は計算方法も課税対象も大きく異なっています。
理解することは、会社の経営計画や税務処理にも役立ちます。
まとめ:なぜ償却資産税と法人税の違いを理解することが大切?
会社経営を行う上で、税金の種類や性質を正しく理解し、適切に対応することが非常に重要です。
償却資産税は、たとえ会社が利益を出していなくても、所有している資産に基づいて課税されます。反対に法人税は、利益が出た場合に初めて課される国の税金です。
もしこの二つの違いを知らずに処理を間違えると、税金の支払い漏れや過払い、場合によってはペナルティが発生することもあります。
また、どの税金がどのように会社の資金繰りに影響を与えるかを理解することで、より良い経営判断が可能になります。
これらの知識は経営者だけでなく、営業担当や経理担当、さらにはこれから起業を考える人にも大切なポイントです。
ぜひ今回の内容を参考にして、税金についての知識を深めてみてください。
償却資産税は資産の価値にかかる税金なので、利益が出ていなくても支払わなければなりません。これは意外に思うかもしれませんが、例えば赤字の年でも新しい機械を買っていれば、その分だけ税金がかかります。つまり、会社の "持ち物" に対して払うお金と考えるとわかりやすいです。この違いを理解すると、税金の種類がよりクリアになり、お金の管理にも役立ちますよ。
次の記事: 国税徴収法と地方税法の違いとは?中学生にもわかりやすく解説! »





















