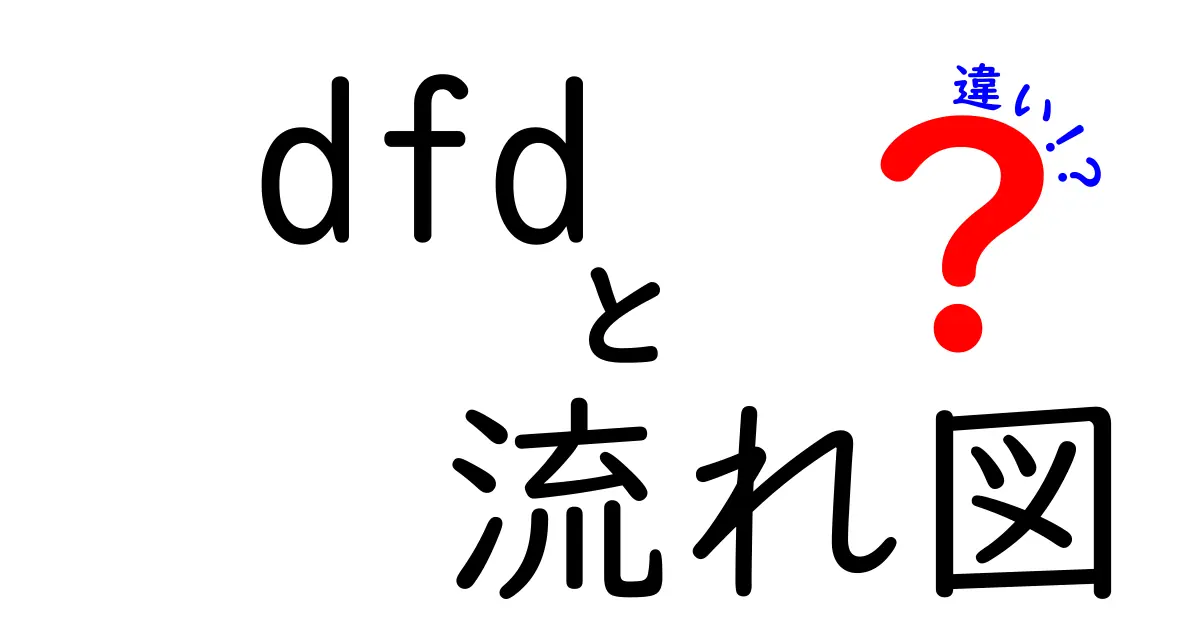

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
DFDと流れ図の違いを、データの流れと処理の観点・記法・用途・粒度・作成の難易度・学習の順序まで、初心者にも分かる言葉で、写真の図解や具体例を交えながら丁寧に解説する前半の章です。ここではまずDFDの基本と流れ図の基本を混同せずに理解するためのポイントを整理します。さらに、実務での使い分けのコツ、よくある間違い、読み手がつまずく点、そして学習を進める際のステップを詳しく紹介します。具体的な例として、オンライン書店の注文処理を仮定して、どのようにデータが移動するか、どの段階でデータが蓄積され、どの段階で処理が進むのかを追っていきます。読者は、データの流れと処理の関係をイメージしながら、図の見方を身につけられるでしょう。
DFDは「データの流れ」を中心に表現する図で、外部エンティティ、データフロー、処理、データストアの4つの要素で構成されます。これはシステムの中でデータがどのように動くかを大局的に示すのに向いています。読み手はデータの出どころと入り先、どのデータがどの処理で使われるかを追うことができます。対して、流れ図(フローチャート)は“処理の手順”を順序立てて描く図です。開始と終了、各処理ステップ、条件分岐、入力・出力などを直感的な形で表現します。
したがって、DFDは情報システムの“データの旅路”を描くのに適し、流れ図は業務手順やアルゴリズムの“動き方”を示すのに適しています。
このように目的と視点が異なるため、同じシステムを表す場合でも、DFDと流れ図は異なる角度から情報を提供します。ここからは、実務での使い分けのポイントを具体的に見ていきます。
次に、DFDと流れ図を合わせて使う場合の流れも説明します。まず要件を整理してDFDのレベル0を作成し、次に個々のデータフローを分解してレベル1以降のDFDを作成します。並行して、同じ業務プロセスの手順を流れ図で描くと、実務担当者や開発者の間での共通理解が深まります。ここで重要なのは、用途に応じて図の粒度を変え、読み手が欲しい情報を的確に伝えることです。
実務での使い分けをイメージでつかむ具体例とコツ:オンライン書店の注文処理を軸に、データの流れと処理手順の協調を詳しく解説する後半の章
オンライン書店の注文処理の例で考えます。受注データは外部から受け取り、在庫確認・決済処理・発送指示といった処理を経て、データストアに蓄積されます。ここをDFDで描くと「データがどこから来てどこへ向かうか」が一本の流れとして見えます。一方の流れ図では、決済の分岐や在庫確認の条件、処理の順番、エラーハンドリングなどの“動き”を細かく追えます。現場では、要件定義の初期段階でDFDを作り、実装設計に落とす前に流れ図で手順を検証するのが有効です。結局は、読者にとって分かりやすい図を選ぶことが大事で、DFDはデータの旅路、流れ図は手続きの道筋を示すと覚えておくと混乱を防げます。
友達とプログラムの話をしていて、DFDと流れ図の違いを深掘りした話題が出ました。DFDはデータがどのように動き、どこで保存され、どの処理で使われるかを全体像として示すもの。一方の流れ図は、実際の手順を順番に追い、条件分岐や繰り返しをどう扱うかを詳しく描く道具です。私たちは、図が“伝える情報の粒度”の差であると説明しました。DFDを描くときはデータの流れを追い、データストアと外部エンティティの関係をつかむことが大切。流れ図を描くときは、処理の順番と条件分岐を明確にして、誰でも追える手順にすることがコツです。





















