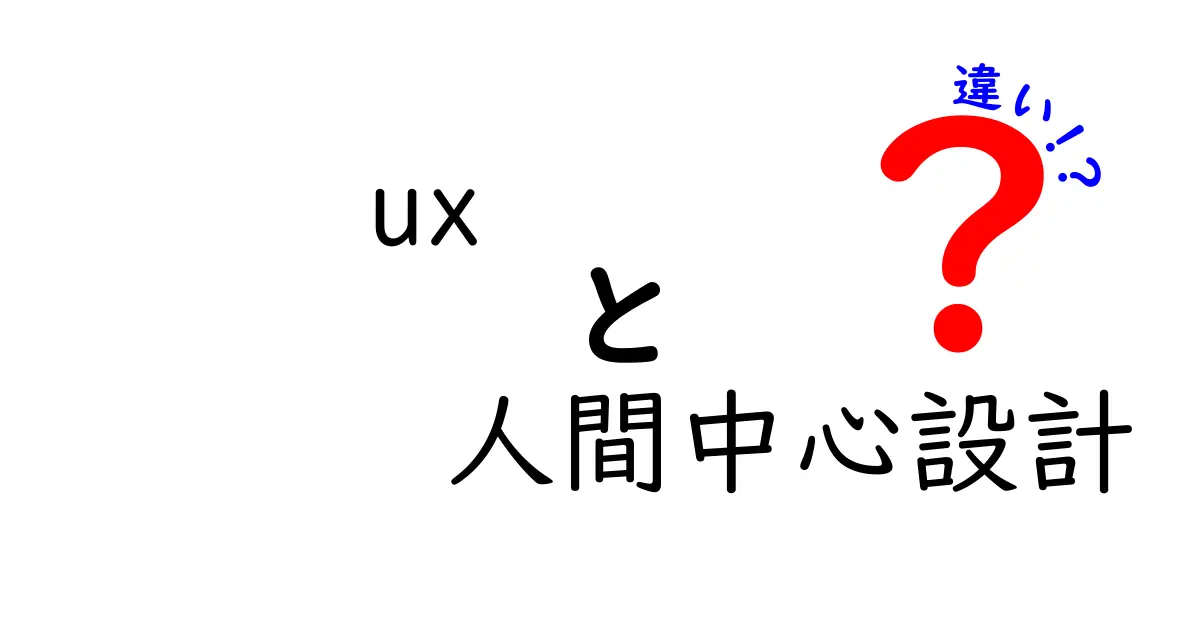

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
UXと人間中心設計の違いを正しく理解するための基本ガイド
このセクションでは、UXと人間中心設計の違いを基礎から整理します。まず、UXは「ユーザーが製品やサービスを使うときに感じる体験の全体」を指す広い概念です。ここには使い勝手だけでなく、満足感、信頼感、感情の動き、学習曲線、記憶のしやすさ、視覚的な美しさなど、使い終わるまでのすべての瞬間が含まれます。一方、人間中心設計はその体験を作るための具体的な設計プロセスであり、ユーザーのニーズを深く理解し、解決策を反復的に検証しながら形にしていく方法論です。
この違いをはっきりさせると、設計の対象や評価の指標が変わってくるため、プロジェクトの初期段階でどの方針を選ぶかが明確になります。UXは最終的にユーザーが感じる体験全体を評価するための基準となり得ますが、設計工程の途中で何を調べるべきかを指すのが人間中心設計の役割です。
次に、実務の場でよくある誤解を解くと、UXと人間中心設計を別物として捉えるより、UXを“体験の結果”と理解し、人間中心設計を“その体験を作るための手段”と理解することが大切です。これを意識すると、要件定義の際に“使う人の心地よさは何か”を問い、設計・評価の各フェーズにおいて、ユーザーの声をどう反映するかを具体的に検討できます。
以下は、違いを具体的な観点で比較する表と、実務で押さえるべきポイントです。
現場で役立つポイントと実践例
現場で役立つポイントとして、まずリサーチを徹底してペルソナと旅路を描くこと、その旅路に沿ってプロトタイプを作り、ユーザーテストで改善、最終リリース後も評価を回すという循環を回すことが挙げられます。これらはUXの質を高め、人間中心設計の原則を守るための実践的な手順です。
具体例として、スマホアプリの onboarding の改善を考えると、最初の体験で「何を知ってもらうべきか」「何を触ってもらうべきか」を明確にします。仮説を立て、低コストの紙プロトタイプやデモを使って早期に検証します。ユーザーの動きや反応を観察し、不意の戸惑いを言語化して設計に戻す、というサイクルを回します。最終的には、学習しやすさと楽しさの両立を目指します。
- リサーチと共感の徹底
- ペルソナと旅路の明確化
- 早期のプロトタイピングと iterative testing
- 改善の優先順位を決める判断軸
- リリース後の評価を欠かさない文化
ある日、友人と雑談していたとき、彼が『人間中心設計って結局、ユーザーの声を集めてそれを形にするってこと?』と言いました。私は笑いながら、人間中心設計はただのヒアリング集めではなく、観察、共感、発見、そして反復の4段階を回す設計哲学だと答えました。例えば、道具を使う人の手の動きを見て、どんな動線がストレスになるかを見つけ、必要な機能を最小限の形で用意していく。途中で仮説を検証するために、プロトタイプを作ってすぐに友人に使ってもらい、感じた不便さを言葉へと落とします。こうして、ユーザーの感情と行動の両方を理解することが、結果として使いやすさと満足感を同時に高めるコツだと気づくのです。最終的には、設計者だけの視点ではなく、実際に使う人々の体験の可能性を広げることが目的であると私は考えます。





















