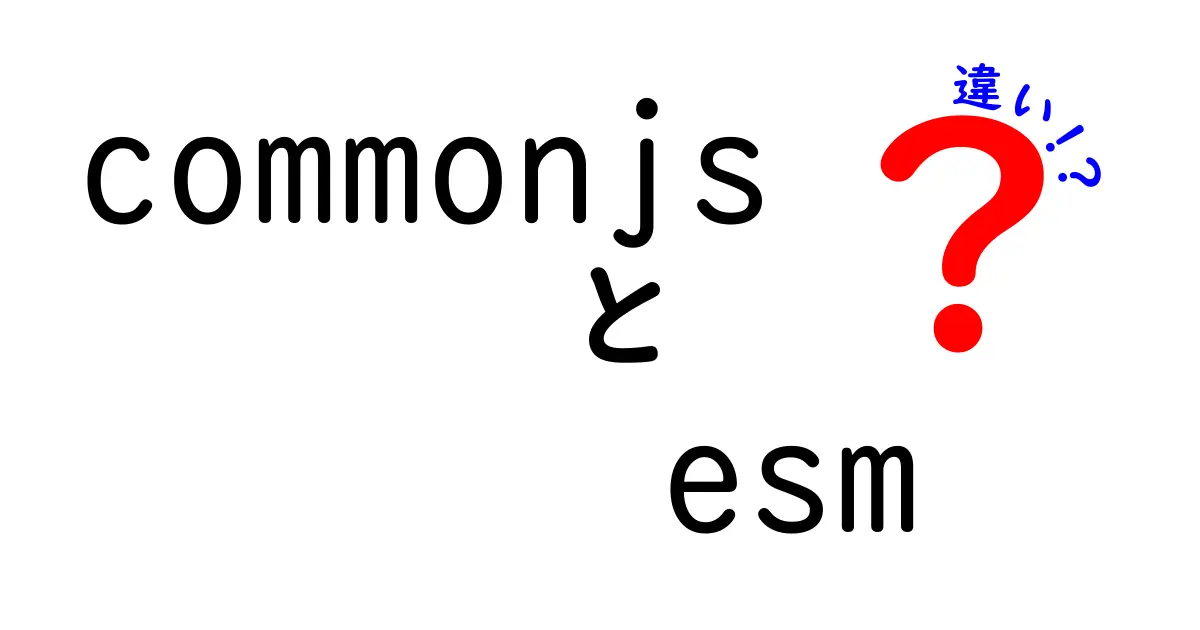

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:commonjsとesmの違いを知る理由
commonjsとesmの違いを理解することは、JavaScriptの世界でモジュールを正しく使い分ける力を養う第一歩です。現在のWeb開発やNode.jsの世界では、モジュールの取り扱い方がアプリの構造やビルドの仕組みに直結します。
たとえば、ブラウザとサーバーの両方で使えるコードを作るとき、ESMを選ぶと将来的な互換性が高くなる傾向があります。一方で、長年使われてきたCommonJSは豊富なライブラリと安定性の面で強みがあります。ここでは、クリックされやすいポイントを押さえるために「コードの書き方」「実行時の挙動」「ツールの対応」という三つの観点から、具体的な違いを順番に解説します。
この章を読めば、「どちらを使うべきか」「どう移行を進めるべきか」が見えてきます。最初は難しく感じても大丈夫。ゆっくり読み進めて、実例のコードを見比べるうちに感覚がつかめてきます。
まず覚えておきたいのは、CommonJSとESMは「モジュールの読み込み方」と「エクスポートの仕方」が異なるという点です。これだけでも、実務での差が多く生まれます。次に、静的解析と動的読み込みの違い、そして環境設定の話が絡んでくるため、単なる用語の違い以上の影響が生まれます。これらを順序立てて見ていくことで、モジュール設計の選択肢が広がるのです。
本記事では、初心者にも伝わる実例と、日常の開発で使えるコツを交えつつ、解説を進めていきます。
このセクションの要点:ESMとCommonJSの基本的な機能の違い、実務での選択肢、移行時の注意点を押さえることが大切です。
今後の章で実際のコード例と設定の違いを詳しく見ていくので、まずは全体像をつかんでください。
小ネタ:ESMって何が“便利”なのか、雑談風に深掘りしてみよう
ESMという名前を聞くと、なんだか難しそうに感じるけれど、キーワードを分解してみると意外と身近です。ESMの“E”は“ECMAScript”の略で、つまり“JavaScriptの公式仕様に沿ったモジュールの使い方”を指しています。
僕がいちど体感した話をすると、ESMはimport/exportを通じて「この機能はどこから来ているのか」を静かに教えてくれます。コードを横に並べて読んでいくと、依存関係のつながりが直感的に見えるようになるんです。CommonJSではrequireが実行時に呼ばれるため、どの順番でモジュールが読み込まれているかを追うのが少し難しく感じる場面があります。ESMでは静的解析が前提になるため、ツールが最適な依存関係の解決を先にしてくれることが多いのです。
この差は、プロジェクトの拡張性やビルドの最適化にも影響します。例えば、コードを分割して遅延読み込みをする際、ESMのimport()を使うと非同期読み込みが自然に扱えます。つまり「必要になったときにだけロードする」という賢い設計がしやすくなるのです。
もちろん、完全に切り替えるには準備が必要です。でも、ESMとCommonJSの違いを“会話”として理解することが、移行を楽にする第一歩になります。





















