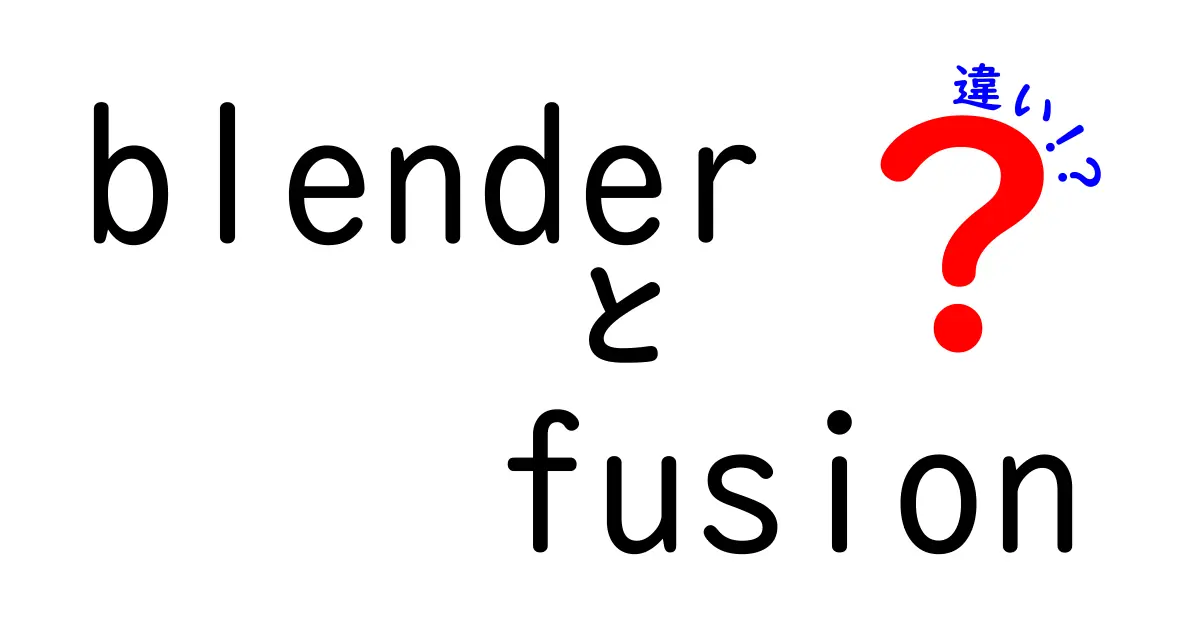

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
BlenderとFusion 360の基本的な違いを知ろう
Blenderは世界中で愛用されるオープンソースの3D制作ソフトです。モデリング・アニメーション・レンダリング・シミュレーション・VR/ゲーム素材作成まで、幅広い機能を一つのアプリで扱えます。
この点が最大の魅力のひとつであり、完全無料で利用できる点が創作を始める入口として大きな強みです。Blenderは創作の自由度を重視する設計思想で、直感的な操作よりも「作って試す」精神を支えます。世界中のユーザーがチュートリアル・フォーラム・プラグインを共有しており、日本語の解説も豊富に揃っています。
一方、Fusion 360はAutodesk社が提供する商用ソフトで、CAD/CAM/CAEに特化しています。部品の寸法・公差・アセンブリの検討、製造準備のための機能が組み込まれており、現実のモノづくりを前提とした設計思想が中心です。Blenderよりも「正確さと再現性」を求められる場面が多く、機械設計や部品開発といった用途に適しています。
この二つの大きな違いは「目的と設計思想」です。Blenderは芸術的な創作、アニメーション、ゲーム向けの素材づくりを幅広くカバーします。対してFusion 360は機械部品の設計・公差管理・製造準備といった現場志向の作業に強みがあります。
使い分けるときの核心は「作りたいものの性質」と「成果物の用途」です。例えばキャラクターの3Dモデルやアニメーション、ゲーム用の素材を作るならBlenderが適しています。対して機械部品を設計して、実際の部品として加工・製造へつなぐならFusion 360が有利です。総じて、両方を使い分けることで、創作と設計の両方に強いスキルセットが築けます。
機能の違いと使い分けの実感
Blenderはモデリングの自由度が高く、自由な発想を追求する場面で力を発揮します。
アニメーション、リギング、物理演算、レンダリング(CyclesやEevee)といった機能を一つの環境で回せるのが魅力です。学習リソースは豊富で、日本語の解説動画やコミュニティの質問応答が活発です。
Fusion 360は設計の「履歴ベース」な編集(パラメトリック設計)が主役です。寸法拘束、ジオメトリ制約、アセンブリ内の部品の動作、外部の製造データやCNC加工データとの連携など、現実のモノづくりと直結する機能が揃っています。
簡単に言えば、Blenderは「作る喜びを形にする道具」であり、Fusion 360は「正確な設計を現実の部品へ落とし込む道具」です。
どちらを選ぶかは、あなたが作りたいものの性質と、将来的に目指すキャリア像で決まります。創作を中心にしたい人にはBlender、設計・製造の現場に近づきたい人にはFusion 360が向いています。
ライセンスと学習難易度の違い
Blenderは完全無料・オープンソースで、誰でも自由にダウンロードして使えます。学習資源は多く、日本語の教材も豊富で、個人の趣味から学校の課題まで幅広く対応します。サードパーティのアドオンも多数あり、機能を追加することが容易です。
Fusion 360はサブスクリプション形式の商用ソフトです。個人の無償プランや教育機関向けの無料ライセンスも提供されていますが、企業での本格利用や長期プロジェクトには料金が発生します。クラウド機能の活用が前提となる場面も多く、ネット環境が作業のスピードに影響することもあります。学習難易度はBlenderに比べて「設計思想の理解」が鍵になるため、初学者には若干ハードルを感じる人もいます。ただし公式ドキュメントが整理されており、段階的に学べば着実に上達します。
データ形式と互換性の特徴
ファイル形式の互換性は現場でよく話題になります。BlenderはFBX・OBJ・GLTFなどの一般的な3D形式に対応しており、ゲームエンジンやレンダリングパイプラインへ移行する際の相性が良いです。
Fusion 360はSTEP・IGES・STLなど、機械設計に適した形式を中心に取り扱います。部品データの輸出入を通じて他のCADソフトと連携する場面が多く、企業のワークフローに適合させることが重要です。両者を使い分ける際には、最終成果物の用途(映像・ゲーム用か、現実部品の製造か)を軸に、どのファイル形式が最も重要かを事前に決めておくことが効率的です。
| 項目 | Blender | Fusion 360 |
|---|---|---|
| 主な用途 | アニメーション・ゲーム素材・キャラクター | 機械設計・アセンブリ・製造準備 |
| ライセンス | 無料・オープンソース | サブスクリプション形式(個人の無償プランあり) |
| 学習曲線 | やや急だがチュートリアルが豊富 | 設計思想が難しい部分がある |
| 主なファイル形式 | FBX・OBJ・GLTF など | STEP・IGES・STL など |
まとめと使い分けのコツ
最終的な結論としては、作りたい成果物と作業の流れに応じて選ぶのが最も大事です。創作的なモデリングやアニメーションを楽しみたいならBlender、現実世界の部品を設計して製造につなぐ場合はFusion 360を使うのが良いというのが一般的な見解です。学習を進める際には、まずBlenderの基本操作を身につけてから、必要に応じてFusion 360の機能に移行するのがスムーズです。さらに、両方を使い分けることで、3Dの幅がぐっと広がります。最後に、情報源をいくつか選んで学習することが重要です。公式ドキュメント・公式チュートリアル・日本語の解説動画を組み合わせ、地道に練習を重ねていきましょう。
Blenderは無料で高機能な3Dツールとして有名ですが、Fusion 360はエンジニア向けの機能が充実した有料ツールです。私が友達と話して感じたのは、Blenderは“作る楽しさ”を爆発させる力が強く、Fusion 360は“正確さと現実の部品へ落としこむ力”が強いということです。もしも将来、ゲーム制作やアニメ制作を志すならBlenderを第一候補に、機械設計や製造プロセスを学びたいならFusion 360を視野に置くとよいでしょう。二つの道具を同時に使いこなせると、創作の幅と現実世界の適用力が同時に高まります。





















