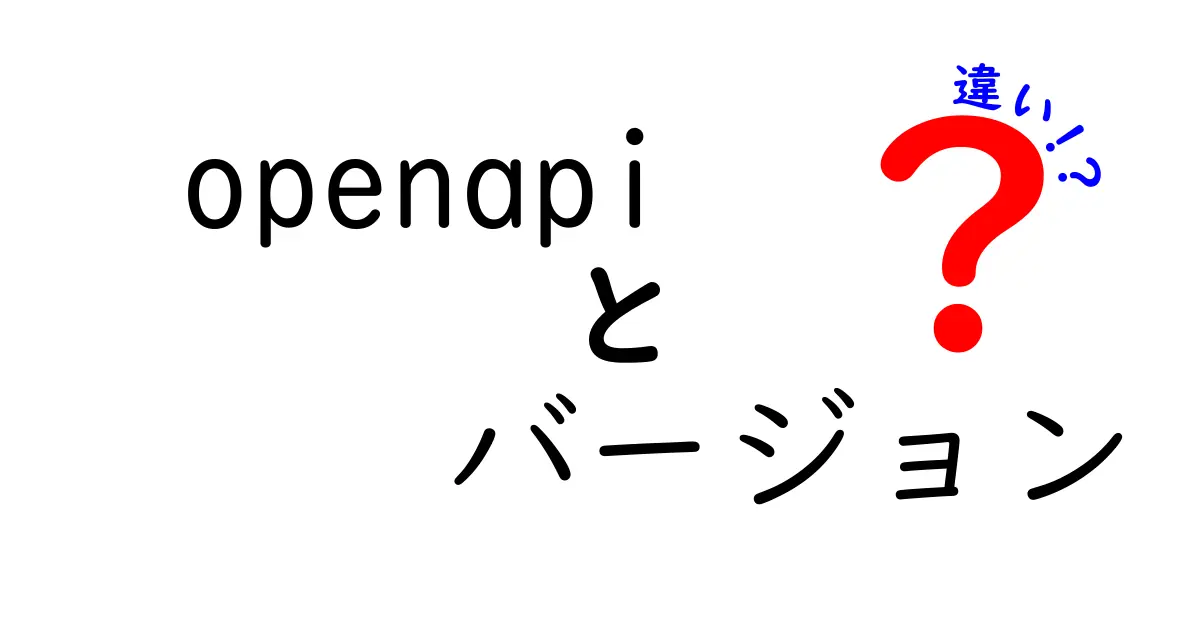

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
OpenAPIのバージョン違いを知るとAPI仕様が読めるようになる
OpenAPIはAPIの設計図を機械 readable 仕様として表現する仕組みです。旧称のSwaggerと混同されがちですが、仕様のバージョンが違うとどの機能が使えるか、どの書き方で定義を記述するかが変わります。特にバージョン2.0と3.xでは入力するファイルの構造そのものが異なり、パラメータの定義場所やリクエストボディの扱い、レスポンスの参照方法などが一新されました。2.0ではすべてが一つの大きな定義内に詰め込まれていたのに対し、3.xではcomponentsという再利用可能な部品を中心に設計するスタイルが推奨され、
これが大型のAPIを分かりやすく保つコツになります。
また、3.xではサポートする仕様要素が増え、セキュリティスキームの定義方法やリクエストの形式が柔軟になっている点も大きな違いです。
なぜバージョンが分かりにくいのか
現場で実務をしていると、どのバージョンのOpenAPIを参照するべきか迷う場面があります。理由はシンプルで、- 仕様書の書き方が大きく異なること、- 使用しているツールや自動生成の挙動がバージョンに強く依存すること、- 互換性の問題があることです。2.0の仕様に慣れている人は3.x系の新機能を使いこなすのに追加の学習が必要になる場合があり、逆に3.x系の新機能を取り入れたいが既存のコードベースが古い場合には段階的な移行計画が不可欠です。この記事では、そうした現実的な悩みを解決する考え方を紹介します。開発の初期段階から仕様を揃える工夫をしておけば、後での統合やドキュメントの自動生成にも好影響を及ぼします。
OpenAPIというキーワードを友達に説明するなら、こう話します。OpenAPIはAPIの設計図を機械にも読める形で書くための共通言語。つまり、何ができて、どう使うのか、どんなデータを返してくれるのかを、機械と人間の両方が理解できるように整理する道具です。3系と3.1の話をするとき、僕が大切だと感じるのは再利用性の考え方の違いと、リクエストボディとパラメータの分離の仕方です。例えば、同じ型のデータを何度も書く代わりにcomponentsで部品化して、必要な場所で呼び出せるようにするのが3.xの強み。こうすると、APIの追加や変更の際にも影響範囲を小さく保てます。つまりOpenAPIは“設計図の言い換え”であり、チーム間のコミュニケーションを滑らかにするための道具であると捉えると、難しさよりも使い道の楽しさが見えてきます。さらに、ドキュメント自動生成ツールとの相性も良く、成果物を自動で整然と作ってくれる点が魅力です。





















