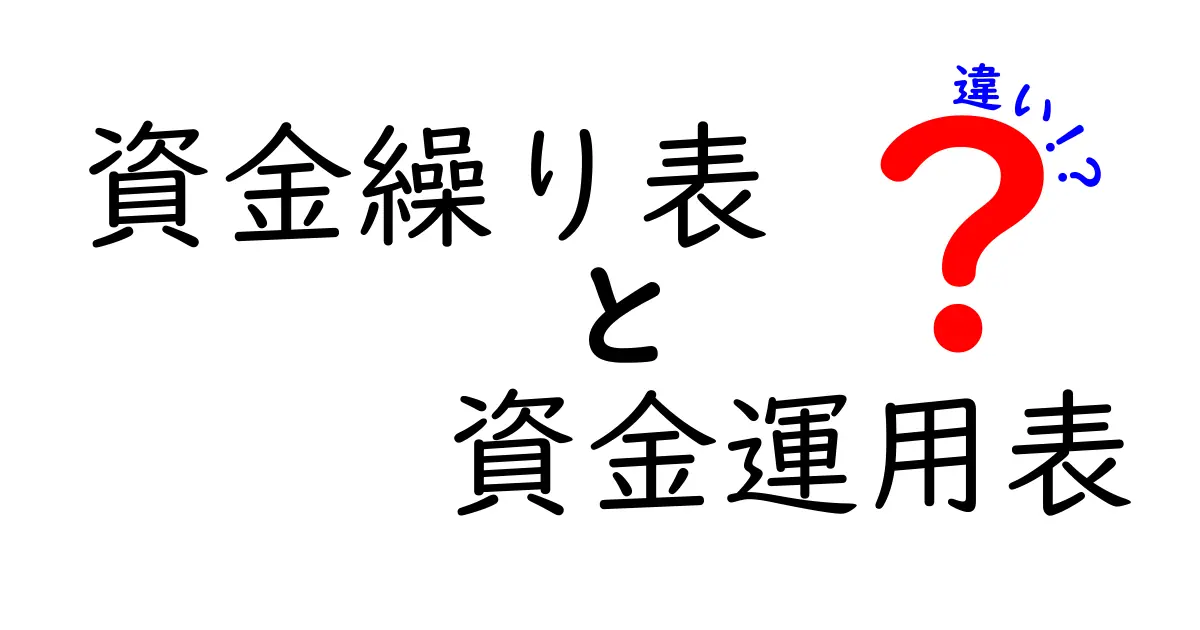

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
資金繰り表と資金運用表の基本概念の違いを理解する
資金繰り表とは、企業のお金の出入りを日付ごと・月ごとに「今後どのくらいの現金が手元に残るか」を予測する表です。現金が不足しそうな場面を回避するための道具で、主に入金タイミングと出金タイミングの差を管理します。具体的には、売上の入金予定日、仕入れ代金の支払日、人件費、家賃、税金などの支出の発生日を一覧化します。企業が急な資金不足に陥らないよう、現金の不足を前もって把握し、資金繰りを改善するための対策を検討します。日々の資金繰りは、短いスパン(週次・月次)で監視・更新することが重要です。特に中小企業では、月初の現金余力と下旬の出金計画の差を意識することで、資金ショックを避けられます。
この表の作成には、銀行の入金データ、売上の予想、請求・支払のタイミング、そして会社の口座の残高の推移を反映させます。過去の実績データを基に、次月の入出金を現実的に見積もることが大切です。
なお、資金繰り表を作るときは、「手元現金の実測値」と「将来の入金・支出の予測値」の差を常に意識します。これがわかれば、急な資金需要が起きたときに銀行に相談するタイミングや、短期借入を検討するべきかどうかが見えてきます。
資金運用表の基本概念と使い方
資金運用表は、現金の「余剰」が出た場合に、それをどう運用するかを計画する表です。ここでいう運用には、投資の検討、余剰資金の預金・定期預金化、余裕資金の返済優先順位の設定、新規借入の検討などが含まれます。資金繰り表が現金の入出金の予測中心であるのに対し、資金運用表は現金の「使い道」の計画です。資金が手元に増えたとき、どのように眠らせず増やすか、あるいはコストを下げるかを考えます。
運用はリスクとリターンのバランスを取りながら、短期・中期・長期の目標を見据えます。たとえば、短期の余剰金を預金に預けて安全性を確保しつつ、顧客への前払金や信用保証料の支払いを最適化する、という具体的な動きがあります。資金運用表を作るときには、金利動向、流動性の確保、リスク管理の三つを軸に考えると整理しやすいです。現金をただ眠らせておくより、正しく運用して社の成長につなげるためには、運用方針を明文化して関係者と共有することが大切です。
使い分けと実務のポイント
実務での使い分けはシンプルです。資金繰り表は日々の現金の入りと出の流れを把握するための道具で、資金運用表は余ったお金をどう活用するかを決める道具です。両方を併用すると、資金の「今の状態」と「これからの使い方」を同時に管理できます。実務のポイントは次のとおりです。
1) 週次・月次の更新ルールを決める。
2) 予測値はなるべく現実的に、過去の実績を反映させる。
3) 重要な指標には現金不足の兆候、資金余剰の再投資方針、キャッシュフローの安定性を挙げる。
4) 関係部署と共有することで、急な変更にも素早く対応できる体制を作る。
実践のステップと注意点
実務での作成手順を、初心者にも分かる形で整理します。
1) 1か月分の収入と支出のデータを集約する。
2) 予定日を日付で並べ、入金と出金を時系列で割り当てる。
3) 余裕が出た場合の運用案を考える。
4) 実績と予測を定期的に比較し、ずれを修正する。
5) 表を見ながら、どのタイミングで借入を検討するか、どのタイミングで投資を増やすかを判断する。
このとき重要なのは、「現金の実測値」と「将来の予測値」の両方を大切に扱う点です。表だけを追いかけると、現実の資金状況と乖離してしまいます。現場の実感を重ねながら更新することが、安定した資金管理には不可欠です。
さらに、リスク管理の観点から、急な支出や売上の変動に備え、予備費を一定割合確保しておくと安心です。最後に、表の見方を共有することで、経営者だけでなく現場のスタッフも資金の動きを理解でき、意思決定のスピードが上がります。
資金運用表って、ただの数字の羅列だと思っていたけど、実は財布の使い方を整理する道具なんだよね。友達とカフェで話しているように、余ったお金をどう活かすかを考えると、将来の計画がぐっと具体的になる。
「今この瞬間の現金を守る」ことと「余ったお金を増やす」こと、この二つを同時に考えるには、資金繰り表と資金運用表をセットで使うのが一番手っ取り早い。もし資金運用表だけを作っていても、現金の流れがどう動くか分からなければ意味が薄い。だから、まずは資金繰り表で現金の流れを把握してから、余裕資金の運用を検討する、そんな順番が自然だと思う。





















