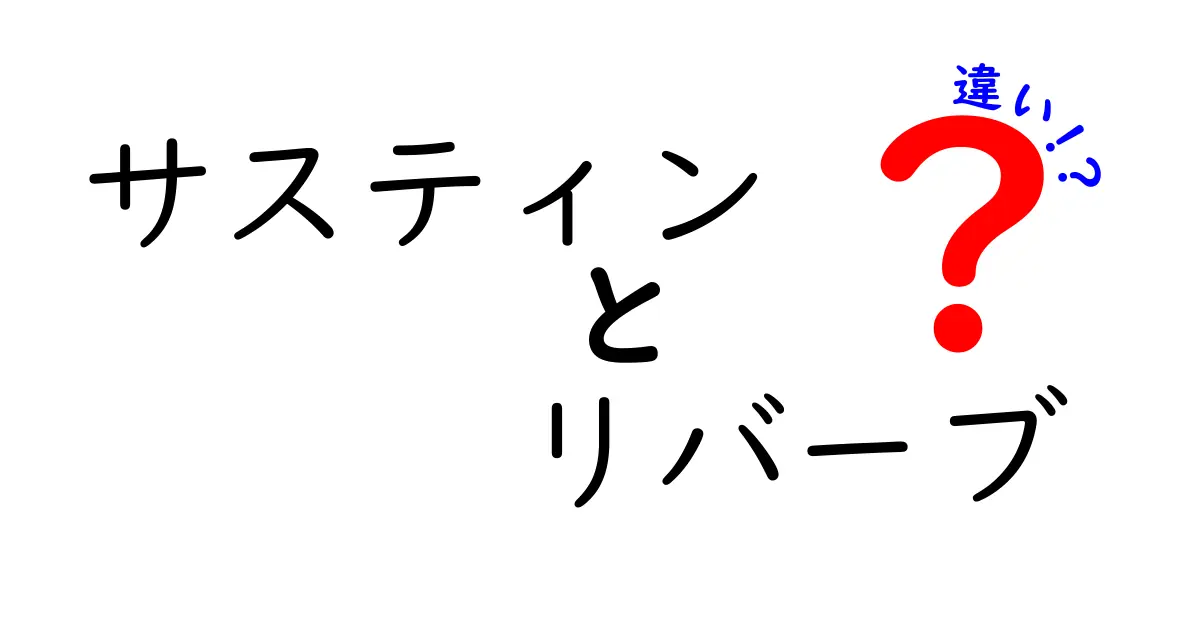

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サスティンとリバーブの基本を押さえる
ここでは「サスティン」と「リバーブ」がどう違うのか、音楽制作の現場でどのように使い分けるのかを、中学生にもわかるやさしい言葉で説明します。サスティンは音の長さの話、リバーブは空間の話です。それぞれが持つ性質を知ると、曲の印象が変わり、楽器の鳴り方が自然かどうか、ボーカルが抜けるかどうか、などの判断がしやすくなります。サウンドデザインの基礎として、サスティンとリバーブの役割を体感できる練習を交えながら、実例を交えて紹介します。まず覚えておきたいのは、サスティンはダイレクトな音の持続、リバーブは空間の響きを模したエフェクトであり、それぞれが音の輪郭に違う影響を与えるという点です。音量を下げたり上げたりするだけの作業ではなく、音色の広がり方、距離感、そして聴感上の「現実感」をどう作るかが大事です。リバーブの長さを長くするか短くするか、サスティンを適度に保つか切り捨てるか、などの判断は曲全体のテンポ、ジャンル、歌詞の伝えたい意味にも影響します。音楽理論の難しさを避けつつ、手触りの感覚で学べる点がこの二つのエフェクトの魅力です。これから詳しく見ていくと、サスティンとリバーブは決して同じものを指していないことが分かります。積極的に使っていくと、音の距離感が変わり、聴く人の耳に残る印象も変わるため、実際の制作現場では異なる場面で別々に使い分けられるのです。サスティンは楽器が発する生の音の延長線上で働くことが多く、聴こえの密度や輪郭を保ちながら音を伸ばします。一方でリバーブは空間全体の響きを模した仮想的な空気を作る役割があり、同じ音でもリバーブの有無や設定次第で音が“遠く”感じたり“近く”感じたりします。こうした理解を持つと、ミックスの時に何を優先するべきかが見えやすくなります。音の立ち上がり方と減衰の仕方には個性があり、ボーカルのサスティンが長いときはリバーブを控えめにする、逆にサスティンが短い楽器には軽いリバーブを加えるなどの工夫が生まれます。最終的には、曲のジャンルや演出の意図に合わせて、サスティンとリバーブの組み合わせを選ぶことが、聴く人にとって心地よい音作りにつながるのです。
実用のポイント: 違いをどう使い分けるか
このセクションでは、実際の制作で「サスティン」と「リバーブ」をどう使い分けるかのコツを、具体的な場面別に見ていきます。まず、ボーカルを主役にした楽曲では、サスティンを適度に保ちつつリバーブを控えめにすることで、歌詞の明瞭さと感情の伝わりやすさを両立します。次にギターやピアノなどの伴奏楽器では、サスティンを調整して音の長さのバランスを取り、リバーブを少しだけ足して空間の厚みを与えると、全体のサウンドがまとまります。さらに、リバーブを使う場面で注意したいのは“音が抜ける瞬間”と“反射の時間”です。音が鳴ってすぐにリバーブが効きすぎると、肝心の音が先に消えてしまい、聴感上の力強さが失われます。逆にリバーブを控えすぎると、音が無機質になり聴き疲れの原因にもなります。こうしたバランスを取るには、曲のテンポ、メロディのライン、歌詞の意味を意識して、各楽器に対して最適なサスティンとリバーブの組み合わせを見つけることが大切です。ここで活用したいのが、耳で聴いて判断する練習と、DAWのメトリクス機能・プリセット機能・オートメーション機能を使った細かなコントロールです。例えば、曲がブレークする瞬間にはサスティンを少し落としてリバーブの尾を伸ばすことで、ドラマ性を作れます。逆にサビの盛り上がりでは、サスティンを少し長めにして歌声を支えつつ、リバーブを薄くして歌詞をクリアに伝えると効果的です。最後に、リスナーの耳を意識して、過度なエフェクトで曲全体の聴感を壊さないよう心がけましょう。音楽は科学でも芸術でもあり、サスティンとリバーブの組み合わせはその両方の要素を活かす鍵になります。練習を重ねて、自分の曲に最適な処方箋を作り上げてください。
サスティンとは何か: 音の伸びと表現を決める要素
サスティンは音の持続時間のことです。例えばピアノのノートやギターの弦音がどのくらい残るかを決め、音の輪郭をどれだけ長く保つかを決定します。サスティンを伸ばすと音の幅が広がり、和音のつながりが滑らかになる一方で、過度に長いと音が煩雑に聴こえることもあります。実際のミックスでは、ボーカルや楽器ごとにサスティンの長さを微調整して、他の音とぶつからずに聴こえるように調整します。この作業はエンベロープの設定(ADSRのDとS)やダイナミクス処理、軽い飽和感の追加と組み合わせると効果的です。例えば曲のサビで語尾をしっかり伸ばしたい場合はサスティンを長めに、キレのあるリフには短めに設定するのがコツです。音の距離感を感じさせたい場合にもサスティンの長さを操作して、聴き手に音の位置を伝えます。なお、サスティンだけでなくリバーブやディレイといった他のエフェクトとバランスを取ることが重要です。ボーカルが主役の楽曲では、サスティンを適度に抑え、歌詞の明瞭さを確保するのが基本です。以上の感覚は、練習を重ねるほど耳が自然に鍛えられ、どの音にどの程度のサスティンを与えるべきか判断できるようになります。サスティンは音楽の感情を長く伝える道具であり、リバーブとの組み合わせ次第で曲の雰囲気が大きく変わる重要な要素です。
リバーブとは何か: 空間の雰囲気を作るエコーの仲間
リバーブは音が出てから耳に届くまでの間に、部屋の形や材質、反射の性質によって生まれる複雑な響きを模したエフェクトです。現実の部屋の大きさや天井の高さ、壁の素材によって反射が変わり、音の“空間感”が決まります。リバーブを多く使うと音が広がり、音源の距離感が変化します。映画のサウンドトラックのように壮大な空間を作ることも可能ですが、使いすぎるとボーカルが埋もれたり、細部の言葉が聞こえなくなることがあります。リバーブにはタイム(長さ)、プリディレイ(先に出る遅延)、反射の数・強さなど複数のパラメータがあり、それぞれ曲のジャンルに合わせて調整します。実際にはボーカルには控えめ、合唱やギターのストロークにはもう少し大きめ、というように目的に応じて使い分けます。リバーブを選ぶ際には“空間のイメージ”を先に決めておくと調整が楽です。ホール型は大きな空間感、プレート型は金属的でクリアな響き、ルーム型は身近な部屋のような反射、などがあり、曲の雰囲気に合わせて組み合わせを探っていくのが楽しい作業です。リバーブは音を“遠く見せる”“近くに感じさせる”力を持つ一方、適切なバランスを超えると聴き疲れの原因にもなるため、曲全体の設計を意識して使うことが大切です。
実用のポイント: 違いをどう使い分けるかのまとめ
このセクションでは、実際の制作で「サスティン」と「リバーブ」をどう使い分けるかのコツを、具体的な場面別に見ていきます。まず、ボーカルを主役にした楽曲では、サスティンを適度に保ちつつリバーブを控えめにすることで、歌詞の明瞭さと感情の伝わりやすさを両立します。次にギターやピアノなどの伴奏楽器では、サスティンを調整して音の長さのバランスを取り、リバーブを少しだけ足して空間の厚みを与えると、全体のサウンドがまとまります。さらに、リバーブを使う場面で注意したいのは“音が抜ける瞬間”と“反射の時間”です。音が鳴ってすぐにリバーブが効きすぎると、肝心の音が先に消えてしまい、聴感上の力強さが失われます。逆にリバーブを控えすぎると、音が無機質になり聴き疲れの原因にもなります。こうしたバランスを取るには、曲のテンポ、メロディのライン、歌詞の意味を意識して、各楽器に対して最適なサスティンとリバーブの組み合わせを見つけることが大切です。ここで活用したいのが、耳で聴いて判断する練習と、DAWのメトリクス機能・プリセット機能・オートメーション機能を使った細かなコントロールです。例えば、曲がブレークする瞬間にはサスティンを少し落としてリバーブの尾を伸ばすことで、ドラマ性を作れます。逆にサビの盛り上がりでは、サスティンを少し長めにして歌声を支えつつ、リバーブを薄くして歌詞をクリアに伝えると効果的です。最後に、リスナーの耳を意識して、過度なエフェクトで曲全体の聴感を壊さないよう心がけましょう。音楽は科学でも芸術でもあり、サスティンとリバーブの組み合わせはその両方の要素を活かす鍵になります。練習を重ねて、自分の曲に最適な処方箋を作り上げてください。
友達とこの前、学校の合唱コンクールの話をしていたんだ。音作りの話題になって、僕はサスティンとリバーブの違いをどう説明すれば伝わるかなと考えた。結局、サスティンは音の“長さ”を決めるパンチ力、リバーブは音の“居場所”を作る空間づくりだと思うと、すごく分かりやすくなる気がした。もし歌声が少し長く伸びて聴こえたら、それはサスティンが効いている証拠。だけどそのままだと歌詞が埋もれそうなら、リバーブを控えめにして距離感を調整する。僕らの合唱にもこの二つを組み合わせる練習が必要だと気づいた。実は音楽を勉強していくうちに、テクニックより感覚の方が大事だと感じる場面が多い。だから、家で自分の声を録って、サスティンとリバーブをいじりながら聴く練習を続けたい。こうして自分の曲に合う“処方箋”を見つけることが、音楽の楽しさを深める一歩になると思う。





















