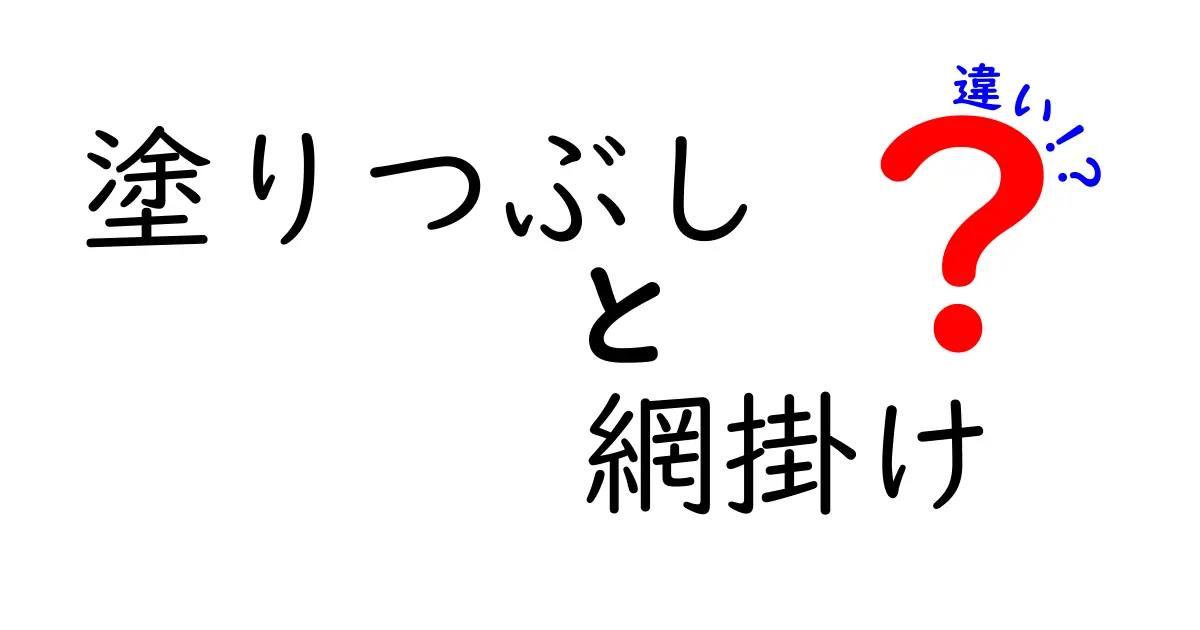

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
塗りつぶしと網掛けの基本を押さえる
塗りつぶしと網掛けは、図や表、プレゼン資料でよく使われる基本的な用語です。塗りつぶしは範囲を一色の面として“完全に塗る”操作を指します。実際にはセルの背景を塗りつぶしたり、図形の面を一色で覆うことで、強調したい情報を一目でわかるようにします。強さや色は自由に選べ、背景の色を統一することで資料全体の見た目が整います。対して網掛けは線の模様で領域を覆う方法です。斜めの線が規則的に入ることで、面全体を「塗りつぶした」ように見せつつ、文字や図の中身が見える余地を保つことができます。網掛けは“透け感”と“区切り感”を同時に作る技術で、デザインのトーンを穏やかに保つのが得意です。塗りつぶしが色の塊を強く打ち出すのに対し、網掛けはパターンで情報の読みやすさを調整します。現場での適用例として、WordやExcel、PowerPointなどのオフィスソフト、あるいはデザインソフトでの塗りつぶしと網掛けの使い分けが挙げられます。塗りつぶしは色の違いで重要度を示すのに適しますが、過度な色は読みづらくなることにも注意が必要です。網掛けは色を使わず陰影を作るので、モノクロ印刷やカラー印刷のどちらでも安定して読みやすい見た目を保てます。現場での実務感覚として、塗りつぶしは一発で目的を伝える力、網掛けはデザインの柔らかさと読みやすさを両立する力を持つと覚えておくとよいでしょう。
用途別の使い分けと実例
使い分けの基本ルールと具体例を詳しく見ていきます。まず、強調したい情報には塗りつぶしを使い、背景とデータの区別をはっきりさせましょう。次に、資料の整理や図の階層を示す場合には網掛けを用いて“透け感”を作ると、読み手の目に優しく印象が落ち着きます。実務の場面として、Excelのセル背景を赤で塗りつぶすとデータの重要性がすぐ伝わります。一方、表の見出しや注記部分に網掛けを使えば、文字の可読性を保ちながら区切りを視覚化できます。デザイン設計のコツは、色味のバランスと模様の控えめさを意識することです。塗りつぶしと網掛けの使い分けは、資料の読みやすさとデザインの印象を大きく左右します。
| 項目 | 塗りつぶし | 網掛け |
|---|---|---|
| 適している場面 | 重要情報の強調・全体の背景統一 | 区切り・読みやすさの演出 |
| 印刷時の見え方 | 濃く出やすい | 安定して読みやすい |
| デザイン上の印象 | 力強い | 落ち着いた雰囲気 |
放課後、友達と資料づくりをしていたときのこと。『塗りつぶしと網掛け、どう違うの?』と聞かれて、私はこう答えました。塗りつぶしは範囲を一色で覆う、つまり色の塊をはっきり作る技術。だから重要な部分を目立たせたいときにピタリです。網掛けは線の模様で領域を覆い、色を塗るよりも薄く見せつつも情報を区切る効果があります。だから、デザイン上の区切りや見た目の柔らかさを出したい場合に適しています。実際の資料では、塗りつぶしは一撃で注目を集める力があり、網掛けはページの読みやすさを保つリズムを作ります。
\n




















