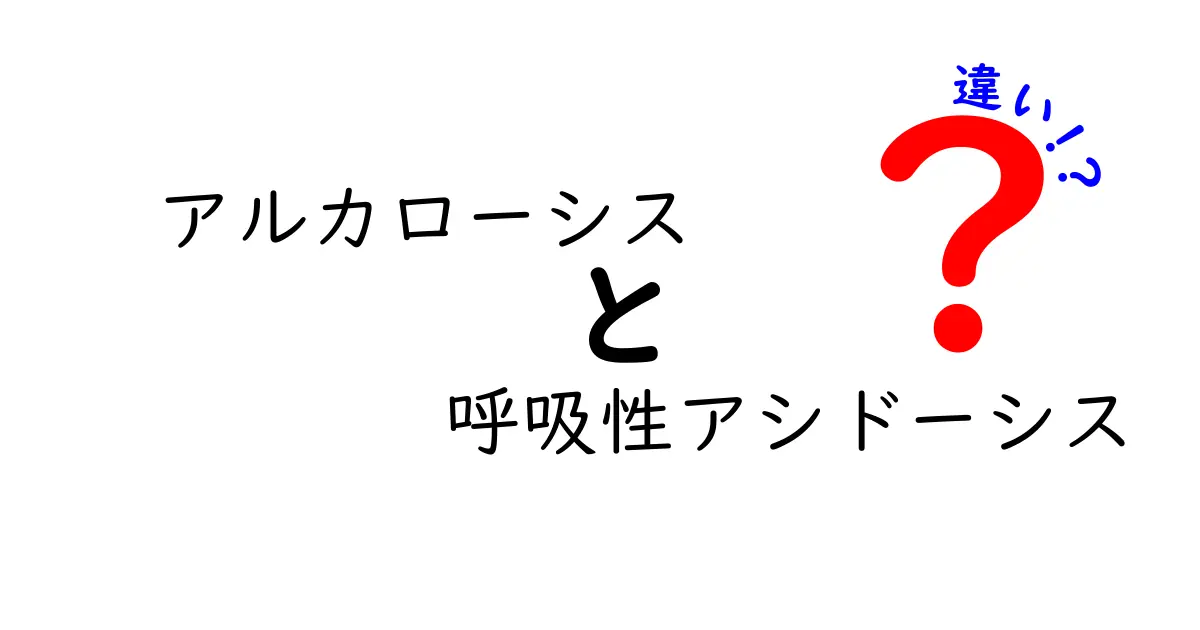

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:アルカローシスと呼吸性アシドーシスの基礎
血液の状態を表す指標にpHという数値があり、7.35から7.45が通常の範囲です。アルカローシスは血液のpHが7.45を超えて上がる状態で、脱水や嘔吐、過換気などが原因になることが多いです。一方、呼吸性アシドーシスは血液のpHが低下し、原因はCO2の排出がうまくいかないこと、つまり呼吸がうまく機能していない状態です。CO2は体内の酸性を強くする要因であり、肺の換気が悪いと体内にCO2がたまり、pHは下がりやすくなります。
ここで大切なポイントは、酸塩基平衡の土台をなすのはCO2とHCO3-のバランスであり、それが崩れると体は別の仕組みで補正しようとします。
正常の範囲を超えると、体はどう反応するのでしょうか。アルカローシスでは血液が過度に「塩基性」になろうとするため、呼吸を速くしてCO2を吐き出すか、腎臓がHCO3-を排出して体内の塩基を減らそうとします。反対に呼吸性アシドーシスでは、体は腎臓に働きかけてHCO3-を再吸収して体内の塩基を取り戻そうとします。こうした補正は急性と慢性で速度が変わり、慢性の方が補正が進んでいるように見えることがあります。
違いを決める3つのポイント
酸塩基の状態を決める際に、まず見るべき3つのポイントがあります。
1つ目はpHの方向です。アルカローシスはpHが7.45を超え、呼吸性アシドーシスは7.35未満に向かいます。2つ目はCO2の値です。呼吸性アシドーシスではCO2が高め、アルカローシスの呼吸性例ではCO2が低かったり正常域だったりします。メタボリックなアルカローシスではCO2は必ずしも高くありません。3つ目はHCO3-の値です。メタボリックなアルカローシスではHCO3-が高くなりやすく、呼吸性アシドーシスでは補正としてHCO3-が徐々に上がることがあります。これら3つの指標を組み合わせて、実際の状態を読み解くのが基本です。
補足として、補正の方向性をイメージするためには、体がどう「補う」かを理解するのが役に立ちます。肺は呼吸でCO2を出し入れするエンジン、腎臓はHCO3-を作ったり排出したりする「調整役」です。肺は急性のときの主役、腎臓は慢性のときの主役になることが多く、補正の速度と程度はこの違いで変わります。こうした補正のしくみを知っておくと、ABGと呼ばれる血液ガスの数字を見たときに「今どの段階か」「これからどうなるか」を読み解きやすくなります。
実際の診断と対処
現場では arterial blood gas ABG という血液検査を使ってpH CO2 HCO3-を一度に見ることが多いです。pHとCO2の組み合わせで呼吸性か代謝性かを判断し、さらにHCO3-の変動を見て補正の方向性と程度を読み取ります。急性の呼吸性アシドーシスではCO2が急に上がりpHが低くなりますが、腎臓が補正を始めるまでには時間がかかるため、初期対応は気道確保や換気の改善が中心です。慢性の場合は腎臓がHCO3-をしっかりと作り出し、補正が進むため治療方針も長期的な視点になります。アルカローシスの場合は嘔吐や利尿薬の乱用、過換気症候群などが原因として挙げられ、これを緩和するには原因を取り除くことが基本です。水分バランスや塩分の管理、栄養の補充も重要です。
治療は原因の除去とともに、安定した呼吸と血液のpHを保つことを目標にします。病院では、状況に応じて酸性の流れを抑える薬、あるいはアルカリ性の流れを整える薬が使われることがありますが、家庭での自己判断は危険です。専門の医療機関で適切な検査と治療を受けることが大切です。
まとめと理解を深めるポイント
アルカローシスと呼吸性アシドーシスは、血液のpHがどの方向に動くかと、CO2とHCO3-の関係で特徴づけられる症状です。pHが高いか低いか、CO2が高いか低いか、HCO3-の変化を組み合わせて判定します。実際には酸塩基平衡の嘘のようなケースもあり、複数の要因が絡むことが多いです。身近な例としては過換気や嘔吐、腎機能の変化などがあります。正確な判断と適切な治療のためには、医療機関での検査と医師の診断が不可欠です。自分や家族の体に異変を感じたら、無理をせず早めに相談することをおすすめします。
たとえば友だちと雑談する感じで、アルカローシスと呼吸性アシドーシスの違いを深掘りします。CO2が体内でどう働くのか、pHが高くなると体の動きがどう変わるのかを、日常の例えを交えてゆっくり語り合います。酸性とアルカリ性のバランスが崩れると、体はどう補正するのか、肺と腎臓がどんな役割を果たすのかを、難しい専門用語を避けながら理解していきましょう。
次の記事: 体温と基礎体温の違いを徹底解説!測定のコツと日常への活かし方 »





















