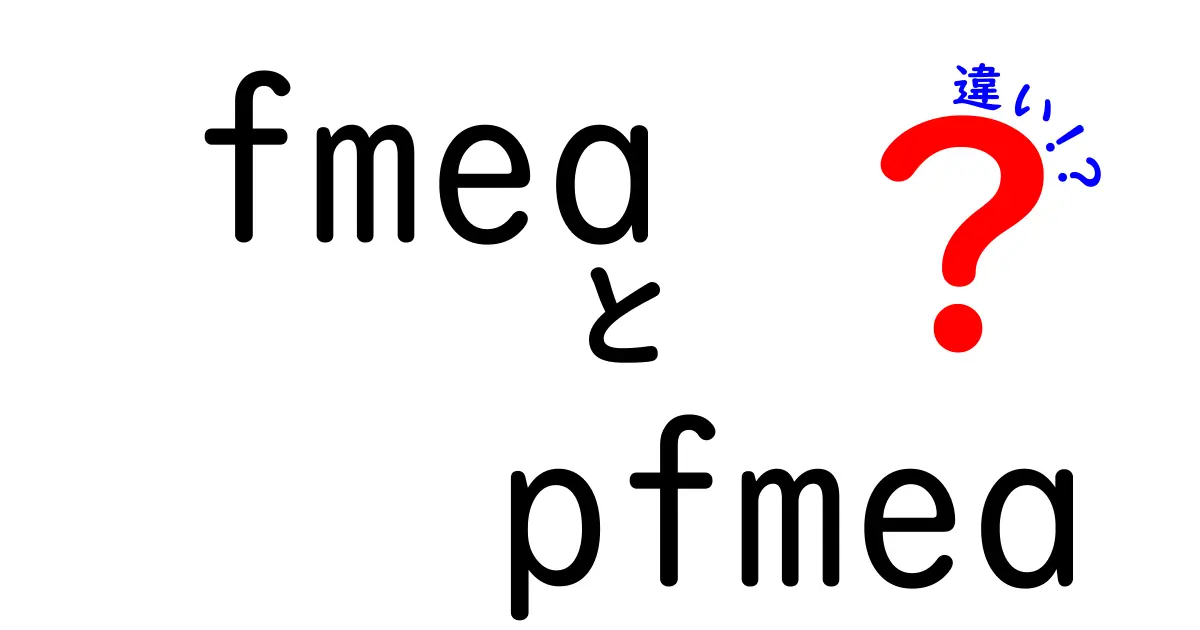

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
fmeaとpfmeaの違いを知るための基礎ガイド
このガイドは「fmea」と「pfmea」を正しく使い分けるための基礎を、難しくなく理解できるように解説します。まず結論から伝えると、FMEAは設計と工程の両方をカバーする総称的な手法の呼び名であり、pfmeaはそのうち特に「プロセス(工程)」の分析に絞った具体的な応用です。つまり、設計段階での機能や形を決めるときに使うのが fmea、実際の作業の流れを改善するために使うのが pfmeaという風に理解しておくと、現場での話がすっきり分かります。
この違いは、学習の順序にも影響します。設計段階でのリスクを前もって予防する考え方を学ぶと、その後の製造段階で起こり得るミスを想定する pfmea にスムーズに移行できます。
次に、実務での進め方の基本を整理します。まずは「何を守るべきか」を明確にすること、次に「どの時点で対策を打つか」を決めること、最後に「改善のための優先順位をどう決めるか」を数字で表すことです。これらのポイントを押さえると、品質の改善が段階的に見える化され、関係者全員が同じ目標を共有しやすくなります。
実務で使うときには、設計と製造の両側面を同時に見られるチームが理想です。設計者と現場の作業員、品質保証の担当者が協力して進めることで、より現実的な対策が生まれやすくなります。この記事では、 fmea と pfmea の基本的な考え方と、現場での具体的な運用のコツを、なるべく平易な言葉で紹介します。
fmeaとは何か?
fmea とは Failure Mode and Effects Analysis の略で、製品の設計段階で起こりうる故障モードとその影響を洗い出して評価する手法です。設計段階では「どういう機能をどう動かすべきか」を決めるので、機能の欠陥がどんな問題を生むのかを前もって考えることが大切です。具体的には、機能を分解して想定される故障モードを列挙し、それぞれの故障がもたらす影響を整理します。次に「原因は何か」「現在の対策はどれくらい機能しているか」を記録し、重大度・発生確率・検出度の3つの指標を掛け合わせてリスクの優先順位を決めます。この作業の要点は、最もリスクの高い部分を先に改善することで、製品の信頼性を高められる点です。設計変更が必要な場合は、設計者・エンジニア・品質保証のメンバーが協力して対策を検討します。現場での検証と連携を重ねるほど、実際の製品が市場に出るときの失敗を減らせるのです。
FMEA は製品の“機能”と“設計上のリスク”を同時に見張る役割をもち、品質保証の土台を固める手法です。
pfmeaとは何か?
pfmea は Process FMEA の略で、主に 製造プロセスや作業手順そのもののリスクを分析するための手法です。設計が完成した後、工場のラインや作業の流れで「どこで、どんな故障が起き得るか」を探します。作業手順、設備の状態、材料の供給、人の動きなど、プロセスの各要素を一つずつ見直して、故障モードと影響、原因、現状の対策を整理します。 pfmea では 重大度・発生・検出 の指標を用いて、どの工程を優先的に改善するべきかを判断します。結果として、ラインでの不良を減らし、作業ミスを減らすための標準化や教育に役立ちます。現場の改善は、品質コストの削減や納期の安定にもつながり、従業員の作業負荷を適切に管理することにも寄与します。
放課後、友だちと fmea と pfmea の話をしていた。彼は“設計の難しさ”がいちばんの壁だと思っていたが、僕は違う角度から話した。『fmeaは設計での穴を埋めるための道具、pfmeaは現場のどう動けばミスが減るかを考える道具だよ』と説明すると、彼は「なるほど、工程の中での小さなミスも積み重なると大きな問題になるよね」と納得した。僕らは、詳しい数値の話よりも、まず「何を守るべきか」を共有することの大切さを話し合った。こうした会話を重ねると、教科書の知識が実社会の工夫へと結びつくのを実感できる。





















