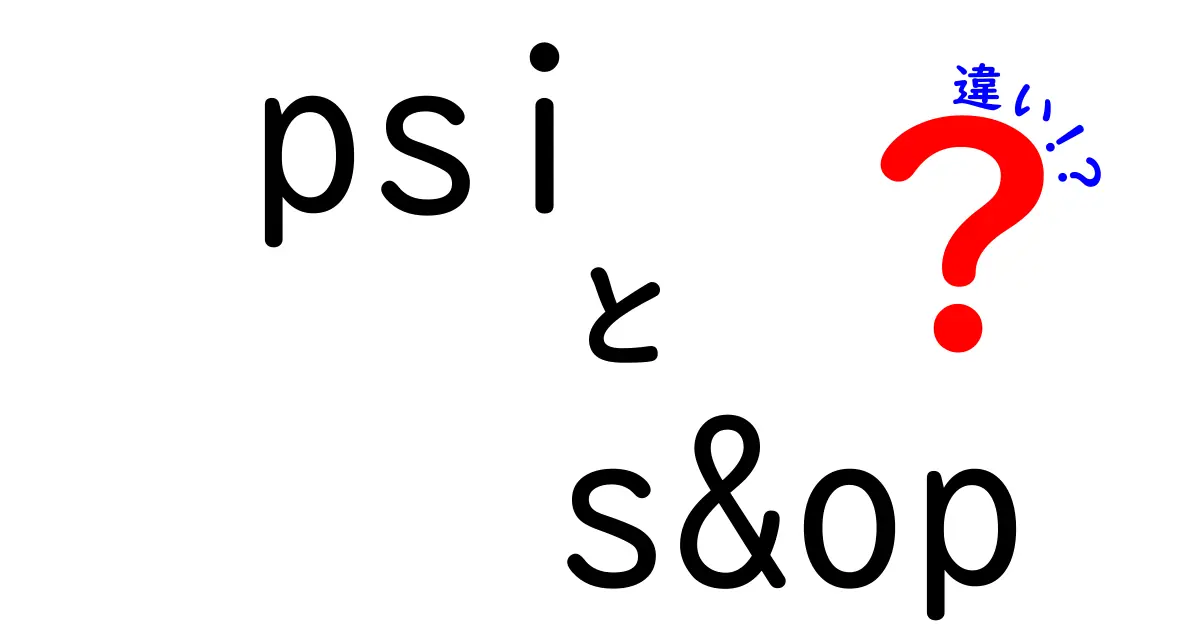

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
psiとS&OPの違いを理解しよう
psiとS&OPの混同は、現場と経営の間にある“認識のズレ”が原因で起こりやすいです。
このセクションでは、まずそれぞれの定義と目的を分けて理解し、次に実務での使い分けのヒントを紹介します。
PSIは生産計画と在庫管理の現場レベルの最適化に焦点を当て、日々の生産ラインの動きや部品在庫を細かく調整します。
対してS&OPは組織横断の長期的な需給バランスを決めるプロセスで、月次や四半期ごとの需要予測と生産能力の整合性を図ります。
この違いを正しく理解すると、現場の指示と経営の意思決定が噛み合わず生じる遅延を減らせます。
以下では、両者の基本概念を順番に深掘りします。
なお、両者は目的が異なるがゆえに“つなぐ工夫”が必要です。
この点を意識して読み進めてください。
まずは用語の背景を整理します。
PSIはProduction(生産)、Scheduling(スケジューリング)、Inventory(在庫)の頭文字を取ったもので、現場の実行計画を日次・週次レベルで回す枠組みです。
生産ラインのボトルネックを特定し、資材の入荷タイミングや加工順序を最適化して、欠品を減らし納期遵守を高めます。
この段階ではデータの粒度が細かく、現場の安定稼働を最優先に考えます。
一方、S&OPはSales(販売)とOperations(業務)を横断して、Forecast(需要予測)とCapacity(生産能力)をリンクさせるマネジメントレベルの活動です。
月次の合意形成を通じて、財務的な影響も含めた総合的な戦略が決まります。
つまり、PSIは現場の“どう動くか”を決め、S&OPは組織全体の“何をどれだけ動かすか”を決める――この2つの役割分担を理解することがスタート地点です。
次に、現場と経営の視点を比較していきます。
PSIは「現場の安定稼働」と「短期の納期遵守」を最重要指標として、OEEやリードタイム、在庫回転率といった指標を用いて日次単位で評価します。
S&OPは「需要と供給の整合性」と「財務的な健全性」を最優先に、欠品リスク、過剰在庫、キャッシュフローなどの指標を月次・季節的な視点で追います。
このように、評価軸と時間軸が異なるため、同じデータでも見方が変わります。
実務では、データの一貫性を保ちながら、現場の実行性と経営の方針をつなぐ連携ルールを作ることが重要です。
さらに、以下のポイントを押さえると、 psiとS&OPの使い分けが現場で自然に理解されます。
・PSIは短期・現場寄りの実行計画、S&OPは中長期・経営寄りの合意形成という時間軸の違いを前提にする。
・データの粒度と分析の深さを分ける。現場には細かな実行データ、経営には総括的な需要予測と資源計画を用いる。
・両者をつなぐ“橋渡し”の仕組みを作る。例えば、PSIで確定した日次計画をS&OPの月次計画の入力として扱い、需要予測の前提を現場データで検証する、などです。
この橋渡しがうまくいくと、意思決定の速度と質が大きく向上します。
PSI(生産・スケジューリング・在庫)とは何か
PSIは生産計画・工程順序・在庫管理の三点セットを日々の運用に落とし込む実務の中核です。
具体的には、どの製品をどの順番で生産するか、どの部品をどのタイミングで手配するか、在庫の過不足をどう抑えるかを、データを基に決定します。
この時に使われる代表的な指標には、リードタイム、OEE、在庫回転率、欠品率などがあります。
PSIは現場の可用性と実行性を向上させることを最優先に置くため、現場の声を反映させやすい柔軟性が求められます。
また、MESやERPと連携させることで、作業指示と在庫状況をリアルタイムで同期させ、遅延を最小化します。
実務での注意点としては、過度な細分化に走りすぎないことが挙げられます。細かすぎる計画は現場の混乱を招きやすく、逆に意思決定の遅延を生むことがあります。現場の実務キャパシティとデータの品質を見極め、適切な粒度で計画を組むことが大切です。
加えて、在庫の安全率とリードタイムの安定性を同時に管理することで、予期せぬ需要変動にも柔軟に対応できます。
S&OP(Sales and Operations Planning)とは何か
S&OPは、 sales(販売)と operations(オペレーション)を横断して、需要と供給のバランスを整える組織横断の会議型プロセスです。
典型的には月次の会議で、販売予測、マーケティングの施策、製造能力、購買リードタイム、財務目標を横断的に検討します。
S&OPの成果物は、実行可能な月次プランと、場合によっては翌月以降の中期計画を含みます。
このプランは在庫コストや欠品リスク、キャッシュフローといった財務的影響を含めて評価され、経営陣の意思決定に反映されます。
S&OPがうまく機能すると、戦略と現場の間にあるギャップを埋め、組織全体のパフォーマンスを安定させます。
実務のコツとしては、以下の三つを意識します。
1) 現場データと需要予測を一貫して扱うデータモデルの整備
2) 部門間のコミュニケーションルールと意思決定の権限の明確化
3) 財務影響の定量化とリスク評価の組み込み
この三つをそろえると、S&OPはより実効性の高いものになります。
また、S&OPの議論は週次・月次でアップデートされ、半年~一年先のシナリオも検討します。
長期の戦略と短期の実行を一致させることが、競争力の源泉です。
実務での使い分けと注意点
以下の表は、代表的な違いと使い分けのポイントを端的に示したものです。
現場のデータ品質を高めつつ、経営の方針を反映させる設計を心がけましょう。
この表から分かるように、PSIとS&OPは時間軸と意思決定のレベルが異なる点が大きな違いです。
両者を効果的に連携させるには、PSIで作られた現場の確定計画をS&OPの inputs(需要予測・資源制約)として活用する仕組みが基本です。
現場データの品質を高めること、合意形成のプロセスを透明化すること、そして財務影響を定量化することが、失敗を防ぎ、組織全体のパフォーマンスを高めます。
まとめ
PSIは日々の生産と在庫を最適化する運用レベルの枠組み、S&OPは組織横断の需給バランスを決定する管理レベルの枠組みです。
この二つは相互補完的であり、互いを支え合う形で機能します。
正しく使い分け、うまくつなぐことで、現場の安定稼働と経営の成長戦略を同時に実現できます。
実務では、データの品質管理、透明な意思決定プロセス、財務的影響の可視化が鍵となります。
これを意識して取り組むと、組織の計画力は確実に高まるでしょう。
S&OPの会議って、数字が大事だけどそれ以上に“人の会話”が結果を動かす場だよ。売れるはずの予測が現場の実感とズレてしまうとき、会議室の空気が変わる。データは嘘をつかないけれど、解釈の仕方で道が変わる。だからこそ、S&OPは“合意の作り方”を学ぶ場でもある。私は、現場の声と財務の目標をどう結びつけるかを意識して会議に臨むようにしている。どういう仮説を立て、どんなデータで検証するのか—その小さな積み重ねが大きな納得へと繋がる。





















