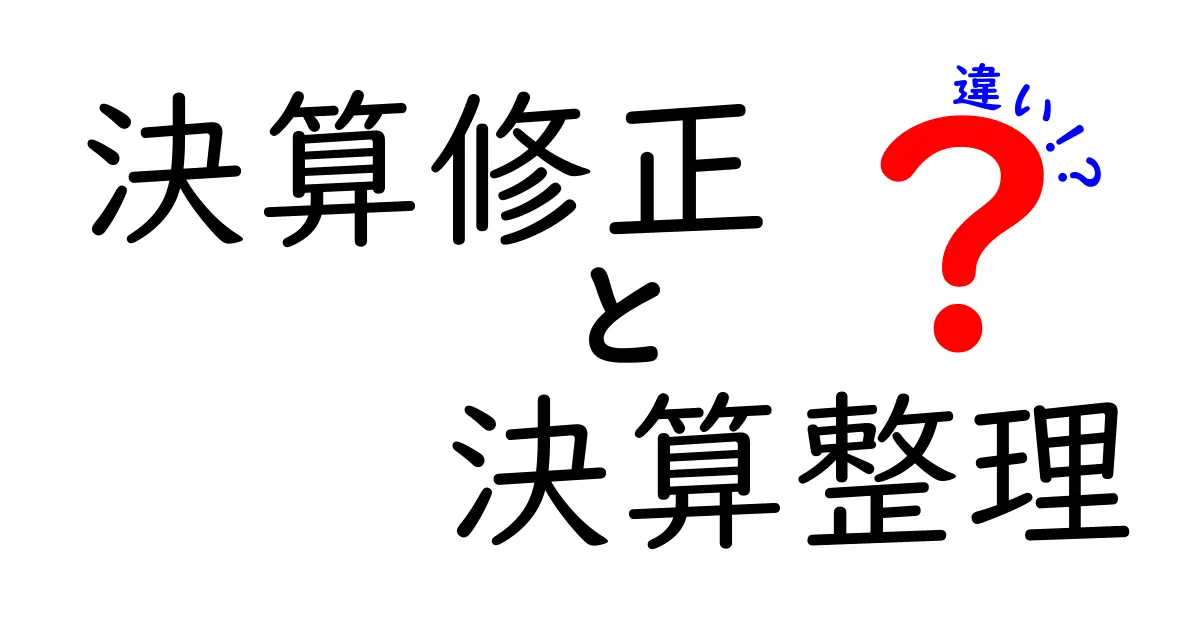

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
決算修正と決算整理の基本を把握する
決算修正と決算整理は、会社の会計を正しく反映させるための作業ですが、意味が似ているため混同されやすい言葉です。まず、決算修正とは、過去の会計処理の誤りや不足を正す行為を指します。たとえば、売上を二重に計上してしまっていたり、費用計上が漏れていたりといった数字の誤認識を直す作業です。こうした修正は、過年度に遡って修正することが多く、正しい利益や資産の金額を表示するために必要です。決算修正が行われると、財務諸表の過年度の金額も修正後の数字に置き換えられ、監査や税務申告にも影響を及ぼします。ここで大切なのは、修正の原因となった事実をはっきりさせ、どのような誤認識だったのかを社内で共有することです。
次に、決算整理は、期末直前後の時点で「来期に正しく反映させるための準備作業」を指します。整理は過年度の修正とは違い、主に来期の観点で、未払いや前受、前払費用、棚卸資産の評価、減価償却の見積りの見直しなどを行い、現在の期の数値と来期の数値の整合性を保つことを目的とします。整理は法令上の義務というよりも、会計方針の適用の適切さを確保するための工程です。こうした作業は、決算日後の数日から数週間の間に集中的に行われ、財務報告の信頼性を高める重要なステップとなります。
実務での違いを具体例で把握する
実務での理解を深めるには、具体的な事例を見ていくのが近道です。たとえば、過年度の売上を誤って10万円多く計上していたとします。この場合、決算修正として「売上高」を10万円減らす仕訳を行い、同時に「売掛金」または「未収金」の科目を調整します。
この修正は過年度の財務諸表に影響を及ぼし、株主総会の資料や税務申告にも影響します。一方、決算整理では来期の正しい認識を前提に、未払費用の見積りを見直したり、棚卸資産の評価を修正したりします。例えば棚卸資産の評価額を実務上の実在在庫と比べて過大に計上していた場合、整理の段階で適正額へ修正します。これにより、来期の売上原価や利益が正しく反映され、キャッシュフローの見通しも安定します。
整理と修正は仕訳の方向性が異なり、修正は過去の数字を正す、整理は現在と来期の数字の整合性を保つという役割分担になります。現場では、証拠資料の突き合わせ、関係部門の確認、会計方針の適用の一貫性の確認を順序立てて進めることが求められます。特に、監査対応を想定する場合には、修正の背景を明確に説明できることが重要です。
- 修正と整理の対象期間の違い … 修正は過年度を対象にすることが多く、整理は現期と来期を中心に扱うことが多い。
- 影響を受ける財務諸表 … 修正は過年度の財務諸表、整理は来期の財務諸表の整合性に影響を与える。
- のちの対応 … 修正は株主・監査・税務に影響するため慎重な検証が必要、整理は来期の運用を円滑にするための準備と捉える。
ポイントと誤解を解く
多くの誤解は、「修正と整理は同じ作業」と思われがちな点にあります。実際には性質が異なるため、適用する会計資源や影響の範囲も変わります。ここで覚えておきたいのは、誤認識はなぜ起きたのかを検証する手順が先に来ること、そして来期へ影響を及ぼす整理は現行の会計方針の適用の妥当性を確認することです。もしこの二つを混同してしまうと、財務諸表の信頼性が低下し、税務申告にも矛盾が生じるリスクがあります。現場では、原因の特定、根拠資料の整理、修正と整理の区別を明確にし、社内の承認フローを通じて文書化することが基本です。最後に、実務におけるポイントとして、①根拠資料をそろえる、②会計方針の適用を統一する、③監査対応を想定した説明資料を用意する、という3点を挙げておきます。
今日は決算修正の入り口にある“発見と検証”の姿勢について。修正は単なる数字の訂正ではなく、なぜ間違いが起きたのかを理解する作業です。現場の私たちは、数字が変わると誰が一番困るかを想像し、現実のビジネスの動きと結びつけます。修正を通じて、数字は物語を語る道具だと気づきます。真実を追求する姿勢こそ、良い決算を作る第一歩です。





















