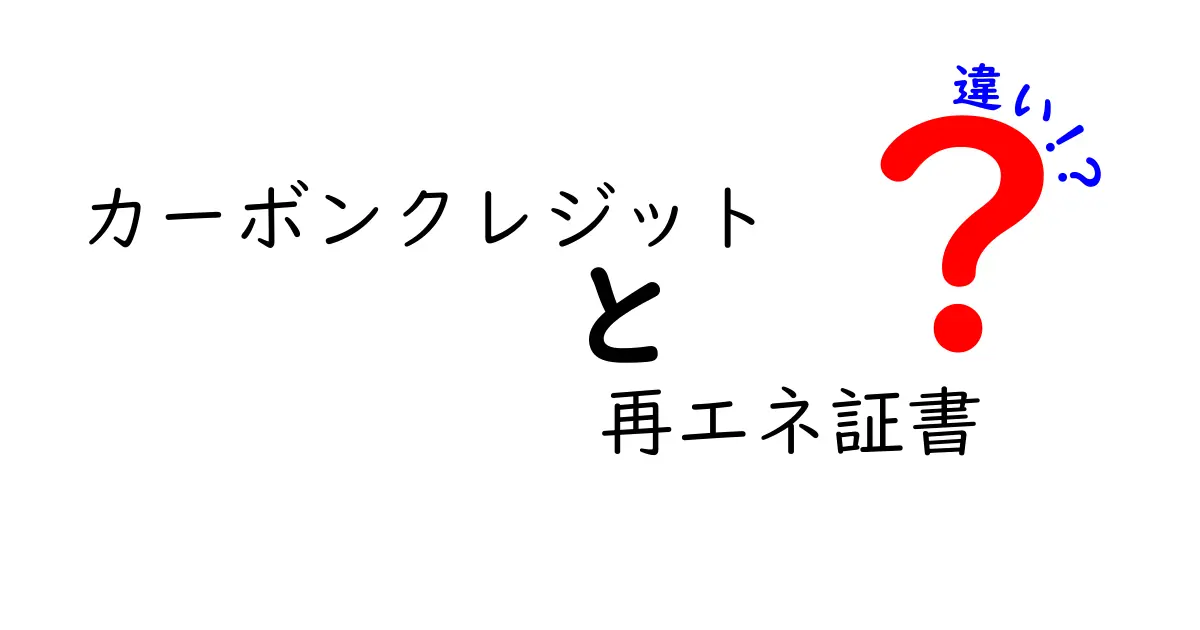

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カーボンクレジットと再エネ証書の基本を押さえる
カーボンクレジットとは、一定量のCO2を削減することが実現されたと証明する証書です。換言すれば、地球全体の排出を減らす「成果」を市場で取引できる商品という意味です。発行されるのは、森林保全や新たな低炭素技術の導入など、実際に排出削減が確認できるプロジェクトです。企業が自社の排出量を補うためにこのクレジットを購入することで、直接の排出量削減が難しい状況でも、間接的に地球温暖化対策を進めることができます。ここで重要なのは、追加性(その削減がなければ実現しなかった成果であること)と、永続性(削減が将来も継続すること)を満たしているかの評価です。
この評価が甘いと、実際には排出が減っていなくてもクレジットが増えるだけの不正が起きやすくなります。
一方、再エネ証書とは別の仕組みで、再生可能エネルギーの「発電量」を証明する証書です。電力の物理的供給と証書の取引は分離されることが多く、企業や自治体はこの証書を用いて、購入した電力の再エネ比率を示すことができます。再エネ証書はCO2排出の直接的な削減を意味するわけではなく、「再エネ由来の電力を使っています」という事実を証明する手段として機能します。証書は発行元や制度設計によって信頼性が左右されるため、取引相手の信用や適用される規制を確認することが大切です。
この点が、カーボンクレジットと大きく異なるポイントです。
この二つの仕組みの共通点は、いずれも“環境改善を促すための市場の仕組み”であることです。ただし、使われる場面と目的が異なります。カーボンクレジットは排出の削減量をオフセットする商品、再エネ証書は再エネを使った電力の証明書として機能します。理解を深めると、企業が自社の方針に合わせてどちらを優先すべきか、あるいは組み合わせて使うべきかが見えてきます。
現場での活用を考えると、まず自社の目標(例えば事業のカーボンニュートラル達成時期や再エネ比率の目標)を明確にし、その上で適切な証書を選ぶことが大切です。
違いと使い方の実務を整理する
実務での違いを整理すると、以下のポイントがわかりやすくなります。
・目的の違い: カーボンクレジットは排出量の「補填・オフセット」を目的、再エネ証書は電力の再エネ由来を証明する目的。
・発行と監督: カーボンクレジットはプロジェクトごとに発行され、追加性や永久性が問われます。再エネ証書は発電事業者や制度機関が認証します。
・取引の性質: 双方とも市場で売買できますが、価格形成の要因が異なります。
まとめとして、両者の目的と使い方を混同しないことが重要です。企業が実際に何を目指しているのか、どのようにして信頼できる形で環境改善を評価するのかを考えると、自然と最適な組み合わせが見えてきます。
私たち消費者も、購入を検討する際には、証書の発行元、期間、追加性、証書の種類が自分の価値観に合っているかをチェックすることが大切です。最後に、透明性の高い情報を選ぶことが長期的な環境貢献につながります。
再エネ証書についての雑談風小ネタ: 友だちとカフェで再エネ証書の話をしていて、私はこう思った。再エネ証書は“再エネを使っています”という事実を証明する手段であり、電力の実際の供給と証書の関係は必ずしも直結しない。だから、企業が再エネ証書を買う理由は“見栄え”ではなく、持続可能性の戦略としての信頼性確保や法的要件の達成にあることを深掘りしたい。証書の品質や発行元の信頼性をしっかり確認することが大切だと、友人と話していて実感した。





















