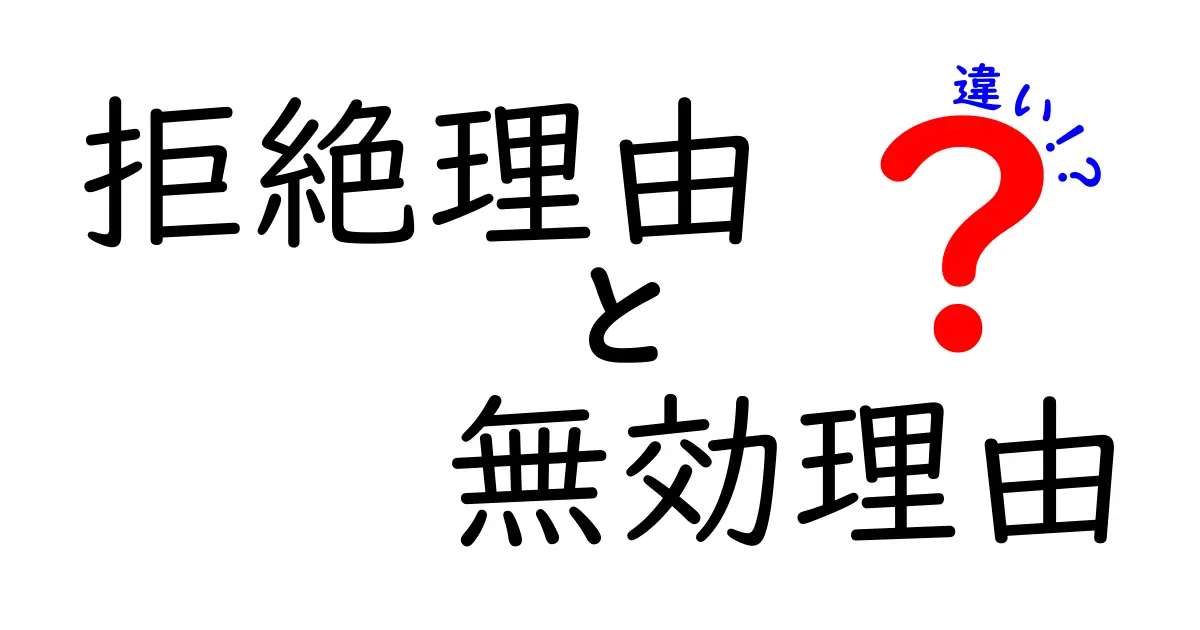

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
拒絶理由と無効理由の基本を押さえよう
みなさんは「拒絶理由」と「無効理由」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも法的な判断の理由を指しますが、意味と使われる場面は大きく違います。拒絶理由は申請が通らない理由、無効理由はすでに成立している権利を取り消す・無効にする理由という違いです。これを理解するのは、特に特許や商標、契約の場面で役立ちます。拒絶理由は「これでは申請が受理できません」という審査の判断、無効理由は「この権利が成立していない・失われた」という判断です。
この二つの言葉の本質的な違いは、場面が「新しい権利が受理されるかどうか」か、「既に成立している権利が有効かどうか」か、という点に集約されます。つまり、拒絶理由は「新規性・適法性・実質要件が満たされていない」という申請側の壁、無効理由は「既存の権利の有効性を争う壁」です。
この違いを理解すると、資料の読み方、書き方、そして申請・訴訟の流れがぐんと分かりやすくなります。
特に中学生の皆さんには、身近なルールづくりの例と結びつけて覚えると覚えやすいです。
実務での使い分けと具体例
実務では、拒絶理由は審査官が「この点は不足しています」と指摘して審査の継続を求める場面で現れます。例えば新しい技術やデザインの申請を出したとき、新規性・進歩性・産業上の利用可能性などの基準を満たしていない場合に拒絶理由が提示されます。反対に無効理由は、既に成立している権利を取り戻す・取り消すことを目的に争われます。実務上は、訴訟で相手の権利が成立していないと判断されれば無効理由が適用されることが多いです。
以下のポイントを押さえると、違いがわかりやすくなります。
- 誰が判断するのか(審査官 vs 裁判所・審決庁)
- 何を判断基準にしているのか(新規性・公序良俗・実用性などの基準 vs 権利の存続要件)
- 申請の段階か、既存の権利の効力を争う段階か
具体的なケースを想定すると良い練習になります。
例1:新規のアイデアを出して特許を申請したが、既存の技術と同一性が指摘されて拒絶理由が示された場合。
例2:すでに成立している商標権を別の企業が使っているとして無効理由を主張する裁判が起きた場合。
今日は『拒絶理由』について、雑談風に深掘りします。拒絶理由は、何か新しい申請をしても“そのまま通らない理由”のことです。学校の日課の変更提案を思い浮かべてみてください。新しいルールを作るとき、現場はまず“その案が現状と矛盾していないか・他のルールと衝突しないか”を確認します。もし矛盾があれば素早く修正を求めるのが拒絶理由の役割。これを覚えておくと、提出物の読み方や審査の流れがグンと分かりやすくなります。
前の記事: « 判断料と実施料の違いを徹底解説:いつ払うべきかを分かりやすく解説





















