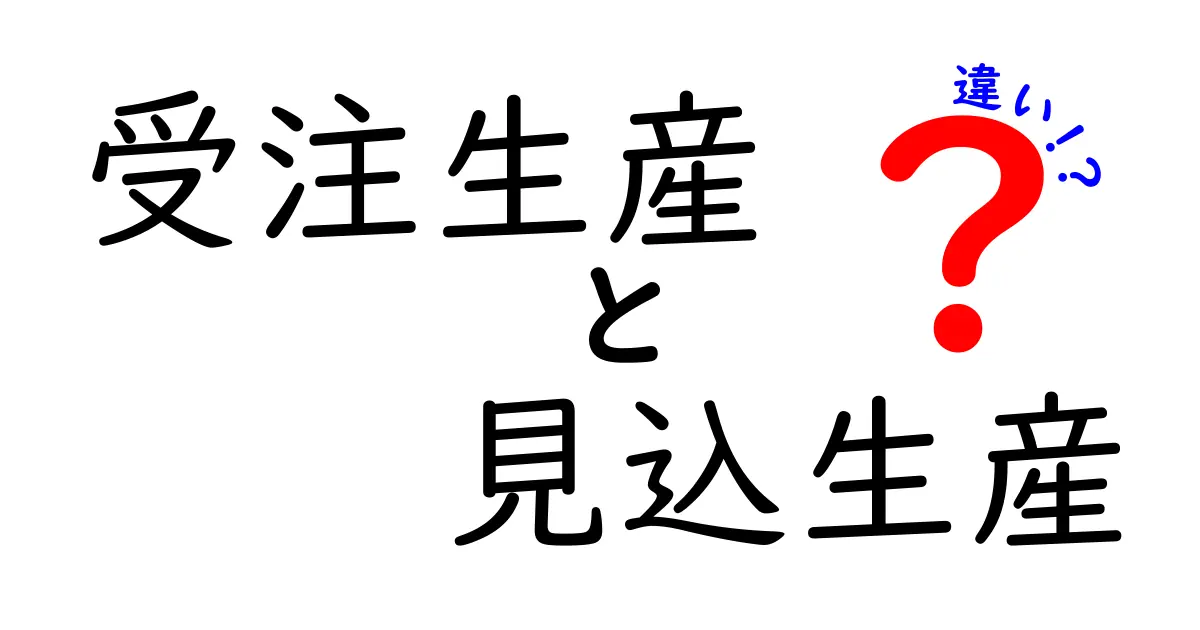

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
受注生産と見込生産の基本を理解する
この話は、消費者の手元に商品が届くまでの流れを左右する大事な考え方です。受注生産とは、名前のとおり「お客様の注文を受けてから製造を開始する方法」です。
一方、見込生産は「需要を予想して事前に生産しておく方法」です。どちらが良いかは、ビジネスの性質や市場の動き、リードタイムの長さ、在庫コスト、キャッシュフローなどによって決まります。
例えば、カスタムメイドの家具や高級時計は受注生産が向いています。発注が入ってから材料を取り寄せ、職人が加工を開始します。その間、他の注文が入っても即座に対応できる反面、納期が長くなりやすいという特徴があります。
一方、日用品や人気の商品は見込生産で在庫を確保する方が、すぐに出荷できる利点があります。需要が安定していれば、在庫を適切に回転させて売上を伸ばしやすいです。
この二つの方法を理解することは、メーカーだけでなく小売業やサービス業にも役立ちます。何を作るか、いつ作るかを決める指針になるからです。
違いの実務的なポイントとリスク
実務では、両方の方法にそれぞれ長所と短所があります。受注生産の最大のメリットは「在庫リスクが低いこと」です。受注が確定してから材料を発注するので、過剰在庫や売れ残りの心配が少なく、キャッシュフローの安定につながります。しかし、納期を守る責任が重く、追加入荷や生産遅延が発生すると顧客満足度が下がる可能性があります。逆に、見込生産は「納期短縮と高い出荷率」を実現しやすく、需要が安定していれば売上を大きく伸ばせる可能性があります。しかし需要を読み誤ると在庫が過剰になり、値下げ競争や値引きの圧力が生まれます。従って、予測の精度を高める仕組みと、需要の変化に対応する柔軟性が鍵になります。さらに、季節性やイベントの影響、製造リードタイム、仕入れ先の供給状況、品質管理のコストなど、複数の要因を総合的に評価することが重要です。
この違いを理解しておくと、新製品の投入時期を決めるときにも役立ち、在庫の過多や欠品を防ぐ計画が立てやすくなります。
在庫リスクとキャッシュフローの観点
在庫リスクとキャッシュフローは、企業の安定性に直結する重要な要素です。受注生産は注文が確定してから材料を購入するため、初期コストを抑えやすく、在庫費用を最小限にできます。
ただし、個別対応のための設計変更や特注作業が増え、工数が増えることで原価が高くなる場合があります。
一方、見込生産は大量生産のスケールメリットを得やすく、原価を下げやすいのが特徴です。しかし需要を読み違えると過剰在庫が発生し、資金が長期間滞留するリスクがあります。
この点を防ぐには、需要データの透明性を高め、仕入れ・生産計画をリアルタイムで更新する仕組みが不可欠です。
また、価格設定の戦略も大切です。高需要期にはプレミアムを設定し、低需要期にはセールや割引で回転を早めるなど、キャッシュフローの安定化を図ることができます。
実務での選択ガイド
実務でどちらを選ぶべきかを決めるためのポイントを整理します。まず市場の性質を分析し、需要の予測精度を評価します。予測が高精度なら見込生産、予測が難しい・周期的に変動する場合は受注生産を検討します。次にリードタイムと納期の要求度を考え、顧客満足度とコストのバランスを取ります。さらに製品の単価と利益率を確認し、大量生産のスケールメリットを活かせるかどうかを判断します。最後に、柔軟性のあるサプライチェーンを整え、急な需要変化にも対応できる体制を整えます。表にまとめると、以下のようになります。
このガイドを基に、あなたの事業に最適な戦略を選んでください。
| 特徴 | 適用例 |
|---|---|
| 在庫リスクの大小 | 受注生産は低い、見込生産は高い |
| 納期の安定性 | 受注生産は遅れやすい、見込生産は安定しやすい |
| コスト構造 | 受注生産は変動費が中心、見込生産は固定費を抑えやすい |
| 需要予測の難易度 | 難しいほど受注生産が有利 |





















