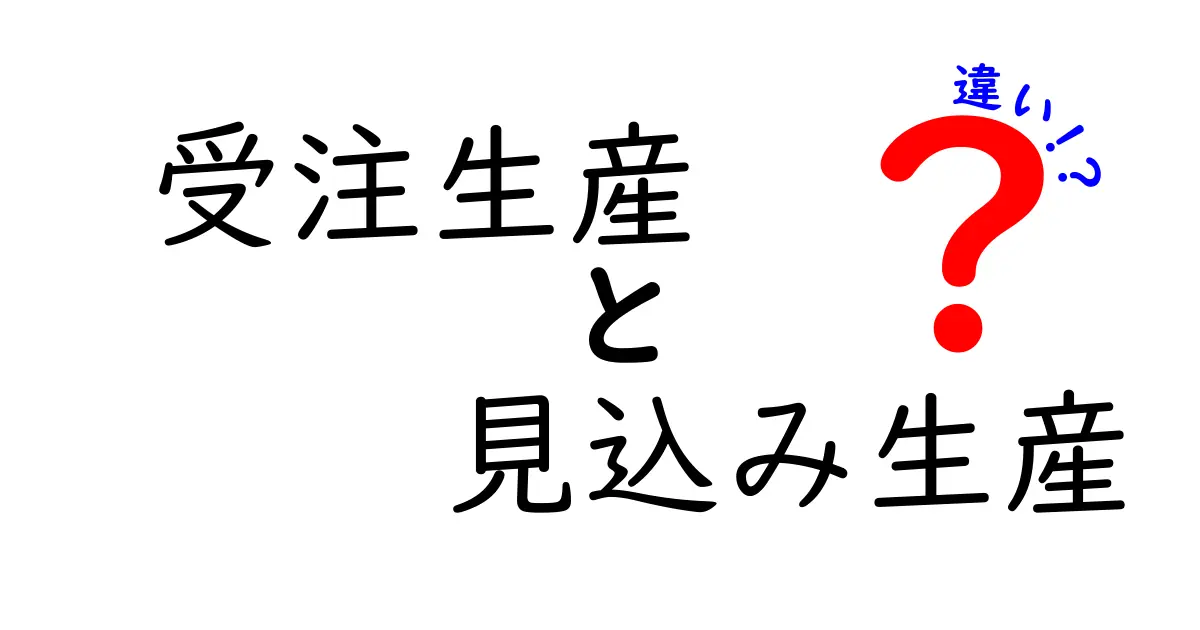

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
受注生産と見込み生産の違いを徹底解説
受注生産と見込み生産は、商品の作り方や在庫の持ち方を決める「考え方の違い」です。受注生産はお客さんの注文が入ってから製品を作る方法で、在庫を抱えずに済む点が大きなメリットです。これにより資金の流れが安定し、売れ残りのリスクが低くなります。見込み生産は需要を予測して前もって作る方法で、納期を短くしやすく、すぐ出荷できる体制を作りやすいのが特徴です。
ただし予測が外れれば在庫が増え、廃棄や価格競争での損失が発生することもあります。
この2つの考え方を正しく理解すると、企業はコストと納期のバランスを取りやすくなります。特に「製品の性質」「市場の安定性」「顧客の期待」を見極めることが重要です。ここから、仕組みの違い、メリット・デメリット、実務での使い分けのポイントを順に解説します。
読み進めると、なぜ一部の企業がハイブリッド戦略を選ぶのかも分かるはずです。
仕組みの違いと流れ
受注生産の基本は「注文を受けてから設計・生産を始める」という流れです。注文が来ないと生産を開始しないため、在庫コストを抑えられます。とはいえ、注文後のリードタイムが長くなりがちなので、設計変更を受けても対応できる柔軟性や部材の確保が大切です。部材を標準化して複数の商品で共用する工夫、製造ラインを小さなモジュールに分けて変更を速くする工夫などがよく使われます。
見込み生産は需要を予測して前もって生産します。季節商品や人気商品で使われることが多く、納期の短縮につながります。ですが、需要が外れると在庫が過剰になり、資金の無駄遣いが発生します。予測精度を高めるためには過去データの分析や市場の動向観察が不可欠です。
このように、受注生産と見込み生産では「作るタイミング」と「在庫の量」が大きく異なります。企業は自社の製品特性に合わせて、どちらが有利かを判断します。
メリットとデメリット
受注生産のメリットは在庫リスクが低いこと、資金繰りを柔軟に保てること、顧客の細かな仕様に対応しやすいことです。
デメリットは納期が長くなりやすい点と、需要が急増した場合の生産量調整の難しさです。小さな企業ほど急な受注増に対応する体制づくりが課題となります。
見込み生産のメリットは納期を短くできる点、製造コストを下げやすい点、規模の経済を活かせる点です。
デメリットは需要予測が外れたときの在庫過剰や不足、廃棄のリスクが高まることです。価格競争にもつながりやすく、長期的にはマーケットの変化に弱いケースもあります。
実務では両者を組み合わせるハイブリッド戦略を取る企業が多いです。たとえば、部品の標準化を進めて見込み生産で在庫を抑えつつ、カスタム部品だけを受注生産で対応する方法です。これにより、納期の競争力と在庫コストのバランスを両立させることが可能です。
実務での使い分けのポイント
使い分けのポイントは「需要の安定性」「製品のライフサイクル」「顧客の納期要求」です。需要が安定しており、部品の共通化が進む場合は見込み生産が有利になることが多いです。逆に需要が不安定で、カスタム性の多い製品では受注生産が有利になります。
また、在庫コストとリードタイムのトレードオフを常に意識し、データに基づく意思決定を行います。
- 需要予測の精度を高めるためのデータ活用
- 部材の共通化と柔軟な生産ラインの構築
- サプライヤーとの共同計画と在庫の適正化
- 顧客への透明な納期管理と代替案の用意
実務では、予測が外れた場合の対応策として価格調整、納期の変更、代替品の提案などを事前に準備しておくことが重要です。これにより顧客満足を保ちつつ、企業の利益を守ることができます。
友達とカフェで話していると、受注生産という言葉が出てきました。僕は「注文が来てから作る」って理解していたけれど、それだけじゃないんだと知る。受注生産は仕様を確定させた後に製造が始まるため、設計段階の柔軟性と部材調達のタイミングが勝負になる。逆に見込み生産は需要を予測して前もってラインを動かすので、納品までの時間を短くできるが、予測が外れると在庫が残ってしまう。僕たちが普段買うカスタムスマホケースも、実はこの二つの考え方のうちどちらかを軸に作られているのかと思うと、身近さを感じた。つまり、製品の性質と市場の動き次第で、作るタイミングを決める戦略があるんだな、と感じた。
前の記事: « 品切れと欠品の違いを徹底解説!買い物の失敗を避ける3つのポイント





















