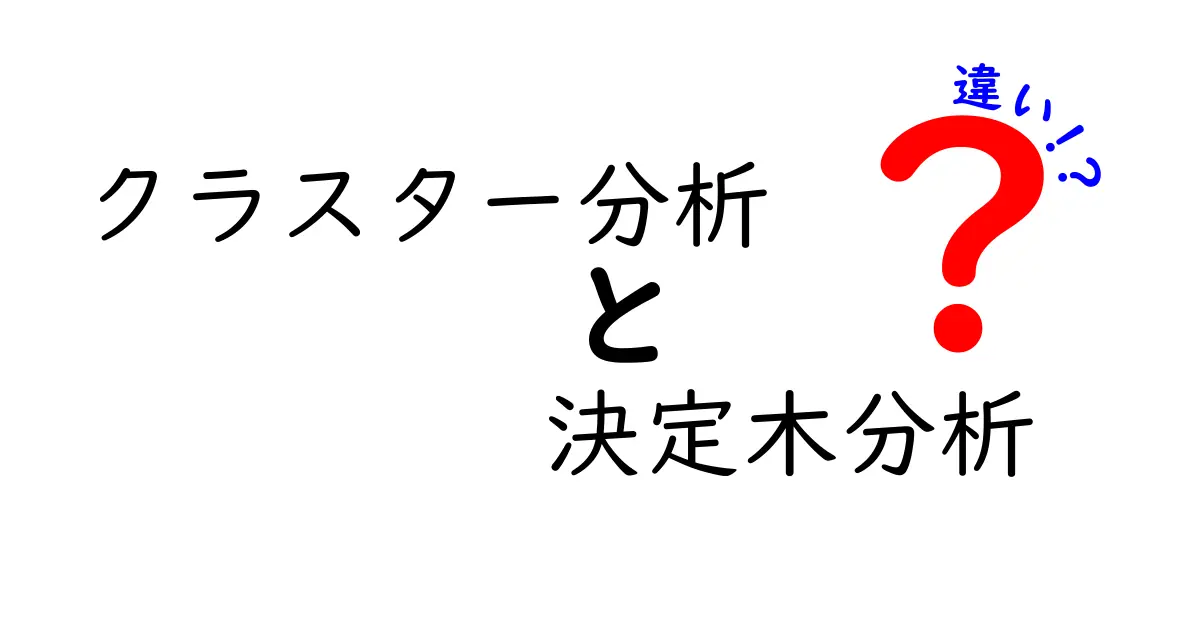

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クラスター分析と決定木分析の違いを完全ガイド|初心者でもわかる見分け方と使い分け
1. クラスター分析とは何か?基本の考え方
クラスター分析とはデータを「似ているもの同士が集まるようにグループ分け」する分析手法です。ここでのポイントは「教師データがいらない」という点です。つまり事前に正解を教えてくれる先生はおらず、データ自身の性質から自然にグルーピングを作ります。例えば学校の友だちの行動データを集めて、買い物の傾向や好きな遊び方が似ている人たちを同じグループに分けるとします。こうしてできたグループは、似ているけれど他のグループとは違う特徴を持つことが多く、将来の行動を予測する際の材料になります。
クラスター分析にはいくつかのやり方がありますが、よく使われるのが「k-means」という方法と「階層的クラスタリング」です。k-meansはまずK個の中心をデータの中から適当に決め、各データをもっとも近い中心に割り当てます。その後中心をデータの割り当てられたデータの平均位置に動かして、もう一度割り直します。これを中心が安定するまで繰り返します。階層的クラスタリングは木のようにどのグループ同士をくっつけていくかを決めながら、段階的に大きなグループを作っていきます。
この手法の良いところは「見えない構造を見つけられる」ことです。反面、データの規模や距離の測り方、中心の数Kの選び方などで結果が大きく変わるため、扱いにはコツが必要です。データの性質をまず理解し、標準化や外れ値の処理を行ったうえで分析を進めると、意味のあるグループが見えてきます。
実務では市場のセグメント作り、顧客の趣味の似たグループを探すとき、研究の予備分析としてデータの構造を掴むときなどに使われます。忘れてはいけないのは、クラスター分析は「正解を持たない問題を整理する作業」であるという点です。この点を理解すると、後の予測モデル作成や意思決定がスムーズになります。
2. 決定木分析とは何か?特徴と仕組み
決定木分析は「正解があるデータ」を使って予測を行う方法です。子どもの学力を予測するテストの級別や、天気予報の雨が降る/降らないといった二択の答えを推定するときに使われます。データの中の特徴を順番に分けていき、どの特徴が結果を最もよく説明するかを見つけます。たとえば「気温」「湿度」「風の強さ」といった特徴で、どの条件の組み合わせが雨になる確率を高くするのかを木の形で表します。
木の頂点は「現在の状態」を表し、分岐は「この特徴がどう違うか」で決まります。最も純度が高くなるように分割を繰り返し、最終的には葉と呼ばれる先端に予測結果が置かれます。決定木は直感的に理解しやすく、結果を図として見せるのが得意です。ただし、過学習に陥りやすいという弱点があります。データ量が少なかったり、特徴が多すぎたりすると、木が複雑になりすぎて新しいデータにうまく対応できなくなることがあります。
そのため実務では「剪定(プルーニング)」と呼ばれる手法で木を簡略化します。交差検証を使って適切な深さを決め、適度な複雑さに保つ工夫が必要です。さらに決定木はデータの前処理がそれほど厳密でなくても動くことが多い一方で、連続値の扱い方や欠損値の扱い方をどう設計するかで結果が変わりやすい点にも注意が必要です。
決定木には「回帰木」もあり、数値を予測する用途にも使われます。分類木はクラスを予測しますが、回帰木は具体的な数値を出します。これらは組み合わせて使われることも多く、データの性質に合わせて使い分けることが大切です。決定木は解釈性が高い一方で、データ量と質に敏感だという点を覚えておくと良いでしょう。
3. 違いをわかりやすく表で確認する
ここでは簡単な比較表を用意して、クラスター分析と決定木分析の違いを一目で確認します。
表を読むときは、何を目的に分析するか、データがラベル付きかどうか、出力が何を示すかを中心に見てください。以下の表は最も基本的なポイントを並べたものです。
この表を見れば、目的とデータの性質で使い分けるべき手法がはっきりします。クラスター分析はデータの構造を知るのに、決定木分析は予測する力を手に入れるのに適しています。
友だちと放課後にクラスター分析の話をしていたときのことを思い出す。彼は「クラスター分析は、データを似ている子たちで固める雰囲気づくりみたいなものだよ」と言い、僕は「なるほど、グループ分けを先にしておけば後で何をすべきか見えやすいね」と返した。実際、同じような購買データを集めてクラスタを作れば、どのグループがどんな商品に興味がありそうかが分かる。だからまず“似ている”の意味をデータで定義する作業が肝心だと感じた。彼は続けて、距離の測り方やKの選び方といった判断基準を丁寧に説明してくれた。私は「正解がない問題を整理する作業」としてのクラスター分析の役割に納得し、何をどう解釈するかが分析結果の価値を決めることを再認識した。





















