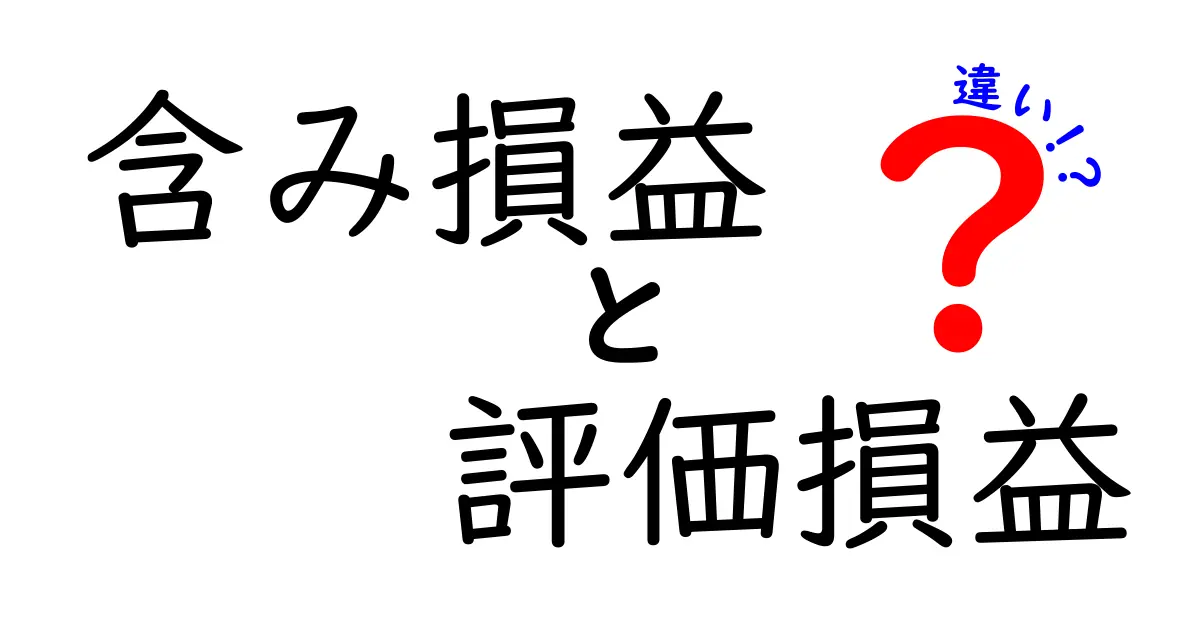

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
含み損益と評価損益の基本を押さえよう
"含み損益"は、現在の市場価格と取得原価の差を指す用語です。つまり、まだ売っていない取引の結果としての損益であり、現金が動くかどうかは売却時点で決まります。たとえば、1000円で買った株が現在1200円ならば含み益は200円、逆に800円に下落していれば含み損は-200円です。この差額は日々の市場の動きで刻々と変わります。保有している間はこの値は「仮の結果」として見え、売却が確定するまでは実現していません。含み損益は投資判断の指標として役立つ一方、目先の値動きに過度に振り回されやすい側面もあります。この点を理解しておくと、今の評価が高くても「すぐに現金化できるわけではない」という現実が見えてきます。
次に評価損益について説明します。
評価損益は、保有投資の評価額の変動によって生まれる損益のことです。会計上は評価替えと呼ばれ、時価評価や公正価値評価を採用する場面で現れます。売却の有無に関係なく、資産の時価が変われば帳簿の数値も動きます。例えば株を保有していて時価が上昇すれば評価益が増え、時価が下落すれば評価損が生じます。税務上は、評価換えの損益がその場で課税されるわけではなく、実際に売却して現金化されると課税の扱いが変わるのが一般的です。つまり、含み損益と評価損益は「現金化のタイミング」と「会計上の表示」の2つの側面を別々に見る必要があります。
この違いを意識しておくと、投資判断をする際に「いまの評価が高い・低い」という表示と「いくら現金が手に入るか」という現実を分けて考えられます。
日常的な実務を考えると、含み損益は短期的な売買の判断材料として使われ、評価損益は財務諸表の見方や企業の評価を把握する手がかりになります。これらを分けて考える習慣をつけると、投資のリスク管理がしやすくなるでしょう。
まとめると、含み損益は「いまの市場価値と取得価額の差」、評価損益は「時価評価による会計上の差額」であり、実際の現金化の時期が異なる点が大きな違いです。
この考え方を基礎として、長期的な資産形成と短期的な資産運用のバランスを取っていくことが大切です。
違いを生活に例えると?
含み損益と評価損益を生活の場面に置き換えると、少し分かりやすくなります。たとえば、友達から借りたお金を「今ここで返す約束」と考えたとき、それは含み損益に近い感覚です。いまは現金は動かなくても、約束の内容は変わらず、後日返済して初めて現金の動きが確定します。一方で、将来の進学費用など「将来の約束されたお金の価値」を見直す作業は評価損益のイメージです。現在の支出計画や将来の資産価値が変われば、帳簿上の価値はすぐには動かなくても、評価としての額が変わります。こうした区別を意識すると、現金化のタイミングを急ぐべきか、今は待つべきかを判断しやすくなります。
さらに、実務の現場では「含み損益が大きいから売ろう」と考えるよりも、「今売ると税金の影響はどうなるのか」「長期の目標に対してどう動くべきか」を総合的に判断することが重要です。評価損益の変動は、財務状況の読み取りにもつながるので、学校の成績表のように数字だけでなく、背景にある取引の性質を理解することが大切です。
実務での注意点とよくある誤解
実務でのポイントは、含み損益と評価損益を別々に見る癖をつけることです。含み損益は現時点での市場価値と取得原価の差であり、日々変動します。大きな含み益が出ても必ず現金化できるとは限らないため、売却のタイミングを見極める判断力が必要です。反対に評価損益は、評価額の変化によって帳簿上の数字が動くものの、実際の現金の流れとは直結しないことが多いです。税務面では、評価換えの損益は売却時の確定申告で扱われることが多く、日々の評価額の変動だけで課税されるわけではありません。これを前提に、現金の化を念頭に置いた戦略と、会計上の表示を重視する戦略を使い分けることが大切です。
初心者のうちは、取引履歴と現在の市場価格を別々に記録する練習をするのが有効です。たとえばノートや表計算ソフトで「取得原価」「現在価値」「含み損益」「評価損益」を並べて比較するだけでも、現金の出入りと評価の動きを分けて考えられるようになります。
また、長期と短期の視点を切り替える訓練も重要です。短期的な値動きに惑わされず、長期の目標に合わせて「今は持ち続けるべきか」「一部を売って現金化するべきか」を判断する力を養いましょう。
さらに、投資の基本として「自分のリスク許容度と目的を明確にする」ことがあります。無理のない範囲で少額投資から始め、経験を積んでいくと、含み損益と評価損益の区別が自然に身についてきます。投資は情報と時間を味方にするゲームです。焦らず、学ぶ姿勢を保ち続けることが成功への近道です。
ねえ、ちょっと投資の話を深掘りしてみようか。含み損益って、いまの市場の“いまの自分の資産”の価値と、最初につくった値段との差。売るまでは実際のお金は動かないけど、評価上は毎日変化していくよね。じゃあ評価損益はどうかというと、これは会計上の評価換えによって生まれる“資産の評価額の変動”のこと。現金の動きとは別に、帳簿の数字が動くんだ。こうやって考えると、同じ“損してる/得してる”でも、現金として動く時期と会計上の表れ方が違うことがよくわかる。で、現実にはどっちを見ればいいの?というと、計画によるけど、現金化のタイミングを見極める含み損益と、資産評価の変化を把握する評価損益の両方を同時に意識するのが一番賢い選択になることが多いんだ。私たち中学生でも、日々のニュースの株価の数字と、学校の成績表のような評価の違いを結びつけて考えると、投資の世界がぐっと身近に感じられるよ。
前の記事: « アンレとコンペの違いを徹底解説|初心者にも分かる使い分け方と実例





















