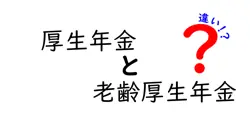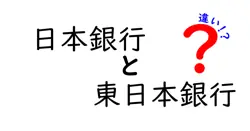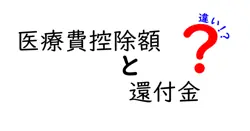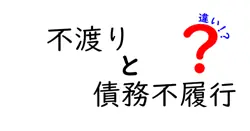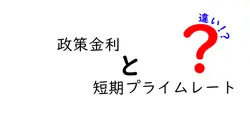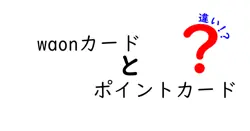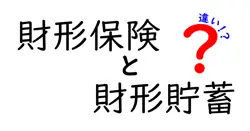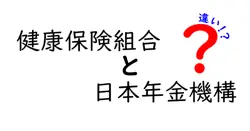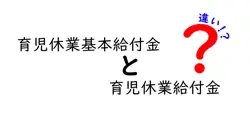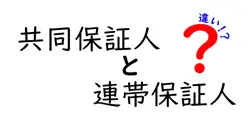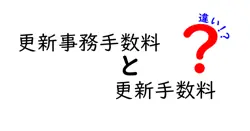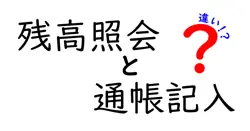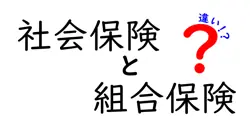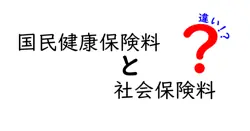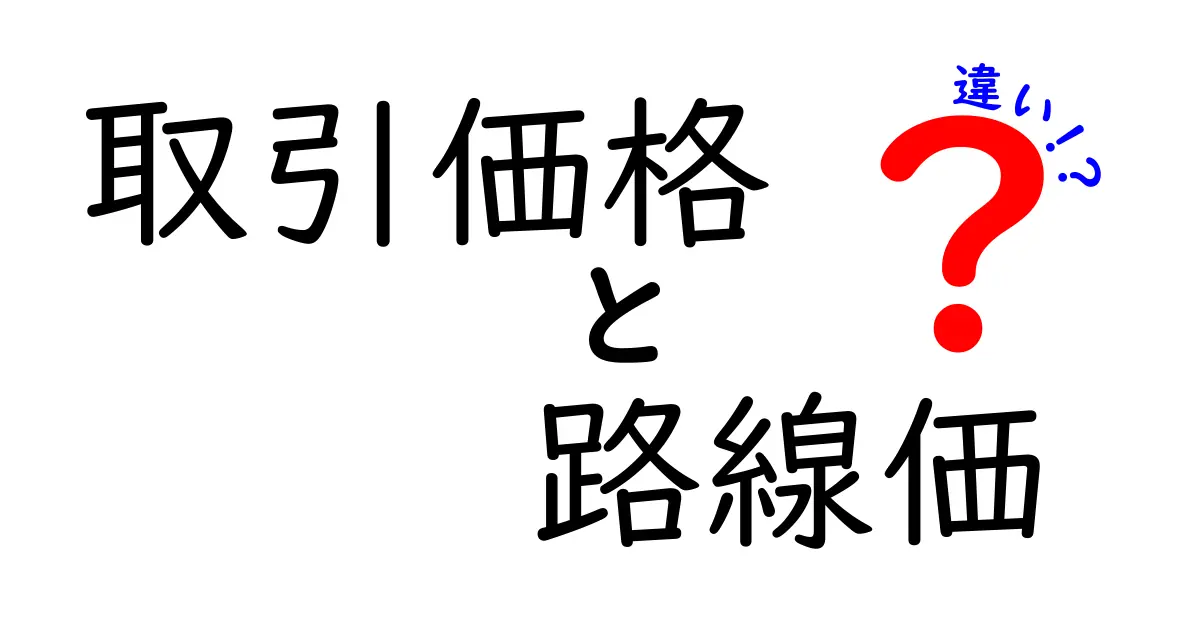
取引価格と路線価の違いって何?
不動産を購入するときや売るときに『取引価格』と『路線価』という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
でも、この二つの言葉はどう違うのでしょうか。
中学生でもわかるように、やさしく解説しますね。
取引価格とは、その不動産が実際に売買されたときの価格のことです。
つまり、実際に売り手と買い手が合意して決まった値段ですね。一方で、路線価は、国が毎年発表する土地の評価価格のことで、主に税金を計算するときに使われています。
このように、取引価格は実際の市場の価格、路線価は税金計算の基準の価格として使われているのです。
この違いを知ることは、不動産の価格を正しく理解し、損をしないためにとても重要です。
取引価格の特徴と使われ方
まずは取引価格について詳しく見ていきましょう。
取引価格は不動産の売買が実際に成立した価格であり、需要と供給のバランス、場所、建物の状態など様々な要素が反映されています。
そのため、同じ地域の土地でも、取引価格は大きく違うことがあります。
また、不動産取引の際の交渉や市場の動きによって変動します。
取引価格は、不動産を売買した時に実際に支払われた金額なので、市場価値を知るのに役立ちます。
ただし、取引例が少ない地域では参考価格として使いにくい場合もあります。
路線価とは何か?その目的と計算方法
次に路線価について説明します。
路線価は国税庁が毎年発表し、主に相続税や贈与税の計算で使われる土地評価の価格です。
路線価は、主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額を表しています。
土地の形状や奥行きによって補正がされ、土地全体の評価額が算出されます。
取引価格と違い、あくまで公式に税金を計算するときの基準として使われている価格です。
また、路線価は公的な価格なので、地域や時期によるバラつきを抑えて客観的に評価されます。
しかし、必ずしも実際の売買価格と一致するわけではありません。
取引価格と路線価の違いを比較しよう!
ここまでの内容を表にまとめて、取引価格と路線価の違いを比較してみましょう。
| 項目 | 取引価格 | 路線価 |
|---|---|---|
| 価格の決まり方 | 実際の売買で決まる (市場の需給による) | 国が毎年調査・公表 (税金計算の基準) |
| 用途 | 売買の参考価格、取引価格 | 相続税・贈与税などの土地評価 |
| 変動 | 市場の状況により変化しやすい | 毎年見直されるが比較的安定 |
| 反映される要素 | 周辺環境・交渉・土地状況など | 道路の価値や形状による補正あり |
| 入手先 | 不動産取引の実例や公開情報 | 国税庁の路線価図 |
まとめ:両者の違いを知って上手に不動産を扱おう
不動産の価格を理解するには、取引価格と路線価の違いを知ることが大切です。
取引価格は市場の実際の売買価格であり、路線価は税金計算のための公的な評価価格です。
両者は目的や利用場面が異なるため、混同しないように注意しましょう。
これらをふまえて不動産を売買すれば、適正な取引ができ、税金の計算もスムーズになります。
不動産に関心がある方は、ぜひこの違いをしっかり覚えておきましょうね。
路線価って、一見硬い税金の話に思えますが、実はすごく合理的なんです。道路ごとに値段をつけて、その道に面した土地の価値を計算するという考え方は、たくさんの土地を評価するときにすごく便利で効率的。路線価で評価された価格は、実際の取引価格よりも控えめで安定しているので、相続税の計算にも安心感があるんですよ。
前の記事: « 固定資産評価額と路線価の違いとは?初心者にもわかるポイント解説!