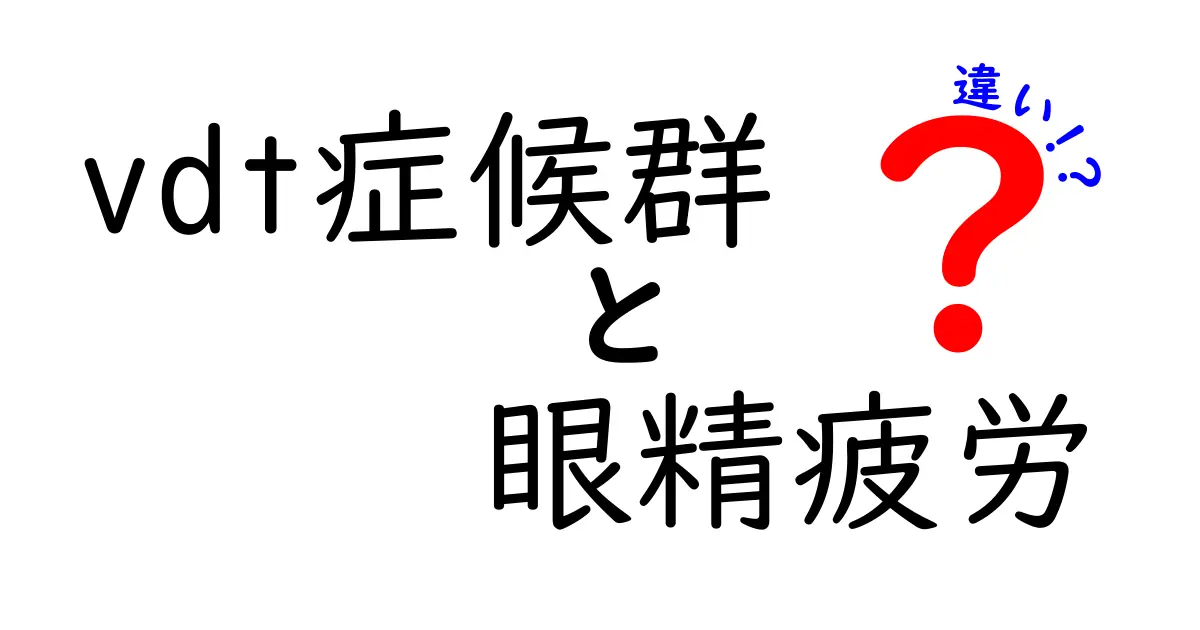

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
VDT症候群と眼精疲労の違いについて知ろう
みなさんは「VDT症候群」と「眼精疲労」という言葉を聞いたことがありますか?
どちらも目の疲れに関わる言葉ですが、実は少し意味が違います。VDT症候群はパソコンやスマホなどの画面を長時間見ることによって起こる体の不調の総称で、目の疲れだけでなく肩こりや頭痛も含まれます。一方、眼精疲労は目そのものの疲れや痛み、かすみ目などの症状のことです。
この記事では、VDT症候群と眼精疲労の違いをわかりやすく説明し、その原因や症状、対策までしっかり紹介します。
VDT症候群とは?原因と主な症状
VDTとは「Visual Display Terminal」の略で、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの画面のことを指します。
VDT症候群は、これらの画面を長時間見続けることで起きる様々な身体の不調のことを言います。
主な原因は画面を見る姿勢の悪さや目の使いすぎ、同じ姿勢を続けることにあります。
主な症状は以下の通りです。
- 目の疲れや乾き
- 頭痛
- 肩こりや首こり
- 手や腕のしびれ
- 腰痛
- 集中力の低下やイライラ
このように目だけでなく全身の不調が現れるのがVDT症候群の特徴です。
眼精疲労とは?原因と主な症状
眼精疲労は目そのものが疲れて起こる不調のことで、特に目を酷使した後に感じやすいです。
VDT症候群の中の症状の一つとも言えますが、パソコン以外にも読書や細かい作業でも起こります。
主な原因は目を酷使しすぎることや、目の乾き、視力の低下、目の病気などが挙げられます。
眼精疲労の主な症状は次の通りです。
- 目の疲れや痛み
- 目のかすみや充血
- まぶしさを感じる
- 涙が出る、乾く
- 重い感じや圧迫感
- 視力の一時的な低下
これらの症状は休息や目薬で改善することが多いですが、長引くと生活に支障をきたすこともあります。
VDT症候群と眼精疲労の違いを表で比較
具体的な対策と予防法
VDT症候群と眼精疲労は重なる部分も多いですが、どちらも日常生活での対策が大切です。
まずは以下のポイントを意識しましょう。
- 適度な休憩をとること(例えば50分作業したら10分休む)
- 目のストレッチや瞬きを意識的に増やすこと
- 姿勢を良くして、画面は目線より少し下に設置すること
- 適切な照明で目の負担を減らすこと
- ブルーライトカット眼鏡やフィルターの利用
- 目が乾いたら目薬を使うこと
さらにVDT症候群の場合は肩や首のストレッチ、適度な運動も重要です。
目に異常を感じたら眼科を受診し、早めに対応しましょう。
まとめ
VDT症候群と眼精疲労は似ていますが、VDT症候群は画面作業による全身の不調の総称、眼精疲労は目自体の疲れに特化した症状です。
どちらも適切な休憩や目のケア、姿勢改善が効果的。パソコンやスマホを使う機会が増えている現代社会において、これらの違いを理解し予防することはとても大切です。
VDT症候群という言葉は最近よく耳にしますが、実は略語のVDTは"Visual Display Terminal"のことを指しています。つまりテレビやスマホ、パソコンの画面そのもののことなんですね。特に若い人に多いのが長時間のスマホやゲーム画面の使用による目や体の疲れです。画面をじっと見続けると目が乾きやすくなり、瞬きの回数も減るので目の疲れだけでなく肩こりや首の痛みまで感じることがあります。ちょっとした休憩や画面から目を離すだけでも違うので、忙しい時ほど意識して目を休めることが大切ですよ。
前の記事: « 眼疲労と眼精疲労の違いとは?知って得する目の疲れの基礎知識
次の記事: 虹彩と角膜の違いとは?目のしくみをわかりやすく解説! »





















