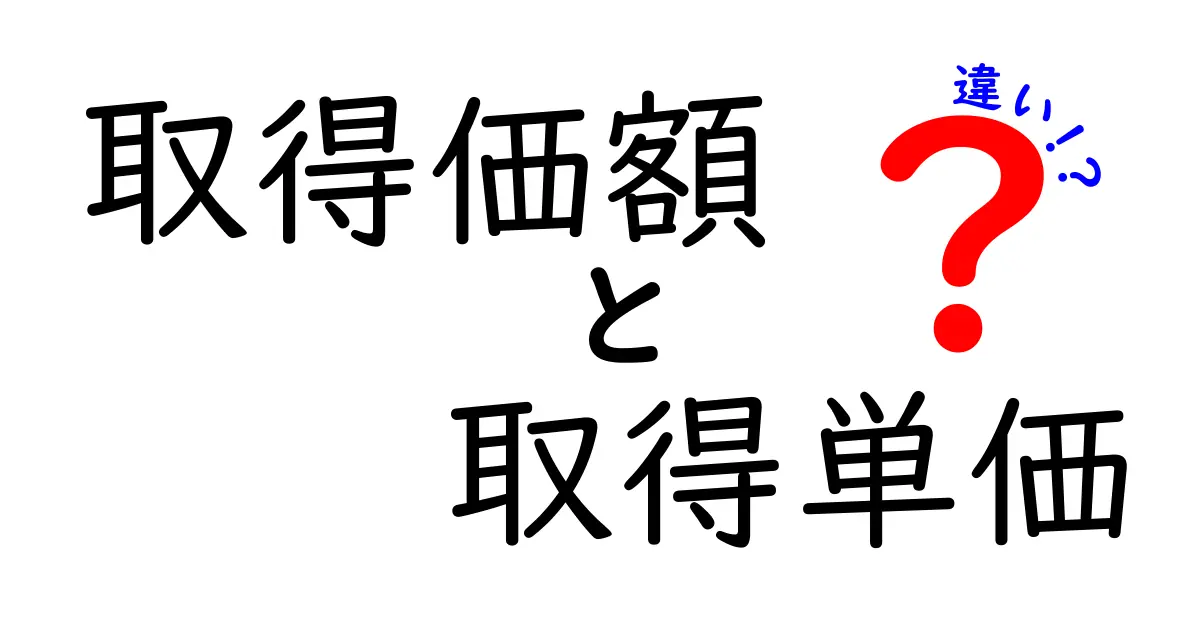

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
取得価額と取得単価の基本的な意味とは?
会計や投資の話でよく聞く「取得価額」と「取得単価」。どちらも資産や商品の購入にかかったお金のことを指しますが、使い方や意味には違いがあります。初心者の方は混同しやすい言葉なので、ここでしっかり覚えておきましょう。
まず「取得価額」とは、資産を取得するときに支払った総額のことを言います。つまり、買うためにかかった全費用の合計です。
一方「取得単価」は、取得した資産1単位あたりの平均費用を指します。例えば株を100株買った場合、その株1株あたりの値段が取得単価です。
このように、取得価額は全体の費用、取得単価は単位あたりの費用を示す言葉です。
取得価額と取得単価の違いを詳しく解説
もう少し具体的に違いを見てみましょう。
「取得価額」はたとえば不動産を買ったとき、土地と建物の価格に加えて仲介手数料や登記費用、税金などの関連費用も含みます。そのため、購入にかかるすべてのコストの合計金額となります。
一方、「取得単価」は「取得価額」を取得した資産の数量で割ったものです。株式や商品、製品など大量に取得する場合に使います。
例として、1000個の商品を30万円で仕入れた場合、取得価額は30万円ですが、取得単価は1個あたり300円です。
この違いを知っておくと、会計処理や在庫管理、投資判断のときに正確なコスト管理ができます。
取得価額と取得単価の使い分けポイント
では「取得価額」と「取得単価」はどのように使い分ければいいのでしょう。
取得価額は全体の買い物や投資の費用を把握したいときに使います。例えば会社が設備を購入するとき、設備全体にかかった費用(購入費用+諸経費)を知るのに役立ちます。
取得単価は、商品の仕入れや売却のコスト計算に使われます。大量の商品や株式の平均的な購入価格を知るときに便利です。
たとえば株式投資で複数回に分けて購入した場合、それぞれの購入価格が違っていても取得単価を計算すると平均的な取得コストがわかるため、損益計算がしやすくなります。
以下の表でまとめてみました。
| 項目 | 意味 | 使いどころ | 例 |
|---|---|---|---|
| 取得価額 | 資産や商品の総購入費用 | 全体の購入や投資費用の把握 | 設備購入の総費用(購入費+手数料+税金) |
| 取得単価 | 1単位あたりの平均取得費用 | 商品の仕入れや株式の平均コスト算出 | 株1株の平均購入価格 |
まとめ:取得価額と取得単価の違いを理解して賢く使おう
今回は、「取得価額」と「取得単価」の違いについてわかりやすく説明しました。
取得価額は購入にかかった全費用の合計で、取得単価はその費用を単位数で割った平均費用です。
この違いを押さえると、会計処理や投資のコスト計算がとてもスムーズに行えます。
例えば株を複数回に分けて購入したり、商品の仕入れ単価を把握したりするときは「取得単価」を使う。
一方、大きな設備や土地などの買い物では「取得価額」を使って全体の費用を確認する。
このようにケースに応じて正しく使い分けましょう。
どちらもビジネスや投資では基本的かつ重要な言葉なので、ぜひ覚えておいてください。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
「取得単価」と聞くと単に1個あたりの値段と思いがちですが、実はその計算方法には注意が必要です。例えば、同じ株を複数回に分けて買うと、購入ごとに値段が違うことがありますよね。そんな時は、単に最後に買った値段ではなく、すべての購入費用の合計を株数で割った平均値を取得単価として計算します。これにより、正確な投資の損益計算が可能になるんです。株式投資をやっている人にとっては、取得単価は勝つための秘訣とも言える重要な数字。少し深掘りすると、投資判断に役立つ面白い知識ですよね。ぜひ覚えておいてください。
次の記事: 製造原価と販売原価の違いとは?わかりやすく解説! »





















