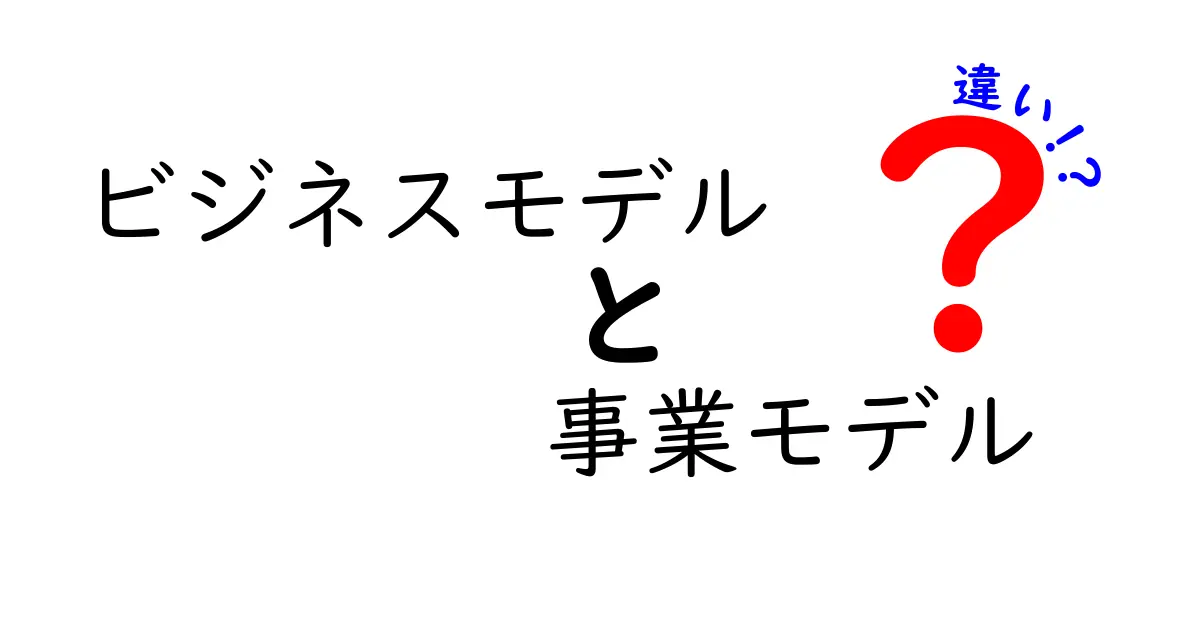

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:なぜ「ビジネスモデル」と「事業モデル」の違いを知るべきか
はじめに、ビジネスモデルと事業モデルは似ている言葉ですが、使われ方は場面によって少し違います。企業の戦略を考えるとき、両者を分けて理解することで「何を作り、誰に届け、どのようにお金を回すのか」という全体像が見えやすくなります。学校の授業で例えるなら、同じ材料を使っても「何を作るか」という設計と「その材料をどう運ぶか」という現場の動かし方は別の設計図になります。
この章では、まず概念の境界線をはっきりさせ、つぎに現実的な運用の課題を考えるコツを紹介します。
読者のみなさんがニュースや企業の話を読んだ時、「この企業はどんな価値を作り出しているのか」「実務はどう回っているのか」をすぐに質問できる力を身につけられるようにします。
ビジネスモデルの定義と役割
ビジネスモデルとは何かをまず押さえましょう。価値をどう作り出し、誰に提供し、そして どの価格で回すのかという三つの要素を組み合わせた「長期的な設計図」です。ここには市場のニーズ、競合との差別化、収益の源泉、コスト構造、顧客との関係性などが含まれます。実際にはスマホのアプリやサービスの背後にある考え方がこの設計図として存在し、広告モデル・課金モデル・サブスクリプションモデルなどの具体的な形に落とし込まれます。
ビジネスモデルは変化する市場に合わせて進化させることが大切であり、長期の視点で安定性と成長性の両立を狙う役割を担います。数字だけでなく顧客の体験、提供価値の持続性、社会への影響なども考慮する必要があります。
事業モデルの定義と役割
事業モデルは、実際の運用を回すための設計図です。製品やサービスを作って売るという基本の流れだけでなく、仕入れ・生産・物流・在庫管理・品質保証・カスタマーサポートといった現場の作業プロセスをどう組み合わせるかが中心になります。ここにはパートナー企業との協力関係、組織の役割分担、オペレーションの手順、データの活用方法、コストの最適化といった要素が含まれます。良い事業モデルは、顧客に価値を安定して届けるための実行力を高め、時には新しい製造・流通の仕組みを作るきっかけにもなります。
現場の動きがうまく回ってこそ、ビジネスモデルが描く価値提案が現実の収益につながります。
二つの違いを見分けるポイント
二つの違いを判断するときのコツを覚えておくと混乱を防げます。第一のポイントは「収益の作り方」と「運用の仕組み」を別々に考えること。第二は「戦略の階層」を意識すること。第三は環境の変化に対する適応性です。
つまりビジネスモデルは市場の課題をどう解決し、どんな価値を誰にどう提供するかの大きな設計図であり、事業モデルはその設計図を現場で現実的に動かすための細かな手順・役割・コスト・リスク管理の組み合わせです。
この二つを分けて考え、定期的に見直すことが、長く続くビジネスの基本になります。
実例でわかる違い
実例を通して違いを感じてみましょう。コーヒー(関連記事:アマゾンの【コーヒー】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)ショップを例にとると、ビジネスモデルは「どうやってお客さんに価値を届けるか」の設計です。価格設定、顧客層、差別化、収益源の設計などが含まれます。一方の事業モデルは「現場をどう運用するか」の設計です。店舗の立地・スタッフの配置・仕入れ先の選定・在庫回転・品質管理・顧客対応の流れといった、実際の運用を回すための仕組みです。両者が噛み合わなければ、売上が伸びてもコストが増え、利益が出にくくなることもあります。
別の例として、同じ商品でもオンラインと実店舗での展開を組み合わせる場合、ビジネスモデルはオンラインの価値の伝え方を設計し、事業モデルは配送・返品・サポートの現場プロセスを設計します。これらが統合されて初めて、顧客にとって使いやすく、企業にとって安定した収益を作る仕組みになります。
比較表
友だちとカフェで話しているときの雑談風に、ビジネスモデルの深掘りをしてみるとこんな感じになる。第1に、なぜそのアプリが お金を生むのかを考えるとき、すぐに広告や課金という解決策が出てくるが、本質は“価値の伝え方”にある。無料で使える機能と有料で使える機能の線引きがビジネスモデルの設計だ。第2に、同じ機能でも提供の仕方を変えると収益構造が変わる。サブスクリプションや一括購入、広告モデルなど、別の道を選べば成長の仕方も変わる。最後に、競合と差別化するには、顧客が本当に必要とする価値を見つけ、それを“持続可能な利益”に変える仕組みを作ることが大事だ。





















