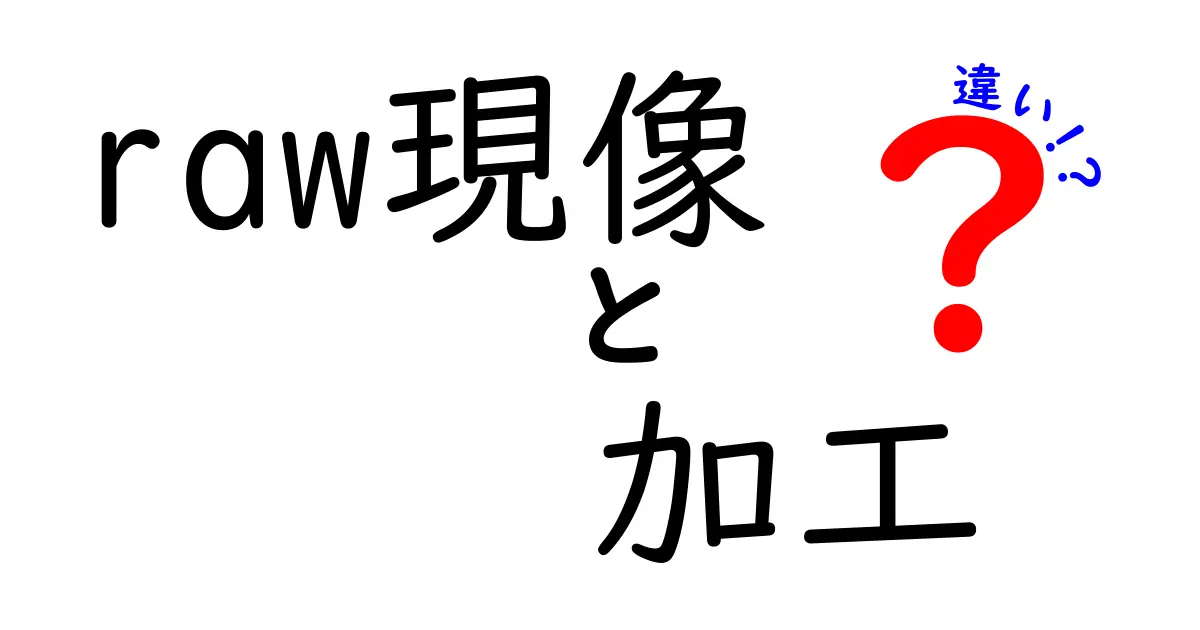

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:RAW現像と加工の基本を理解する
ここから先では RAW現像と 加工の違いを分かりやすく説明します。写真をきれいに仕上げるためにはどちらの作業が必要なのかを理解することが大切です。RAW現像はカメラから出力される生データを活かして自分の好みの色味や明るさを作る作業です。撮影時の露出やホワイトバランス、シャドウとハイライトの階調、ノイズの調整などを段階的に整えていきます。RAWデータはまだ最終的な絵にはなっていません。色の幅や階調の選択肢が多いのが特徴で、これを活かせば後での修正が容易になります。加工はこの生データを元に創造的な作業を行い、作品としての一貫性を出す段階です。RAW現像と加工を分けて考えると、写真づくりの全体像が見えやすくなります。
例えばスポーツの写真で動きの瞬間を活かすにはRAW現像で露出を整え、加工で背景を整えるといった組み合わせが効くことがあります。
大事なのは「何を残し何を強調するか」を決めることです。
RAW現像とは何か?
RAW現像とは、カメラが記録した生データを現像ソフトで読み込み、露出・色温度・色味・階調・シャープネスなどを調整して自分の意図を形作る作業のことです。RAWデータはJPEGのようにプリセットされた圧縮情報ではなく、センサーが拾った光の情報をほぼ素の状態で保存しています。そのため、後から大きく持ち上げたいときにも情報量が多く残っており、特にハイライトの飛びや影の黙々とした情報を修復しやすいのが特徴です。非破壊編集が基本スタイルで、作業は別ファイルとして保存され、元データはそのまま残ることが一般的です。現像ソフトは露出の階調を滑らかに変え、色温度や色味を変えることで「現像前の印象」から「最終的な印象」へと変化させます。ここで大事なのは、過度な編集は写真の自然さを失いがちで、特に年齢を超えた撮影現場では現場の雰囲気を壊さない程度の調整を心がけることです。
加工とは何か?
加工は RAW現像で作った基礎をもとに、さらに創造的な変化を施す作業です。色を強く変えたり、別の素材を合成したり、テキストを入れたり、エフェクトを付けたりします。加工には大別すると二つの側面があります。一つは写真だけの加工、もう一つは画像を別の素材と組み合わせる合成です。前者は非破壊編集の範囲で行われることが多く、レイヤー機能やマスクを使って修正を段階的に重ねていきます。後者は合成によって現実には存在しない風景や物語を描くことも可能です。加工は作品の個性やストーリー性を高める力を持っていますが、過度な加工はリアリティを損なうリスクもあります。写真の表現力を高めるためには、加工の目的を明確にし、何を残し何を強調するかを意識して進めることが大切です。
具体的な作業フローと違いの実例
撮影時の設定を活かしてRAW現像で基礎を整え、加工で完成度を高めるという流れが基本です。まず露出と白バランスを適切に整え、色味の傾きを修正します。次に階調の調整で暗部とハイライトの情報量を均衡させ、ノイズを抑えます。ここまでがRAW現像の作業で、非破壊編集を前提に段階的に保存していきます。続いて加工では色の雰囲気を変えたり背景を整理したり、場合によっては合成を用いて新しい世界を作り出します。大切なのは作品全体の統一感を保つことと、現場の雰囲気を壊さないことです。最後に出力形式を選び、印刷やウェブ配信に適した色空間と解像度に調整します。
この順番を守ると、初心者でも失敗しにくく、写真の表現力を計画的に高めることができます。
比較表:RAW現像 vs 加工
以下の表は代表的な違いを簡潔に示すものです。
表を読むと、RAW現像はデータの基礎づくり、加工は仕上げの創造的な作業という役割が見えてきます。
RAW現像の話を友だちとして雑談風に。夜景を撮るとき、露出を少し落として重厚感を狙いがちですが、RAW現像なら暗部の情報を救済して全体のバランスを取り戻すことができます。ある日、海辺の夜景を撮影して空が白 く飛びそうになった場面で、ハイライトを崩さず影の情報を引き出す作業を試みました。現像で微かな青味を保ちつつ暖色を混ぜてフィルムライクな雰囲気に寄せると、冷たい夜の空気と海の色が自然に混ざり合い、物語性が生まれました。こうした微調整の積み重ねが写真を言葉にする瞬間を増やすのです。





















