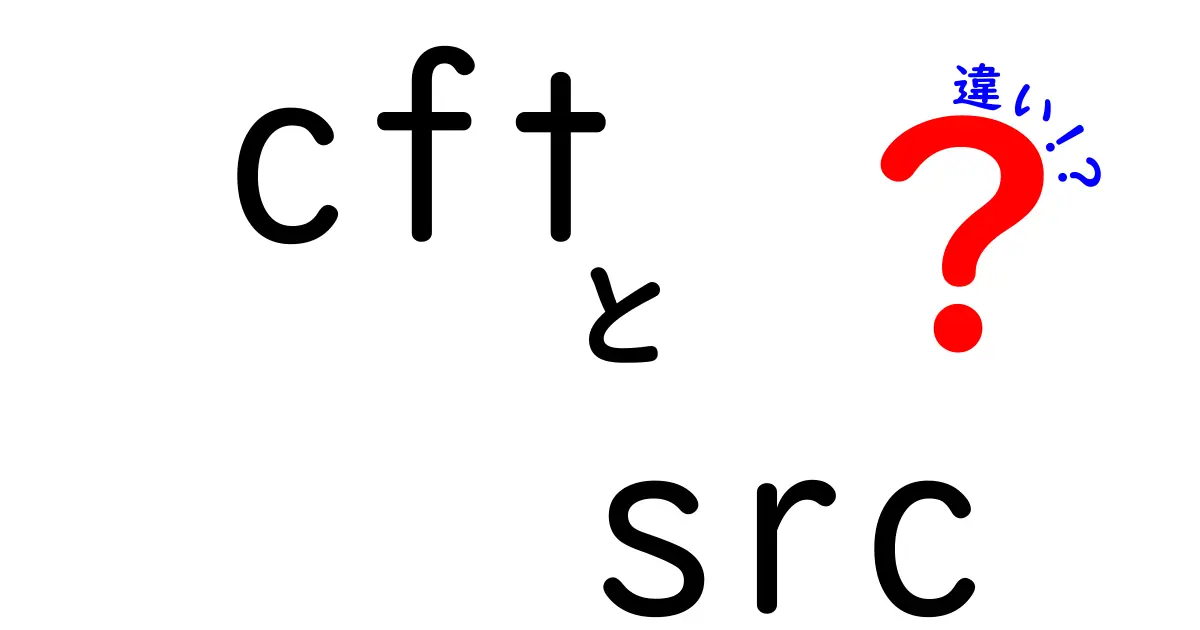

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
cft src 違いの全体像とポイント
このキーワードの中心は cft と src の組み合わせにあります。
どちらも略語として使われることが多いのですが、文脈次第で指すものが変わる点が最大のポイントです。
まずは両者の基本イメージを押さえましょう。
cft は特定のツールや雛形の名前・設計の一部として使われることが多く、何かを作る型や雛形の役割を担います。
一方、src は source の略であり、コードやデータの出発点となる場所を指すことが多いです。
つまり cft は“作り始めの設計図やテンプレート” を表すことが多く、src は“実際に作業を始める原材料やコードの集合” を表すことが多いのです。
この違いを理解するだけで、ファイル名やディレクトリ構成を読んだときの意味を素早く推測できるようになります。
以降のセクションで、具体的な場面と使い分けのコツを詳しく見ていきましょう。
1章 cft とは何か(代表的な意味と使い方)
cft は実務の現場で複数の意味を持つ略語です。最も分かりやすい例としては CloudFormation テンプレートの略称が挙げられます。クラウド環境をコードで定義する際に cft と呼ぶことで、ファイルの役割をすぐに伝えられます。
この場合のテンプレートファイルは通常 JSON か YAML で記述され、リソースの配置・依存関係・設定値を宣言的に記述します。
ただし別のプロジェクトでは cft がツール名やモジュール名の略として使われることもあり、必ずしも CloudFormation に限定されません。
重要なのは文脈です。ファイル名やフォルダ名に cft が含まれていれば、それは“何かの雛形・設計のまとまり”を表している可能性が高いという点です。
このセクションのポイントは、読んでいる場所がクラウド系の設定ファイルかどうかを最初に判断することです。そうすれば cft の意味が自然と絞り込めます。
また cft にはテンプレート以外の意味もあるため、周囲の言葉遣いを手掛かりに正しい解釈を選ぶ練習が必要です。
このように cft は“設計図の集合体”という発想を持つと理解しやすくなります。
2章 src とは何か(基礎と現場での意味合い)
次に src です。
src は英語の source の略で、開発現場では最も頻繁に見かける用語のひとつです。コードの元となるファイル群が入っているディレクトリを指すことが多く、プログラムの実行に直接関与する要素を格納する場所として理解されます。
たとえばソフトウェアのリポジトリを開くと、ルート直下に src ディレクトリがあり、その中にはプログラム本体のソースコードが並んでいます。
また設定ファイルや補助的なデータが src に混ざることはありますが、本質的には“作業の起点になる材料”を指します。
この意味を覚えるコツは、ファイルを開いたときにすぐ目的が見えるかどうかです。src という名が示すのは“ここから物語が始まる”場所という直感的なヒントです。
現場では src の中身を読んで、コードがどの機能を果たすのかを辿る作業が日常的に必要になります。
この文化をつまずかずに受け継ぐには、ディレクトリ構造の意味をチームで共有することが大切です。
3章 cft と src の違いをどう使い分けるか(実践的なコツ)
最後に実践的な使い分けのコツをまとめます。
まず基本の考え方として、cft は“何かを作るための設計図や雛形”として扱い、src は“その設計図を実際に機能させるコードや資材の集まり”として扱います。
具体的には新しいプロジェクトを始めるときにフォルダ構成を決める場合、上位フォルダ名に cft を用意してテンプレートファイルを置くことがあります。一方で実際の開発を進める際には src ディレクトリを中心にコードを書き、テストデータや補助スクリプトは別の適切な場所へ配置するのが自然です。
また混在するケースでは、チーム内で意味を共有することが重要です。例えば同じリポジトリ内の複数のサブプロジェクトがあり cft が設計の集合を、src が実装の集合を指すように命名規約を統一します。
このような統一は初学者にも優しく、リファクタリングの際にも混乱を抑えられます。
最後に覚えておくべきポイントは、cft と src の違いは“役割の違い”だという点です。
役割が異なれば、ファイルの扱い方や更新の頻度も自然と変わります。
この感覚を身につけるだけで、他人と協働する場面でも意思疎通がスムーズになります。
- 要点1 目的の違いを意識してファイル構成を設計する
- 要点2 呼び方の混乱を避けるためチーム内の命名規約を決める
- 要点3 新規プロジェクトではまず役割分担を明確にする
koneta: 友だちとカフェで雑談するように話すと cft と src の違いはすぐ伝わります。彼は cft を設計図と呼び 私は src を出発点と呼ぶ。すると話は自然に広がり どの場面でどちらをどう使うかという実務のコツへと進みました。たとえば新しいアプリを作るとき まずは cft で雛形を準備し その雛形を基に src に実際のコードを置く そんな流れを想像すると 迷いが減ります。





















