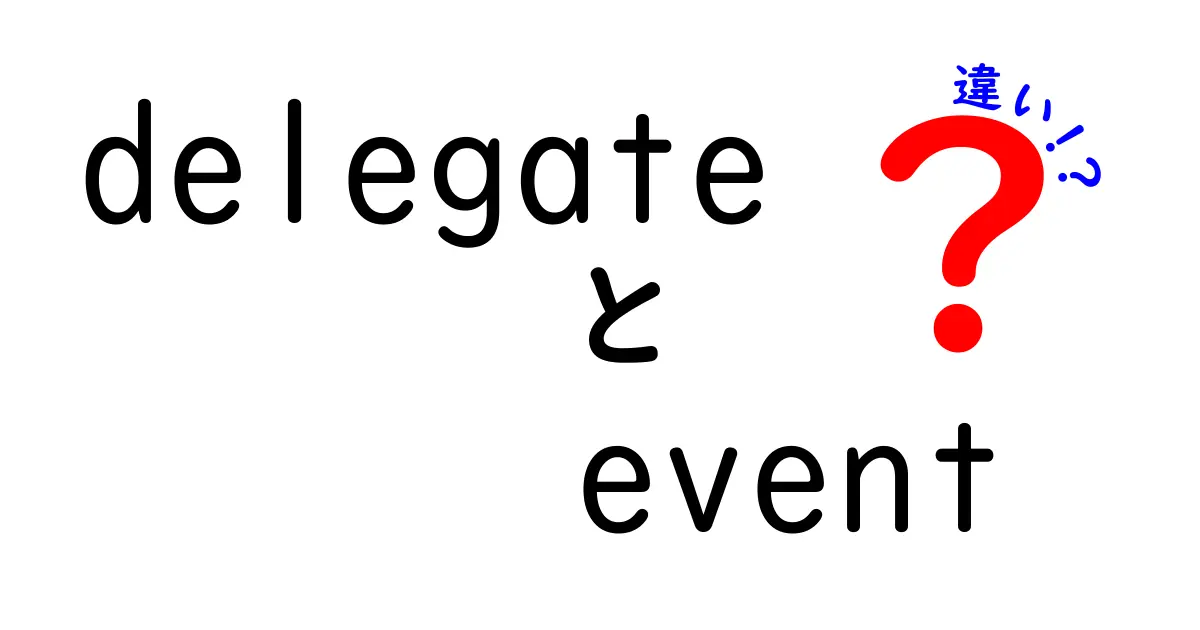

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
delegateとeventの基本を押さえる:両者の役割と違いを一問一答
プログラムの世界でよく使う用語の中に、delegateとeventという言葉があります。
この2つは仲良く登場しますが、それぞれ役割がちがうのが特徴です。
まずdelegateとは、”関数の参照を格納できる型”のことです。つまり、誰かが用意した処理を別の場所で呼び出せるように、参照をひとまとめにしておく箱のようなものです。実際には、デリゲート型に対して「メソッドを登録」し、必要なときにそのメソッドを「呼び出す」ことができます。これは、プログラム内で「このときこの処理を動かそう」という結び付きの設計を作るときにとても便利です。
しかしdelegateは外部から自由に実行を許してしまうと問題が起きる可能性もあります。そこで、イベントという仕組みが生まれました。
次にeventとは何かを整理します。eventは、デリゲートを公開するための専用の機能です。イベントを宣言すると、そのイベントの購読(参加)と解除を外部のコードが行えるようになりますが、「そのイベントを勝手に呼び出す」ことはできません。呼び出し権限をイベントの宣言元に限定することで、安全性と予測可能性が高まります。つまり、イベントは「誰が何をするか」を外部に知らせつつ、実際の呼び出しを管理する立場にあります。
この構造のおかげで、複数の場所から同じ処理を登録しておいても、イベントの発生源だけがその処理をまとめて実行します。
以上の点を押さえると、delegateは処理そのものの参照を扱う道具、eventは決まった場所でその処理を呼び出す仕組みと整理できます。
この違いを理解すると、デザインの方針が見えやすくなります。
例えば、テスト用のモックを渡したいときはdelegateの柔軟性が役立つ場面が多いです。
一方で、外部のコードに対して「呼び出し可能かどうか」を制御したいときにはeventを使うのが安全です。
結論として、delegateは処理を渡す道具、eventはその処理を呼び出す機構を公開する仕組みと覚えると混乱が減ります。
実務での使い分けと注意点:現場での実践ガイド
実務では、外部からの呼び出し権限と通知の範囲を分けて設計することが重要です。
日常のUIイベントやデータの変更通知にはイベントを使うと、意図せぬ呼び出しを抑えられます。
一方、テストや拡張性を重視する場面ではデリゲートを活用して、振る舞いを柔軟に差し替えられるようにすると良いでしょう。
具体的には、次の三点を心がけてください。
1. 外部からの直接呼び出しを避けたい場合はイベントを選ぶ。
2. 依存関係を減らすため、イベントの購読・解除は外部から自然に行えるようにする。
3. 単純な関数の呼び出しにはデリゲートを使い、複数のクライアントへ通知する際はイベントで公開する。
この考え方を身につけると、コードの可読性と保守性が大きく上がります。最初は難しく感じても、デザインパターンとしての位置づけを押さえることで、練習問題の解決にも役立つでしょう。
今日はdelegateとeventの話を深掘りしてみた。デリゲートは“関数の参照を集めて後で呼び出す道具”という感覚で、イベントはその道具を“公開する窓口”として、外部の人が参加したり離れたりできる仕組みだと理解すると分かりやすい。僕のゲーム作りのときも、協力プレイの合図をデリゲートで渡して、プレイヤー全員にその合図を伝えるにはイベントを使う――こんな具合に使い分けると設計がスッキリする。実務では責任の分離と安全性が大事だから、イベントは公開範囲を制限する強力な手段として覚えておこう。





















