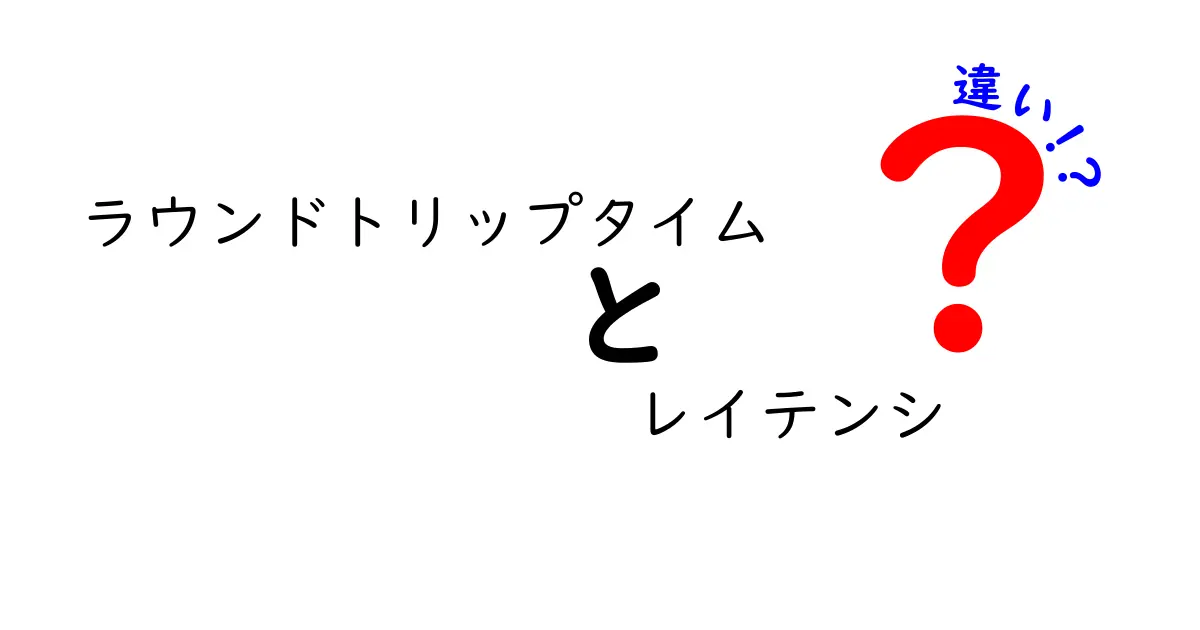

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ラウンドトリップタイムとレイテンシの違いをざっくり解説
ラウンドトリップタイム(RTT)とは、データを送ってから返ってくるまでの「往復の時間」を指します。通信の世界では、相手先の端末まで行って戻ってくるまでの時間全体を測る指標として使われます。
これに対してレイテンシ(遅延)とは、片道の時間、つまり一方の移動にかかる時間のことです。片道だけの遅れを測るので、同じ経路でも送信側と受信側の両方が関係します。これらは名称が似ていますが、意味するものと使い方が違うため、混同しないことが大切です。
ここからは、具体的な定義と違いを、身近な例とともに噛み砕いていきます。
まず最初に覚えておきたいのは、RTTとレイテンシは互いにつながっているけれど別の指標だという点です。RTTは往復の時間を測る総合的な指標で、レイテンシは片道の時間を測る指標です。路線が短く、機器の処理が速い場合は、RTTもレイテンシも短くなります。逆に、距離が長い路線や機器が混雑している場所では、どちらも長くなることが多いです。
この記事を読むときのポイントは、実際に測定する場面を想定して、「どちらの指標を重視するべきか」を明確にすることです。ゲームの勝敗を左右するのは主にRTTの安定性で、動画視聴の安定性を左右するのはレイテンシそのものの遅延です。こうした区別を知っておくと、原因を絞るときに役立ちます。
最後に、日常生活でのイメージを使って、両者の違いをしっかり覚えましょう。
・RTTは往復の時間であり、データが出発点から目的地へ行って戻ってくるまでにかかる全体の時間です。
・レイテンシは片道の時間であり、データが一方向に進むのにかかる時間を表します。
この二つをセットで考えると、通信の“速さ”の正体がよりクリアになります。
ラウンドトリップタイム(RTT)とは何か
RTTは往復の時間を指す指標です。実際には、送信側の端末がデータを出してから、ネットワークを経由して受信側が処理して、再び返ってくるまでの全過程を含みます。
測定の代表例としてはpingコマンドがあり、送信したパケットが返ってくるまでの時間をミリ秒単位で表示します。RTTは、伝搬遅延、回線の混雑、ルータの処理、端末側の応答時間など複数の要因が重なって決まります。
実務的には、RTTの平均値・最大値・分散を見て「どれくらい安定しているか」「どの程度の悪化が起きやすいか」を評価します。
距離が近いサーバーほどRTTは短くなりやすく、海を渡るような長距離の経路では長くなる傾向があります。
ただし、RTTは必ずしも「良い/悪い」を単純に示すだけではなく、経路途中の一時的な混雑や機器の再起動などで一時的に数十ミリ秒変動することがあります。
レイテンシ(遅延)とは何か
レイテンシは片道の遅延を示す指標です。データが発信点から受信点へ移動するのにかかる時間を測ります。主な要因は、伝搬遅延(距離と信号速度)、排除遅延(機器の処理や待ち時間)、キューイング遅延(混雑による待ち時間)、処理遅延です。
伝搬遅延は距離に比例して増え、海底ケーブルの長さや衛星回線の特性などで大きく変わります。排除遅延・キューイング遅延は路線の混雑状況次第で変動します。機器の処理能力が低い場合には処理遅延が増え、全体のレイテンシを押し上げます。
このように、レイテンシは「片道の遅延」を構成する要素を個別に考えることで、どこが問題なのかを特定しやすくなります。RTTが測るのは往復の総時間なので、同じRTTでも経路の片道遅延が極端に偏っているケースもありえます。
日常の通信で重要なのは、レイテンシそのものの遅延と、RTTの安定性の両方です。体感速度を左右するのは実はこの二つのバランスであり、適切な対策は距離だけでなく回線の品質管理にも及びます。
両者の違いを実生活に例えると
実生活でのイメージを使うと分かりやすくなります。たとえば郵便のやり取りを考えてみましょう。あなたが友だちへ手紙を出すとき、手紙が相手の家に届くまでの時間がレイテンシ、手紙を出してから返事が返ってくるまでの全体の時間がRTTです。送信→到着→返事という一連の流れを通じて、道の混雑や郵便局の処理速度が遅いとレイテンシが長くなります。返事が来るまでの時間を二人合計で「往復の遅れ」として見るのがRTT、片道だけの遅れを見ているのがレイテンシです。
このイメージをネットワークに置き換えると、あなたのパソコンからサーバーへデータを送るときの「片道の時間」がレイテンシ、サーバーからあなたへデータが戻ってくるまでの時間を含んだ全体がRTTになります。実際の通信でも、距離が近いほどレイテンシは小さく、RTTも安定しやすくなります。
また、両者を同時に意識することで、どの段階で遅延が発生しているのかをより正確に把握できるようになります。例として、ゲームをプレイしているときに「反応は速いのに視覚的な動きが遅れる」と感じる場合、レイテンシの片道側の遅延が原因かもしれません。一方で、サーバーが遠い、もしくは回線が混雑しているときには、RTTが大きくなって体感速度が落ちる場合があります。最後に、これらの指標は単体で判断せず、複数の測定値を組み合わせて総合的に判断するのが現実的な使い方です。
ある日、友だちとオンラインで協力ゲームをしていたとき、私たちは『どうして時々動きがカクつくのか』という話題になりました。私はまずレイテンシが“片道の遅延”であることを伝え、友だちが『じゃあ相手サーバーまでの距離が関係しているのかな?』と質問しました。そこで、私たちは自宅のWi‑Fiと学校の回線を比べ、距離だけでなく回線の混雑具合や機器の処理能力が影響していることに気づきました。レイテンシが高いと、ゲーム中の反応が遅く感じることが多く、RTTが大きいと画面の動きと実際の操作のズレが起きやすくなります。私たちはこの話を通じて、同じ“遅延”という言葉でも測り方で意味が変わるということを実感しました。今後、遅延を改善するには、距離の近いサーバーの利用、混雑する時間帯を避ける、ルータの設定を工夫するなどの対策があると学びました。こうした小さな気づきが、難しい専門用語を身近に感じさせてくれるのだと実感しました。





















