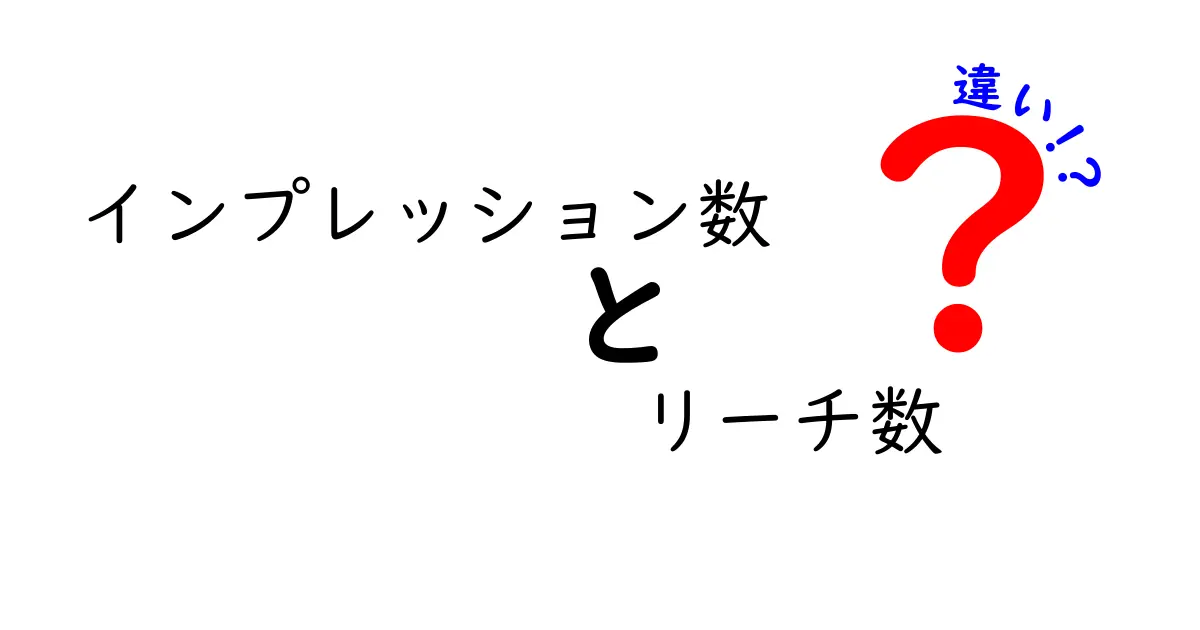

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インプレッション数とリーチ数の基本を知ろう
インプレッション数とリーチ数は、SNSや広告の結果を測るときに必ず登場する用語です。両者は似ているようで意味が大きく違います。まず、インプレッション数とは投稿が表示された回数の合計を指します。つまり誰かがあなたの投稿を何度も開くと、そのたびにカウントされます。1人でも何度も見れば、その人は複数のインプレッションを作り出します。これに対してリーチ数は投稿を見た人の人数を表します。1人が何度見ても、リーチは1として数えます。ここが大切な分岐点です。
この違いを理解しておくと、データを読み解くときに正しい結論を導きやすくなります。たとえば同じ投稿でインプレッションが多くてもリーチが低い場合は、表示回数が特定の人に偏っているということです。反対にリーチが高くてもインプレッションが低い場合は、多くの人に届いているが一度の閲覧で終わっている可能性がある、つまり関心を引く工夫がまだ足りない状況かもしれません。
以下の例を考えてみましょう。例:投稿を1日に100回表示され、70人が見たとします。インプレッションは100、リーチは70。同じ70人が1日あたり3回ずつ見た場合、インプレッションは300、リーチは70です。これにより、同じ投稿でも「どの程度の人数にどのくらいの頻度で届いているか」がわかります。
このような違いを正しく理解したうえで、データを活用することが大切です。リーチを増やす戦略と表示回数を増やす戦略を使い分けることで、目的に合わせた改善がしやすくなります。
このあと、表で各指標の要点を整理します。
実務での使い分けと注意点
このセクションでは、インプレッションとリーチを実務でどう使い分けるかを詳しく考えます。まず、高いインプレッションが必ずしも高いリーチを意味するわけではありません。長い投稿や繰り返し表示される動画は、同じ人に何度も表示されやすく、結果としてインプレッションは多くても到達した人数はそれほど増えません。
逆にリーチが高いのにエンゲージメントが低い場合は、表示先が適切でない可能性やクリエイティブが興味を引けていない可能性を示します。したがって、キャンペーンの評価は「誰に届いたか」と「その人たちがどう動いたか」を両方見るのが基本です。タイミング・方法・クリエイティブを変え、2週間程度の周期で指標を比較するとよいでしょう。
またプラットフォーム差にも注意が必要です。Instagram・TikTok・Xなどは表示アルゴリズムやカウントの取り方が異なります。同じ投稿でもプラットフォームによって数値が大きく変わることがあるため、横断比較の際には各指標の意味を揃えることを意識してください。
実務のコツをまとめます。
1) 目的に合わせて指標を選ぶ(ブランド認知ならリーチ重視、直接の行動喚起ならエンゲージメント)。
2) 投稿の頻度と露出の質を両方意識する。
3) クリエイティブを改善して、再表示を減らしつつ新規視聴者の獲得を狙う。
4) データ期間をそろえ、週次や月次での比較を習慣化する。
最終的には、両方の指標をセットで見て、誰に届き、どう動いているのかを判断するこれが、より正確な分析と、効果的な改善につながります。
リーチ数を深掘りしてみると、届いた人数だけを見ても見えてこないことが多い。実はリーチの“質”と“量”の両方を意識することが大切です。たとえばリーチが多くても、見てくれた人のうち実際に反応する人が少なければ効果は薄い。逆にリーチが少なくても、特定のグループに強い訴求が刺さっていれば結果は出ます。私たちはリーチだけでなく、インプレッションと組み合わせて判断する力を養うべきです。誰に届いているかを想像しながら投稿を設計すると、データはぐっと分かりやすくなります。





















