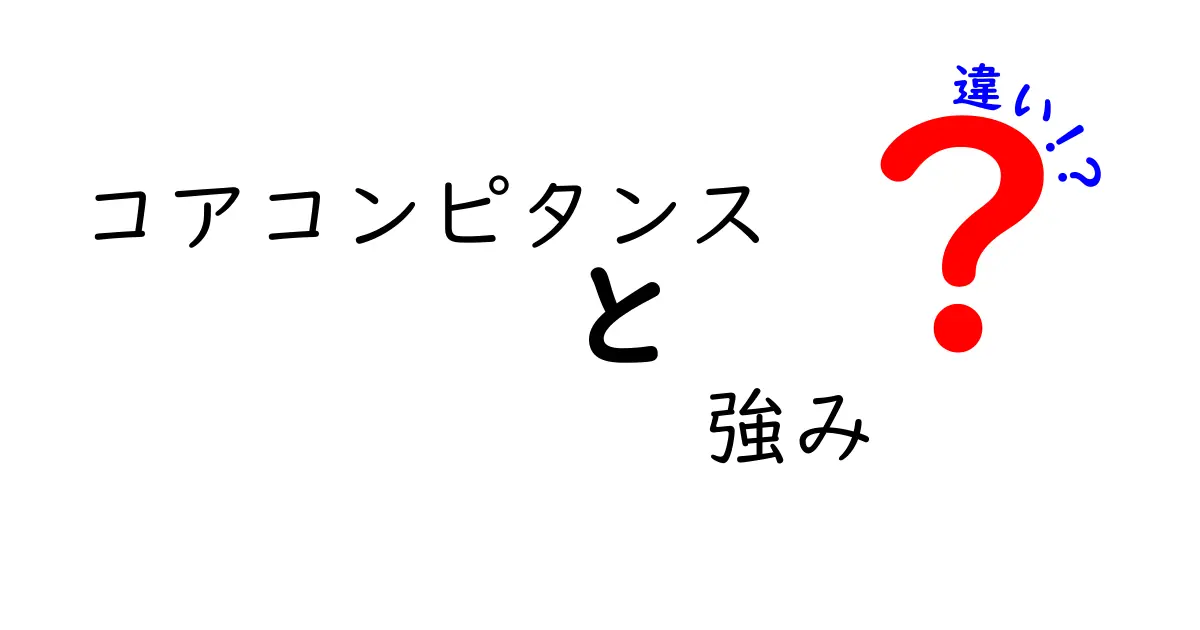

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コアコンピタンスと強みの基本を押さえる
ビジネスの世界でよく耳にする言葉に「コアコンピタンス」と「強み」があります。これらは似ているようで意味が異なります。コアコンピタンスは企業が長期的に競争優位を築くための中核的な能力を指します。一方、強みは個人や組織が得意とする能力や資源の総称で、日常の仕事でも使われる言葉です。ここでは、両者の定義、例、そして実務での使い分けを分かりやすく解説します。まず、価値を生み出す連携部分を洗い出し、どれを強みとして伸ばすべきかを見極めることから始めましょう。
コアコンピタンスを見つけるには、三つの視点が有効です。第一に市場での再現性と模倣難易度、第二に組織の価値連鎖を動かす役割、第三に長期的な差別化の源泉としての潜在力です。これらを整理することで、企業が追求すべき方向性が見えてきます。強みは日頃の業務で誰でも使える概念ですが、それを「競争優位の根」を成すコアに育てるかどうかが鍵です。
このあとの表は、コアコンピタンスと強みの違いを横断的に整理するのに役立ちます。
これらを理解したうえで、次のセクションで具体的な使い分けと実践方法を見ていきます。
違いを活かす具体的な使い分けと実践例
実務での使い分けは、まず自社の価値連鎖を描くことから始まります。
ステップ1として価値を生む連携を洗い出し、競合と比べた再現性と模倣困難性を評価します。
ステップ2としてその中から長期的に差別化を生む要素を特定します。
ステップ3ではその要素を組織文化や教育、採用に結びつけ、日々の意思決定で優先順位を明確にします。以下は実践の具体例です。
- 例1:製造業のA社はサプライチェーンの高度な統合能力をコアコンピタンスとして育て、他社が模倣しづらいノウハウとシステムを整えました。
- 例2:サービス業のB社は顧客データの分析とUX設計の結合を強みとして、個々の顧客に合わせた体験を提供します。
- 例3:創業期のC社は社内の学習文化と意思決定のスピードを磨き、変化に強い組織として成長しました。
このように、コアコンピタンスは長期戦略の中心であり、強みは日常の活動を支える力です。これを正しく使い分けると、資料作成や人材育成、新規事業の選択など、意思決定の場面で迷いが減り、成果が安定します。
とくに新規開発や市場参入のときには、コアコンピタンスを核に据え、その他の強みを補完的に活用するのが効果的です。
ねえ、コアコンピタンスって難しく聞こえるけど、要は“他には真似できない強みの源泉”のことだよ。たとえば、部活動の連携力や学校の情報整理のやり方など、日常の中の小さな流れを根幹で支える力がそれ。これに気づくと、何を伸ばすべきか、どう差別化するべきかが見えてくる。
次の記事: 内部要因と外部要因の違いを徹底解説:中学生にも伝わる基本と実例 »





















