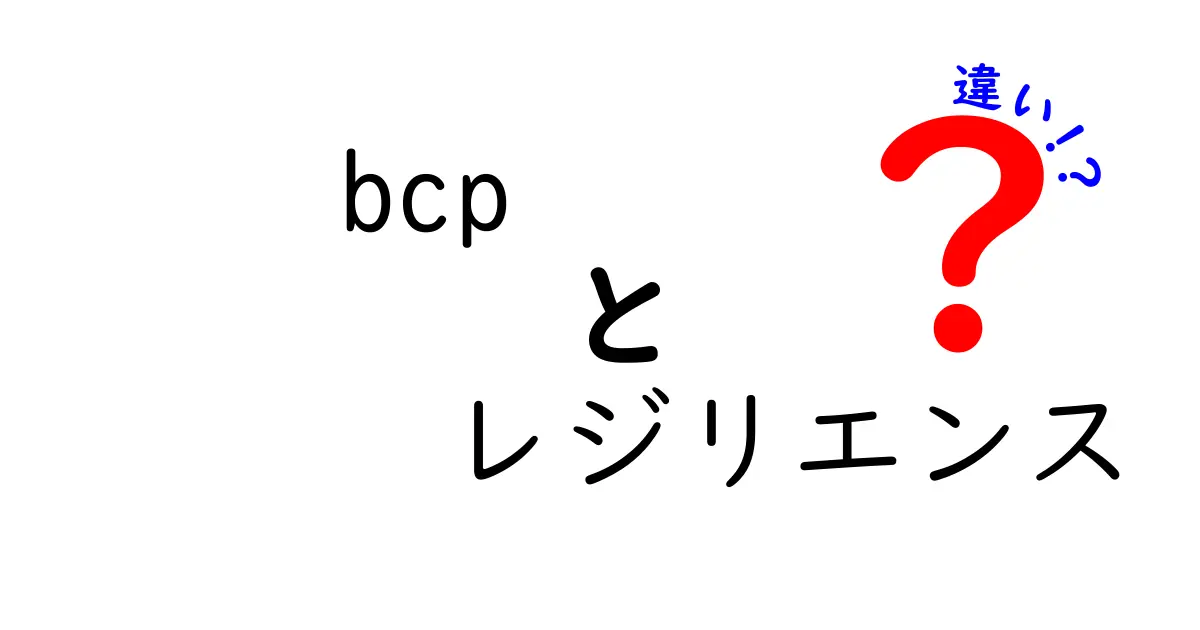

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:bcpとレジリエンスの違いをつかむ
BCPとレジリエンスは、現代の企業経営における安全網の柱です。BCPは災害や事故が起きたときに“何をどう守るか”を決める計画そのものを指し、具体的な手順書や責任分担、連絡方法、資源の配置などを組み上げます。一方でレジリエンスは組織全体の回復力と順応力を意味する能力そのものであり、危機が起きても機能を維持し、速やかに元の水準へ戻す力や、状況の変化に対応する柔軟性を含みます。
この2つは別の概念ですが、現場では互いを補完する関係として活用されます。BCPが“どう動くか”の青写真を提供するのに対し、レジリエンスはその青写真を現場で活かす力を支える実践力と文化を育てます。
以下の見出しでは、具体的な違いを観点別に詳しく見ていき、実務での使い分け方を整理します。
1. BCPとは?基本の定義と目的
BCPはBusiness Continuity Planningの略で、組織が重大な障害を受けても“最悪の事態を想定し、重要な業務を継続または早期復旧するための計画”を指します。目的は業務の中断を最小化し、顧客サービスを維持すること、財務的損失を抑えること、ブランドの信頼を守ること、そして契約上の義務を履行することなど、多面的です。具体的には、影響を受ける業務を特定するBusiness Impact Analysis(BIA)、復旧の目標時点を決めるRTO(Recovery Time Objective)やRPO(Recovery Point Objective)、復旧手順を整理する復旧戦略、連絡網・責任分担の整備、訓練と演習、改善の仕組みなどが含まれます。
ここで大切なのは、BCPは“作るだけではなく現場で使われるべき計画”という点です。現場の人が実際に理解し、日々の業務の中で訓練を通じて自分の役割を確実に果たせるように育てることが求められます。
また、BCPは変化するリスクや前提条件にも対応する柔軟性を前提として設計することが重要で、演習を重ねるごとに現実世界の対応力を高めます。
2. レジリエンスとは?組織の回復力と順応力
レジリエンスは危機の衝撃を受けても崩れにくい設計と迅速な回復を両立させる力を指します。組織レベルでは、戦略の柔軟性、意思決定の速さ、情報の透明性、部門間の協働、ITの冗長性、サプライチェーンの多様性、危機後の学習と改善の文化など、複数の要素が絡みます。
実務的には、レジリエンスは日常の運用の中で育つものであり、予防策だけでなく“崩れた後の復旧”を誰がどう行うかという復旧力と、危機の先を見据えた適応力の両輪を強化します。人材育成や情報共有の仕組み、現場の意思決定プロセス、技術基盤の耐性など、組織全体の文化として根付くことが重要です。
この力は、単発のイベント対策だけでなく、長期的な成長戦略と結びつけて育成されます。
3. BCPとレジリエンスの違い:観点別に比較
観点ごとに整理すると、BCPは「何を守るか」「どの順序で動くか」を決める計画」であり、レジリエンスは「危機をどう乗り越え、どう再成長するか」という能力全体を指します。対象範囲も異なり、BCPは主に重要業務・機能の継続と復旧に焦点を当てるのに対し、レジリエンスは組織全体のプロセス・人材・文化・技術の総合力を高めます。
実務上は、BCPは演習を通じて実際の手順を検証することが中心ですが、レジリエンスは日常の運用改善や組織文化の醸成を通じて長期的に強化します。下の表は、両者の違いを一目で確認できるようにまとめたものです。観点 BCP レジリエンス 目的 重要業務の継続と早期復旧 崩れにくさと迅速な回復・適応の両立 対象 業務機能・部門 中心となる活動 BIA、RTO/RPO、復旧手順 組織文化、意思決定の柔軟性、情報共有、冗長性 評価・改善の頻度 訓練・演習を通じた定期的見直し 成果指標 復旧時間の達成、業務中断時間の短縮
この観点を元に、次の見出しでは実務での使い分けとコツを具体的に解説します。
4. 実務での使い分けと実践のコツ
実務の現場では、BCPとレジリエンスを一体的に運用することが最も効果的です。まずBCPは“手順書を現場で使える状態にする”ことが大事です。
そのためには、現場の業務を理解した担当者の参加、訓練の頻度、演習のフィードバックを組み込み、必要な改善を素早く反映できる回す仕組みを整えます。次にレジリエンスは“日常の継続的改善”を意識して育てます。
具体的には、情報共有のプラットフォームを整備し、部門横断の協働を促す、ITの冗長性を確保する、サプライヤーの多様性を確保する、危機後の学習を定着させるなどの取り組みを組み合わせます。
最後に、演習と現場の振り返りをセットで回すことが重要です。緊急時の意思決定の速さは訓練で育ち、日常の小さな問題解決がレジリエンスの土壌になります。これらを意識して運用することで、BCPは単なる文書から「生きて働く仕組み」へと変わっていきます。
友だちと雑談していたとき、レジリエンスってただ“復旧力”のことだと思っていたんだけど、実はそれ以上に“変化に強くなる力”なんだと気づいたんだ。例えば学校の部活で、天気が悪く大会が延期になっても、別の練習メニューをすぐ取り入れて練習をどう継続するかを即決できるかどうか。これがレジリエンスの実践場面。BCPは計画を作る作業だけど、レジリエンスはその計画を現場でどう機能させ、どう学んで次に活かすかという成長のサイクルだと思う。
だから両方を合わせて使えば、万一のときにも心強いチームになるって、友だちと話していて実感できたんだ。





















