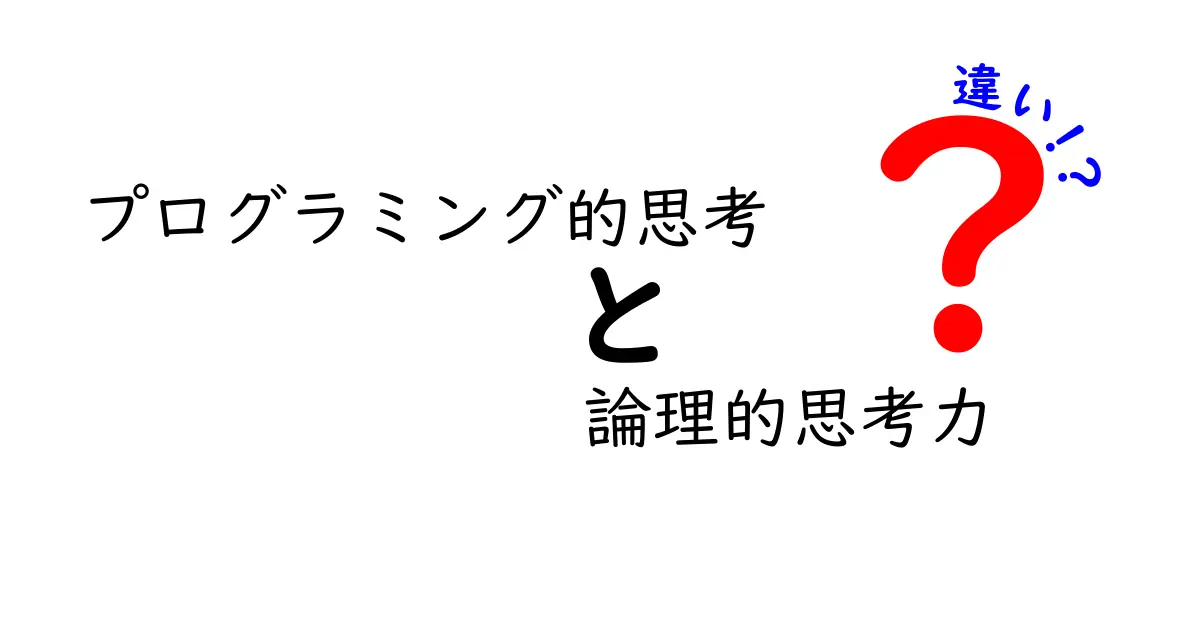

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに プログラミング的思考と論理的思考力の違いを知ろう
このコラムではまず二つの考え方の基本を整理します。プログラミング的思考は「問題を解くための手順を設計する力」であり、実際にコンピュータに動かすための段取りを考える力です。対して論理的思考力は「物事のつながりや真偽を順序立てて判断する力」であり、必ずしもプログラムを書くことを前提にしていません。どちらも“分解して整理すること”“共通の筋を見つけること”が大事ですが、目指すゴールと使い方が少し異なります。ここでは中学生にも理解しやすい言葉で、両者の違いを日常の場面に置き換えて解説します。
まずはこの二つの力がどう分かれているかを大枠で押さえましょう。
プログラミング的思考は問題を解くための手順を設計する力です。例えば算数の問題を解くとき「どうすれば答えに近づくか」を順番に並べる作業がこの思考です。ゲームを作るときには、何をどう動かすか、どの順番で動かせばうまくいくかを考えます。現実の場面でも、料理のレシピを機械的に再現するような感覚で、作業を順序立てて整理する力が鍛えられます。
一方で論理的思考力は、物事の条件と結論のつながりを正しく理解し、矛盾がないかを確かめる力です。証明の筋道を追うときや、意見が正しいかどうかを検証するときに働きます。日常でも情報の真偽を判断する場面で役立ち、会話の中で「なぜそうなるのか」を根拠を持って説明する力が身につきます。
両方を同時に使うと、問題解決の力がぐんと高まります。例えば学校の課題で、まず問題を小さく分解して理解するのがプログラミング的思考、次に分解した要素同士の関係性を確認して正しく組み立てるのが論理的思考力です。プログラミングは道具を使った実践練習、論理は自分の考えを正しく伝える練習と考えると分かりやすいでしょう。
この二つの力は互いに補完関係にあり、いずれか一方だけを磨くよりも、両方をバランスよく伸ばすことが大切です。
ここからは具体的な違いを表にして整理します。下記の表は要素ごとにどの視点が強いのかを示しています。
具体的な場面での違いを分けて考えるコツ
日常の例で考えるとわかりやすいです。例えば学校の掃除当番を決める場面を想像してみましょう。プログラミング的思考なら、掃除をどう分担するかを手順化します。まず機械的に「誰が何をするか」をリスト化し、ゴミを出す順番・掃除道具を使う順序など、再現性の高い手順にします。次にその手順を実際に誰が見ても同じように実行できるよう、チェックリスト化します。これが実装可能な手順になるという考え方です。
対して論理的思考力は、なぜその分担が最適なのか、みんなの動きが矛盾していないかを検証します。誰が動くときに誰の動きと衝突するのか、時間の配分は適切か、道具の使い方の前提は正しいか、という“筋の通り”を確認します。
このように同じ場面でも、まずは手順を作るのがプログラミング的思考、次にその筋道を確かめるのが論理的思考です。
次に、実際の学習で役立つポイントをいくつか挙げます。1つ目は分解と抽象化です。大きな問題を小さな部品に分け、共通点を見つけて抽象化します。2つ目は再現性の確保です。作成した手順が他の人にも同じ結果を出せるかを確認します。3つ目は検証と修正です。間違いを見つけたら原因を追い、どう直せばよいかを考えます。これらを繰り返すことで、プログラミング的思考と論理的思考力の両方が自然に身についていきます。
このコラムを読んでくれている中学生のみなさんには、まず身の回りの小さな課題から試してほしいです。例えば家の片付けの手順をノートに書き出し、友達と共有してみる。次に、その手順が本当にうまくいくか検証します。こうした実践を積むと、自然と二つの力の使い分けが身についてきます。最終的には、何をどう進めるべきかを自分で判断できるようになり、将来どんな仕事に就いても役立つ力になります。
さて話の中で印象に残ったのは、プログラミング的思考と論理的思考は別々のものではなく、むしろ同じ道具箱の中の二つの道具だという点です。私はあるとき友だちとゲームの攻略を話していたのですが、彼はまず“どうやって勝つかの手順”を決めてから動こうとしていました。私はその前に“なぜこの順番だと正しいのか”を突きつめるタイプでした。結局、成功の鍵は両方を使い分けることでした。
だからこそ、日常の小さな課題でも、まず手順を作ってから、次に筋道を確かめる。これを繰り返すと、何をやるにも合理的に進められるようになると実感しています。みんなも自分の生活の中で、手順と根拠を両方意識してみてください。きっと新しい発見があります。
次の記事: やる気と情熱の違いを理解して、今日から行動が変わる5つのヒミツ »





















