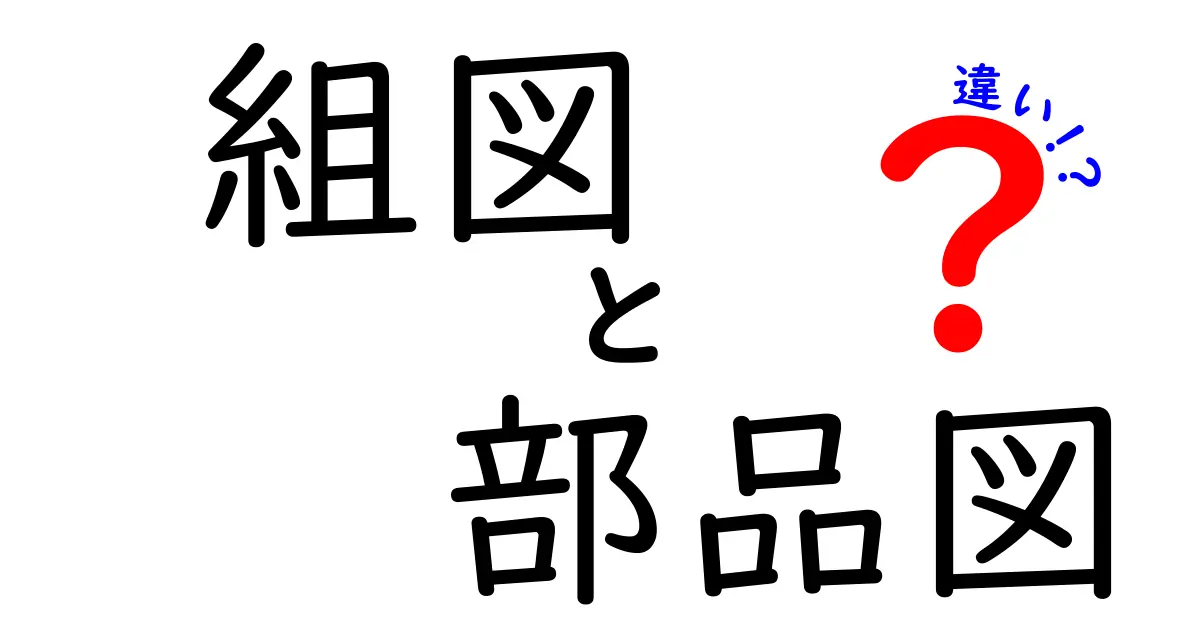

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
組図と部品図の違いを徹底解説:図面読みの力を一歩深めるための基本ガイド
ものづくりの現場では、設計図や製造図を正しく読み解く力がとても大切です。特に組図と部品図は、同じ図面でも役割や見方が大きく異なります。この記事では、両者の違いを中学生でも分かるように、具体的な例や表、読み方のコツを交えながら丁寧に解説します。図面を初めて触れる人でも、部品の名前や番号、数量、公差といった基本的な要素を押さえるだけで、全体像を把握できるようになります。読み方を誤ると、組み立て時に部品が干渉したり、数が足りなかったりといったトラブルにつながることがあります。そのため、まずは部品図と組図の目的をしっかり区別することが大切です。
このガイドを読んで、図面が「何を伝えようとしているのか」を読み解く力を身につけましょう。
本記事は、部品図と組図の基本的な違いだけでなく、現場での読み方のコツや、誤解を生みやすいポイント、さらに実務で使える簡単な見分け方も紹介します。読み進めば、部品の特定、組み立ての順序、マテリアルリストの参照など、図面を使う場面で役立つ知識が自然と身についていきます。
それでは、まず部品図の基本から見ていきましょう。
部品図とは何か。その基本と読み取りのコツ
部品図は、個々の部品一つひとつの情報を詳しく示す図面です。部品図の中で最も重要な目的は、部品自体の仕様を明確に伝えることです。部品番号、名称、数量、寸法公差、材料、表面処理、そして場合によっては加工の指示(ドリル径やねじのピッチなど)まで記載します。
部品図を正しく読むためのコツは、まず「どの部品か」を特定することです。部品図には、部品番号が一目で分かるように大きく表示されていることが多く、BOM(部品表)と連携してこの部品が何個必要か、どの部品と組み合わせるのかを把握します。次に、寸法の読み方をチェックします。部品図には公差が併記され、実際の製造時にはこの範囲内で部品を作る必要があります。公差が緩い部品と厳しい部品では加工の難易度やコストが異なるため、設計者と製造者の間で合意を取るポイントになります。さらに、部品の材料や表面処理も重要な情報です。材料が鉄なのかアルミなのか、表面処理がメッキなのか陽極酸化処理なのかで、耐食性や耐摩耗性、加工性が変わってきます。
部品図を読み解く際の注意点は、同じ図面内で複数の部品が混在していないか、部品番号の対応関係が正確か、図中の注記や矢印の意味を見逃さないことです。部品図は、個々の部品の仕様を正確に伝えるための“部品データの集合体”と考えると理解しやすいでしょう。最後に、部品図は単体の部品だけでなく、製品全体の部品構成を把握するための基礎にもなります。部品がどのように組み合わさるかを想像する力がつくと、設計や検証の作業もスムーズになります。
組図の特徴と読み方
組図は、複数の部品がどのように組み合わさって一つの製品になるかを示す図面です。主な役割は部品同士の組み合わせ方、相互の干渉を避ける、組立順序、そして全体としての機能を伝えることです。組図には「 exploded view( exploded 図)」と呼ばれる部品がバラバラに配置された視点があり、どの部品がどの位置で、どの順序で取り付けられるかを分かりやすく示します。これによって、現場の組立作業者は手順を追いやすく、組立ミスを減らすことができます。組図には部品図にはない特徴として、部品間の干渉チェック、組立順序の矢印、結合方法の指示、組み立て治具の必要性などが加わります。
読み方のコツとしては、まず図の参照記号を部品表と対応づけることです。例えばA-1やB-2といった設計上の参照記号は、図の各部品を指し示します。次に、 exploded view などの視点で、部品がどの順番で組み上がるかを追います。組図のもう一つのポイントは、機能別のざっくり理解です。例えば「このモーターとこのギアはどの軸で回すのか」「このねじはどこに力を伝えるのか」といった、機能の連携を把握すると全体像が見えやすくなります。さらに、組図はBOMと連携して全体の部品数と材料の把握に役立ち、製造計画を立てる際にも欠かせない資料です。総じて、組図は「完成品がどう動くのか」を読み解くための地図であり、部品図は「完成品を作るために必要な部品の詳細情報の辞書」と言えるでしょう。
以下に部品図と組図の要点をコンパクトに比較します。要素 説明 目的 部品の個別仕様と数量を伝える 組立情報 部品の結合方法・順序・干渉を示す 参照デザイン 部品番号と設計記号の対応を明確化 使用場面 製造・品質管理・部品選定の基準
このように、部品図と組図は目的と伝え方が異なるため、それぞれの図面の読み方を分けて練習することが、図面の理解を深める近道になります。最後に、実務で迷いやすいポイントとして「同じ部品が複数の図で表現されていないか」「図中の注記が最新版と一致しているか」をチェックする癖をつけましょう。これで、読み間違いを減らし、図面の信頼性を高めることができます。
友だちと学校の課題の話題で、部品図と組図の違いを話していたときのこと。部品図は“この部品は何で、どう作るのか”を細かく示す辞書みたいだね。一方、組図は“この部品どうやって組み合わせるのか”を伝える地図みたい。A君は「部品図が指示書なら、組図は組み立ての手順書だ」と言い、Bさんは「図面は同じ製品の別の見方。両方がそろわないと完成品が作れない」と結論づけていた。実際、現場では部品図と組図をセットで確認するのが基本で、部品の数量や公差を正しく知ることで、組み立て時の干渉や不足を未然に防げるんだ。
前の記事: « クラフト紙と再生紙の違いを徹底解説!素材選びで印象が変わる理由





















