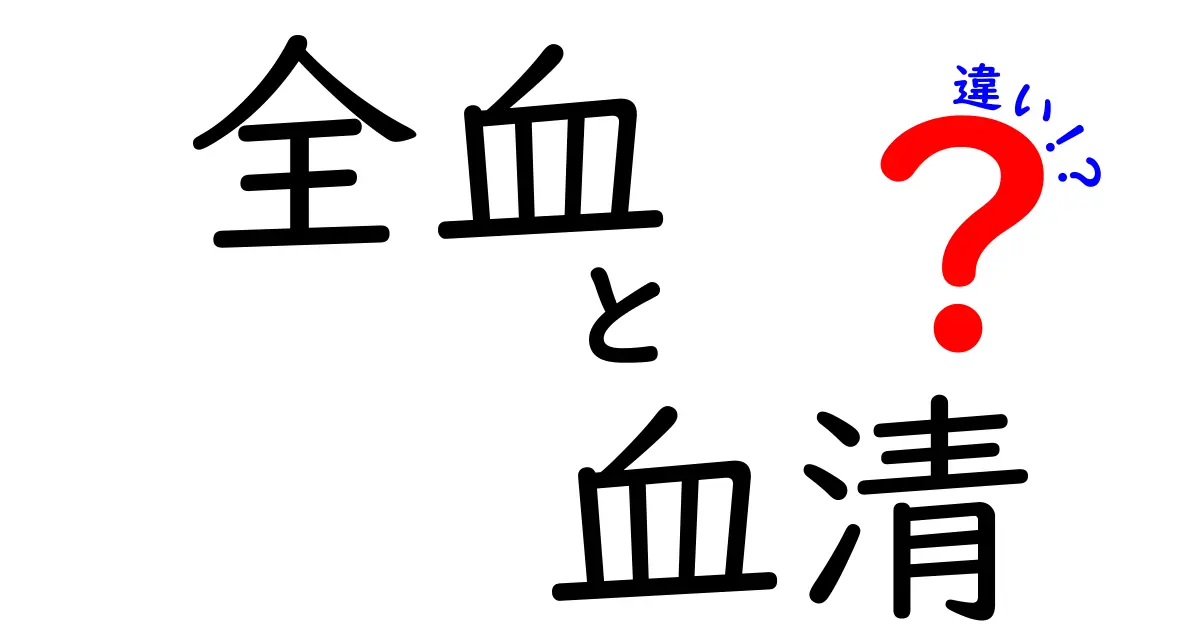

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
全血と血清の違いを理解するための基本
このセクションでは、全血と血清という言葉の基本的な意味を、日常の例えを使って解説します。血液は体の中でさまざまな役割を果たしており、酸素を運ぶ、栄養を届ける、病原体と戦う免疫機能など、多くの大切な仕事をしています。全血はそのままの血液全体を意味し、血液を採取したときの“生の状態”のことです。対して血清は、血液を採取して固まり、沈殿とともにできた液体成分のことを指します。
この二つは、同じ血液から来ているものの、含まれる成分が違うために使い分けが必要です。
例えば、献血後に検査を受けるとき、全血を使う検査と<血清を使う検査があり、それぞれに適した方法で測定が行われます。
以下のセクションでは、全血と血清の定義、成分、そして臨床現場での実際の使い分けを、わかりやすい言葉で詳しく解説します。
全血とは何か
全血とは、採血したそのままの血液のことを指します。ここには赤血球(酸素を運ぶ車の役割)、白血球(病原体と戦う兵士)、血小板(血を止める粘りのある部品)、そして血漿(液体成分)がすべて含まれています。全血は抗凝固剤を使わずに採取した場合の血液全体、または抗凝固剤を使って採取した場合の血漿を含む状態の血液、さらに血液をそのままの状態で測定する検査に用いることが多いです。
このように全血は、体の中で実際に働く成分すべてがまだ混ざっている状態を表します。
臨床の場面では、CBC(全血球計算)、血液型検査、一部の感染症検査などで全血が使われます。
つまり、全血は“血液のどの成分も分けずにそのままの形で扱う”イメージです。
使い方のポイント:全血は、血液の細胞成分を観察する検査や、血流の状態を評価したいときに適しています。
また、血液の凝固を止めずに測るか、凝固させて別の成分を測るかで、次に説明する血清や血漿の扱いが変わってきます。
血清とは何か
血清は、血液を採取してから血液が固まるのを待ち、固まった後に固形の成分を取り除いた液体部分のことを指します。固まる過程で体内のフィブリンというたんぱく質が絡み合い、血液が固まり血餅(凝固塊)を形成します。この塊を取り除いた後の液体が血清です。血清には凝固因子(フィブリンなど)がほとんど、あるいは全ての形で含まれていません。これにより、血清は血漿よりもたんぱく質の組成が異なることがあります。
臨床の現場では、生化学検査(血清化学検査)、特定のホルモンや代謝産物の測定、薬物モニタリングなどで血清を用います。
血清を使うと、凝固因子の影響を避けて検査が行える場合が多く、結果の解釈が比較的安定します。
覚え方のコツ:血清は“血が固まった後の液体”で、凝固因子が少ない、という点を覚えておくと混乱しにくいです。
また、血清と血漿の違いは、凝固因子の有無と採取時の処理方法の違いで覚えると便利です。
全血と血清の違いと臨床での使い分け
全血と血清の最も大きな違いは、「含まれる成分」と「測定の目的」です。全血には血液のすべての成分が含まれており、主に細胞成分の情報を得る検査に適しています。一方、血清は凝固因子が少なく、化学的な成分を精密に測る検査に向いています。
臨床現場では、検査目的に応じて適切なサンプルを選ぶことが重要です。たとえば、血算が必要な場合は全血、肝機能や腎機能の指標を測る場合は血清、といった具合です。
また、採血時の処理手順も異なります。全血は抗凝固剤の有無や輸送条件で結果が影響を受けやすく、血清は凝固時間と遠心分離の条件が結果を左右します。
このような違いを理解しておくと、検査結果を正しく読み取るうえで非常に役立ちます。
医療現場では、患者さんの安全を第一に考え、検査目的に最も適したサンプルを選ぶことが求められます。
もし検査の意味が分からない場合は、医療従事者に質問して、どのサンプルがどの検査に使われるのかを確認すると良いでしょう。
違いを表で整理
このように、全血と血 Serumは同じ血液から作られますが、使い分けの目的と成分の違いを理解することが、検査結果の正確さに直結します。
学習の初期段階では混同しやすい組み合わせですが、現場ではこの違いを常に意識することが大切です。
あなたが将来、医学や生物の道に進むとき、この違いの感覚がきっと役に立ちます。
血清について深く掘り下げた小ネタです。友だちと部活の後にこんな会話をしてみてください。『ねえ、血清って血が固まった後の液体って知ってた?』と尋ねると、彼は『凝固因子がないから測定が安定するんだよね』と返してくるかもしれません。実は血清は凝固因子をほとんど含まないため、薬物や代謝物の濃度を正確に測るのに適しています。部活の後の雑談でも、この考え方が役立つのです。もし検査で血清を使う理由を尋ねられたら、『環境や試薬の相互作用を減らして、正確な値を取りたいから』と答えると会話が深まります。血清と血漿の違いを覚えるコツは、凝固因子の有無を決め手にすること。こうした小さなポイントが、将来の医療知識の基礎になるのです。





















