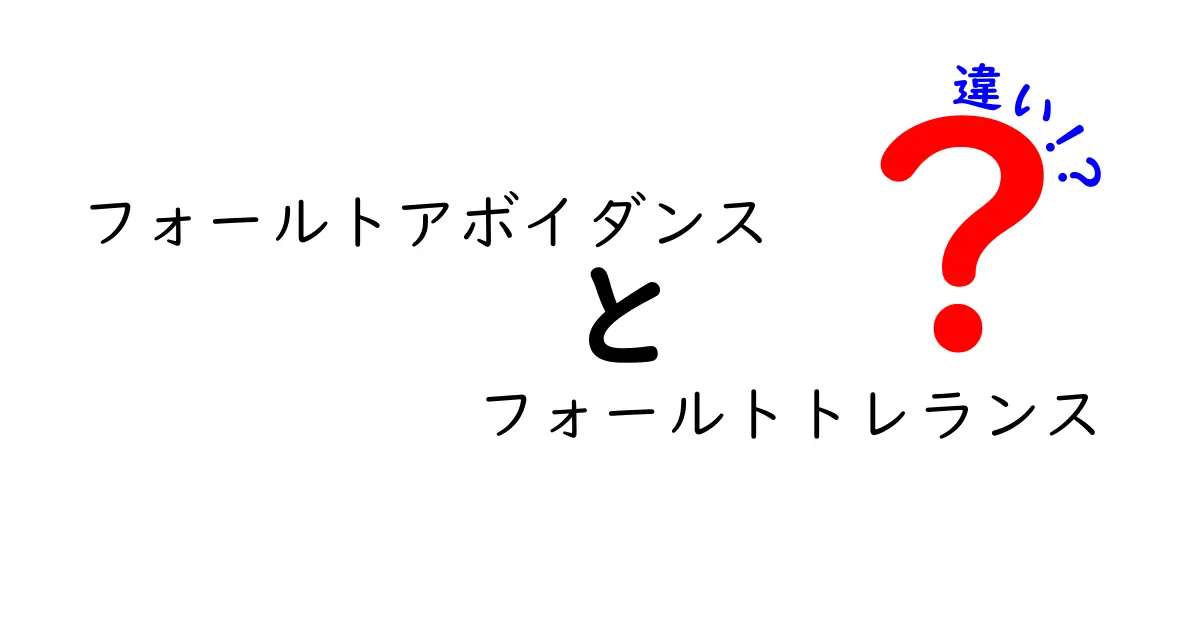

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに フォールトアボイダンスとフォールトトレランスの違いを正しく理解するための基礎知識
技術の世界には「フォールトアボイダンス」と「フォールトトレランス」という似た言葉があります。似ているようで目的や考え方が違うため、場面に応じて使い分けることが大切です。
特にソフトウェア開発やシステム運用の現場では、前もって問題を起こさない工夫をするか、問題が起きても影響を最小限にとどめて続けられるよう備えるかのどちらを優先するかで、設計やコスト、リスクの捉え方が変わります。
この違いを理解すると、どの場面でどちらを選ぶべきか、どんな対策が現実的かが見えてきます。
本文では、身近な例と基本的な考え方を、中学生にもわかる言葉でやさしく解説します。フォールトアボイダンスは「失敗を未然に防ぐ道具箱」、フォールトトレランスは「失敗が起きても機能を保つ仕組み」と覚えると理解しやすいでしょう。
違いの要点を押さえる:定義・目的・実装の観点から見るフォールトアボイダンスとフォールトトレランス
ここでは両者の定義を具体的に分け、どんな場面でどちらを採用するべきかを整理します。
フォールトアボイダンスは「起きないように作る」考え方で、入力の検証・境界条件の設定・安全な設計・外部依存の削減などを含みます。
対してフォールトトレランスは「起きても動き続ける」ことを重視します。冗長化・バックアップ・監視と自動回復・フェイルセーフな分割などが典型です。
現実のシステムでは、完全にフォールトアボイダンスだけで対応するのは難しいため、実際には両方を組み合わせて「できるだけ創出される故障を抑えつつ、故障が発生しても被害を最小化する」というハイブリッドな戦略が多く用いられます。
この両者を適切に組み合わせるためには、まず「何が最も重大なリスクか」を判断することが必要です。たとえば、金融取引システムでは一つのミスも許容されないためフォールトアボイダンスの設計が重要になる一方、クラウドサービスの大規模な運用ではフォールトトレランスの考え方が中心になります。
このように、目的と状況によって適切な組み合わせは変わるのです。
フォールトアボイダンスの特徴と具体例
フォールトアボイダンスは、 「故障を未然に防ぐこと」に力を入れる設計思想です。入力値の検証、境界条件の設定、型の安全性を確保するプログラミング、外部依存を減らすモジュール分割、デフォルト値の設定などが主な手段です。
たとえば、スマホのアプリでユーザーが間違ったデータを入力したときに、すぐにエラーメッセージを出して処理を中断するのではなく、受け入れられる範囲へ自動的に調整することが可能なら、利用体験は途切れにくくなります。
また、セキュリティ面でも、信頼できない入力を内部で徹底的に拒否する設計はフォールトアボイダンスの典型例です。
この考え方は、ハードウェアの故障を前提とした設計にも適用され、部品を冗長化して故障の発生を前提としても全体の品質を保つ工夫にもつながります。
ただし、過度な検証や制約は開発コストを押し上げ、使い勝手を悪くすることがあるため、現実的には「どこまで検証を厳しくするべきか」を、リスクとコストのバランスで判断します。
フォールトトレランスの特徴と具体例
フォールトトレランスは、 故障が起きてもシステムが崩れず、機能の一部が低下しても継続利用できる状態を作ることを目指します。冗長性の確保、バックアップの常時用意、フェイルオーバー機能、監視と自動復旧、分散設計などが核心技術です。
例えば、クラウドのディスクが壊れても別のディスクへ自動的に切り替わり、ユーザーにはほとんど影響を与えずに処理を続けられるのは、フォールトトレランスの代表的な実装です。
インターネットサービスでの「複数のサーバ間で処理を分散する」設計も、個々のサーバに故障が起きても全体としては機能を維持する目的の典型例です。
このアプローチは、システム運用の信頼性を高める一方で、コストが高くつくことがあります。重要なのは「どの程度の信頼性が本当に必要か」を見極め、過度な冗長化を避けつつ、適切なバックアップと監視を組み合わせることです。
友だちはフォールトアボイダンスって何だろうと話していた。僕が『故障を未然に防ぐ考え方だよ』と言うと、相棒のユウは『それって、入力を厳しくチェックして、間違いを弾く感じかな?』と返した。私は『そうそう。たとえば入力の範囲外を受け付けず、うっかりミスを機械が勝手に正してくれると助かる』と頷く。さらに彼らは『でも現実には完璧は難しい。そんな時にはフォールトトレランスの方が役立つ場面もある』と続け、現実のプロジェクトでの使い分けについて語り合った。私は彼らの会話から、失敗を恐れすぎず、適切な防御と回復の両方を準備する考え方を深く学んだ。





















