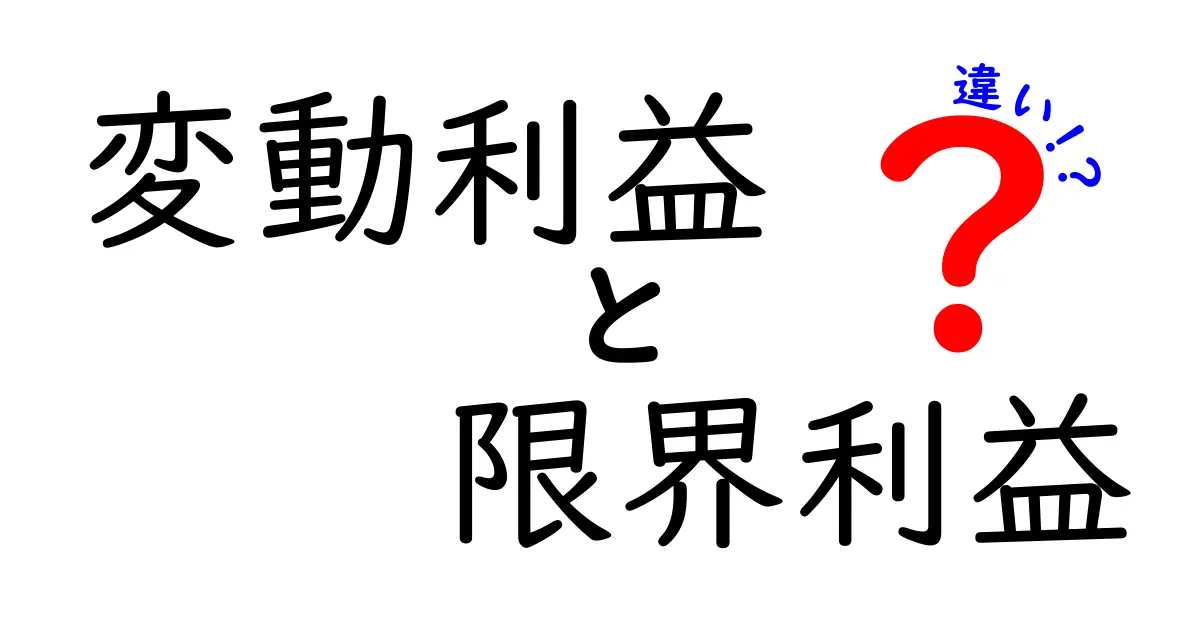

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
変動利益と限界利益の違いをわかりやすく解説
この話は、ビジネスの意思決定を支える基本的な考え方を、できるだけ分かりやすく伝えるものです。
「変動利益」と「限界利益」は、似ているようで使い方が少し違います。
両方とも、売上高から変動的に発生する費用を差し引いた後に残る“貢献できる利益”を表しますが、厳密には呼び方や場面の違いがあり、教科書や業界の慣習で微妙に意味づけが異なることがあります。
この記事では、まずそれぞれの定義を押さえ、次に違いをはっきり整理し、最後に実務での使い方と注意点を具体例付きで紹介します。
変動利益とは
変動利益は、売上高から変動費を差し引いた額として定義されます。
ここでいう変動費とは、数量の増減とともに直接増減する費用のことです。例として、材料費、部品費、販売手数料などが挙げられます。
変動利益の計算式は「変動利益 = 売上高 - 変動費」です。この指標は、製品やサービスを追加で販売したときにどれだけ“貢献できるか”を示すもので、固定費を賄い、最終的な利益へと繋がる基礎となります。
日常の経営判断では、製造量の増減が利益にどう影響するかを考えるときの核となる考え方です。
限界利益とは
限界利益(または貢献利益)も、売上高から変動費を差し引いた額として定義されることが多いです。
つまり、数量の増減に応じて増える利益の“基本となる部分”を指します。
実務上は、固定費をカバーして会社全体の黒字を作る“貢献額”として重要視され、固定費を払い終えればその後は利益が増えやすくなるという考え方につながります。
計算式は同じく「限界利益 = 売上高 - 変動費」ですが、運用上は“固定費を賄えるかどうか”という観点で使われます。また、製品別・部門別の意思決定にも活用され、どの製品を拡販すべきかの判断材料になります。
違いのポイント
結論から言うと、厳密には“変動利益”と“限界利益”は同義語として使われることが多いのですが、文脈や教科書・企業の用語の違いにより、微妙なニュアンスが異なることがあります。
実務では「限界利益」という語は、固定費をどれだけカバーできるかという観点で使われることが多く、意思決定の際の色が強くなります。
対して「変動利益」は、数量の変動とともに増減する利益の総量を指す印象を受ける場面もあり、業界や学校教育の文脈で使われ方が分かれることがあります。
以下の観点を覚えておくと混乱を避けやすいです。
1)売上高と変動費の関係 2)固定費の存在と影響 3)意思決定の場面での使い方の違い
実務での使い方と注意点
実務でこの2つの指標をどう使い分けるかが、意思決定を左右します。
新製品の投入や販促の予算を決めるときには、限界利益を軸に、特定の製品グループが固定費を賄い、黒字化できるかを検討します。
また、複数の製品を扱う場合には、部門別の変動費を正確に把握し、どの製品を増販するべきかを判断します。
ただし、実務では「変動利益」という呼び方が使われる場面もあり、社内の定義を揃えることが重要です。
概念を整理するコツは、固定費は特殊な費用として残り、変動費は販売量に応じて増減すると理解することです。
最後に、表を使ってイメージを固めましょう。
表で見るイメージ
友達同士の雑談形式で深掘りします。ねえ、変動利益と限界利益って同じ意味で使われることが多いけど、実は微妙に使い分けられる場面があるんだ。例えば、同じ売上でも販売量を増やしていく戦略を考えるとき、限界利益が高い製品を優先するべきか、変動費の構成を見直すべきか、という話になる。こうした実務の感覚を、テストのような厳密さと実務の感覚の両面から解き明かしていくと思うと、なんとなくスッキリするよ。
次の記事: 効果・効用・違いの決定版ガイド:日常で使い分けるコツと実例 »





















