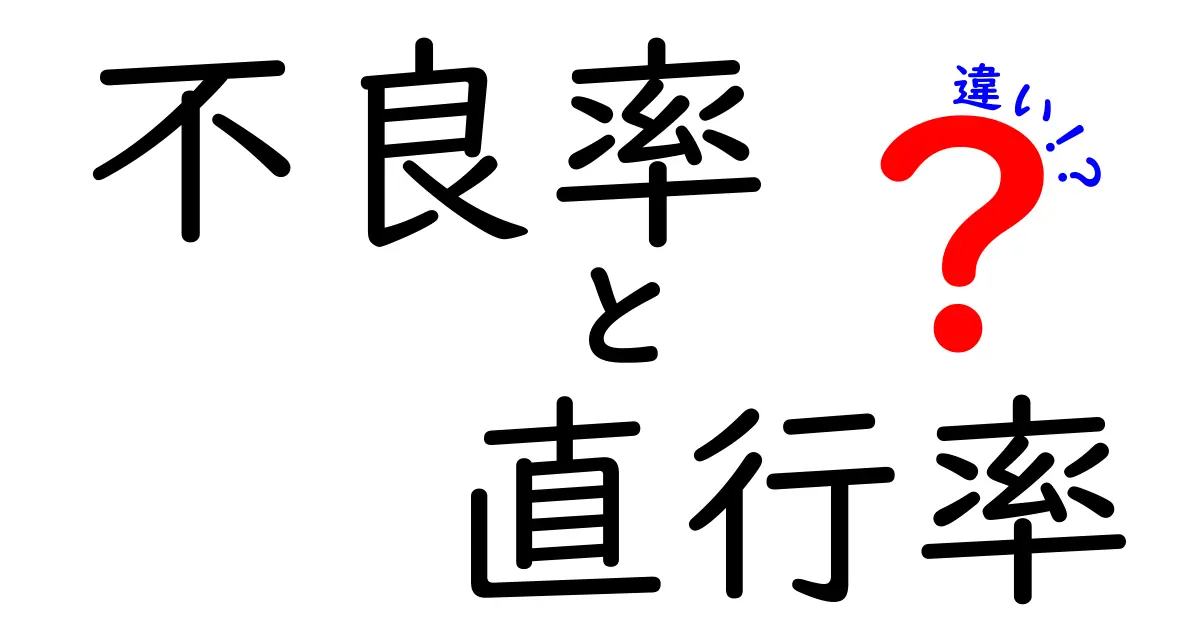

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
不良率と直行率の違いを正しく理解する
ここでは不良率と直行率の基本的な意味と、現場での役割の違いを丁寧に説明します。まずは両者の定義を押さえましょう。
不良率は、製造の品質を測る最も基本的な指標のひとつで、総生産数に対して不良品が占める割合として表されます。品質管理の土台となる数値で、低いほど製品の不良が少なく安定した品質と言えます。
また、直行率は“初回で通過できた割合”を意味します。作業工程を進める際に再加工や再検査が発生せず、そのまま完成品へ移る割合を示します。直行率が高いほど工程が安定し、ムダが少ない状態を示唆します。
この二つは似ているようで、見るポイントと改善の観点が異なります。
以下の章では、それぞれの定義・計算方法・現場での使い方を順に解説します。
ポイントを押さえるコツは、データの取り方と比較する期間の設定を統一することです。どのデータを集計するか、どの時点のデータを使うかで数字の意味が変わってきます。現場では、データの取得方法やサンプルの選び方を揃え、比較可能なフォーマットにしてから分析を始めることが重要です。
不良率の基礎と計算方法
不良率は「不良品数 ÷ 総生産数」で求めます。総生産数には、検査で不合格になった数だけでなく、ロット全体の生産数を含む表現が多いです。
例えば、1000個を生産して50個が不良だった場合、不良率は 50 ÷ 1000 = 0.05、つまり5%となります。ここでのポイントは、どこまでを“総生産数”とみなすかを社内で統一することです。部品の欠品やロットの違いで数値が大きく動くことがあるため、日次・週次・月次で比較する際には同じ基準を使うことが重要です。
正しいデータの取り方と集計の一貫性は、改善の効果を正しく測るうえで不可欠です。
直行率の基礎と計算方法
直行率は「初回検査を通過し、そのまま完成品となった数量 ÷ 総生産数」で求めます。直行率が高いほど、手戻り(再加工・修正)が少なく、工程の安定性が高いと判断できます。
例えば、1000個の製品を生産し、初回で完了したのが900個なら直行率は 900 ÷ 1000 = 0.9、90%です。ここでのポイントは、再加工が発生したケースをどう扱うかです。再加工が多い場合は“直行率が低い”と判断し、原因を特定して工程の見直しを行います。
また、直行率と不良率の関係を読み解くには、工程の段階的な可視化が有効です。初期工程での不良が多くても、後工程で再加工が減るような改善を行えば直行率は向上します。
現場での活用と比較のコツ
現場では、不良率と直行率を別々に monitor するだけでなく、両者の関係性を同時に見ることが大切です。以下の点を意識しましょう。
1) 不良品を減らせば直行率は自然と上がるケースが多いが、それだけで改善するとは限らない。工程のムダを減らし、初期の検査設計を見直す必要がある。
2) 直行率が高くても不良率が高い場合、特定の工程で品質が崩れている可能性がある。検査を増やすのではなく、原因を追求することが重要。
3) 表やグラフで可視化すると、誰でも原因と対策が見えやすくなります。
教室の雑談から始まる不良率の話題。友だちが“どうして不良にならないといけないの?”と尋ねた。私は答えた。現場では、不良をゼロにするのは現実的には難しいが、不良が出る原因を追究して品質を上げることが大事だと説明した。データを見て、どの工程で不良が増えているのか、どの部品で不良が多いのかを特定することが成長の第一歩。直行率については、初回でパスした比率が高いほど作業の無駄が減り、効率が良いとわかる。だから設計と作業手順の改善が欠かせない。データをどう扱い、どう解釈するかが学習の鍵になる。さらに、数字だけを見るのではなく、人の作業や現場の雰囲気も影響することを雑談の中で思い出させてくれた。ミスが起こるとき、誰かが忙しさに負けて判断が甘くなることがある。そんな時は、作業を分解して誰が何をするのか、どの順番で進むのかを再設計する。そうすることで、不良率も直行率も改善され、納期も守れるようになる。





















