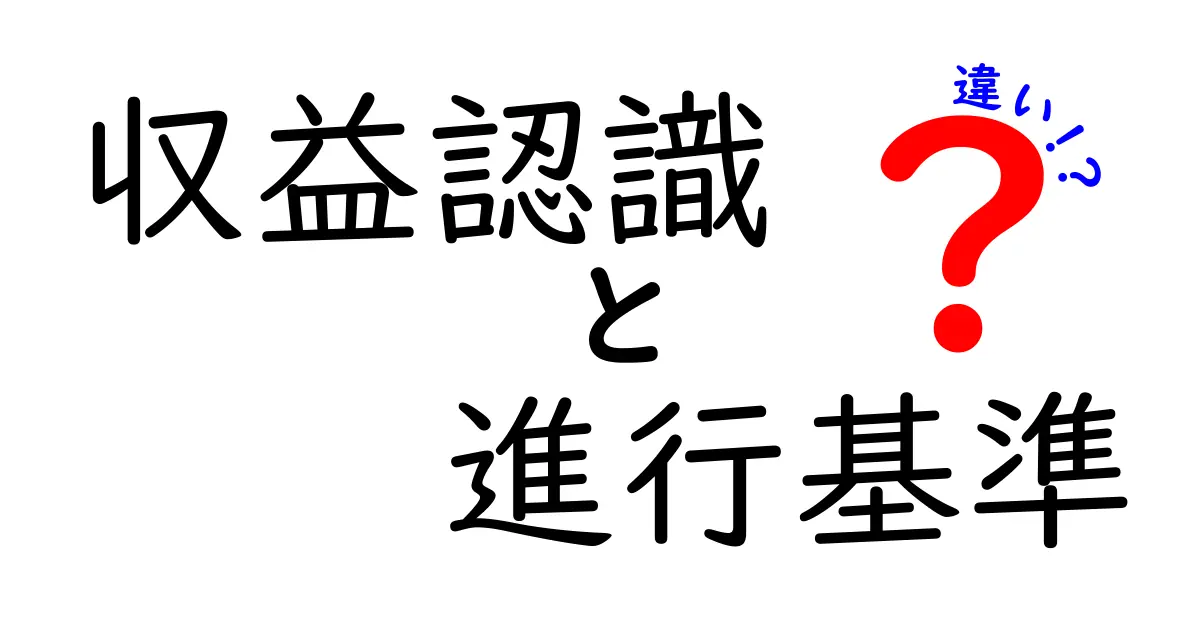

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
収益認識の進行基準と違いを徹底解説!中学生にも伝わる実務のポイント
ここでは「収益認識」と「進行基準」「完成基準」の違いを、難しくなく日常の例とともに解説します。売上がいつ計上されるのか、どんな基準で認識するのかは、企業の財務状況や取引の性質に大きく影響します。特に建設業やソフトウェアのように長い期間に渡る取引の場合、進行基準と完成基準の違いを正しく理解していないと、利益が過大または過小に見えてしまうことが起きます。ここでは中学生にもわかるよう、身近な例と図解を交え、用語の意味、判断基準、実務上の留意点を丁寧に説明します。まずは基本の考え方を押さえ、その後、具体的な適用場面と差異を見ていきましょう。
ここでのポイントは3つです。第一に「いつ」「いくら」を決める基準であること。第二に「顧客に対する支配の移転」がどのタイミングで起きるかを考えること。第三に長期契約では進行度合いをどう測るかが重要になることです。これらを理解すれば、どの基準を使うべきか判断できるようになります。
背景と基本概念
収益認識は「企業が商品を顧客に提供して対価を得る過程を、会計上いつどう認識するか」を決める考え方です。進行基準は長期の契約やサービス提供において、商品の移転が段階的に進む場合に「進捗」に応じて収益を認識します。これに対して完成基準(完了時点認識)は、すべての作業が完了して対価を受け取れる状態になった時点に収益を計上します。現代の会計実務ではIFRS 15やASC 606といった指針が適用され、取引の性質に応じて判断します。
中学生にもわかるように言えば、「作業の進み具合が分かれば分かるほど、売上を細かく分けて記録するのが進行基準」「まだ完成していなければ売上を少なく、完成時に一括で認識するのが完成基準」です。ここを理解するだけで、なぜ同じ取引でも企業ごとに計上時期が違うのかが見えてきます。
進行基準とは何か
進行基準は、長期間にわたる契約や段階的に提供されるサービスで適用されます。ポイントは2つです。第一に「顧客へコントロールの移転」が時間とともに進むかどうかを判断します。第二に「進捗を測定する指標」を使って、売上を部分的に認識します。たとえば建設工事では完成までに数カ月かかることが多く、工事の進捗割合を基準に収益を段階的に積み上げます。進行基準を適用すると、工事の途中段階で利益を少しずつ計上でき、企業の財務状況をより現実に反映させられます。
この基準を正しく使うためには、進捗の測定方法を明確にしておくことが大切です。出荷済みの部品やサービスの提供状況、顧客の承認の有無、契約条件に基づく達成基準などを評価します。
完成基準とは何か
完成基準は、契約の全ての作業が完了し、対価を受け取る権利が生じたときに収益を認識します。長期工事やプロジェクトで、途中で仕様変更が発生したり、顧客の承認が遅れたりする場合に使われることがあります。完成基準は「一括認識」を前提とする考え方で、進行状況に応じて段階的に認識する進行基準とは対照的です。
実務上は、完成基準を採用するかどうかの判断が難しく、契約の性質、リスク、成果物の確定性などを総合的に評価します。完成基準を採用すると、初期の期間には売上が少なく見える一方、プロジェクト完了時には大きな金額が一度に認識され、財務イベントのタイミングが大きく動くことがあります。
実務上の判断ポイントと例
実務では、契約の性質と顧客の受け取り方、成果物の移転タイミング、収益の計測可能性を総合して判断します。例としてソフトウェアのサブスクリプションは、機能が顧客に提供されるタイミングで収益を一部認識することが多く、進行基準の要素が強いです。一方で建設業の長期契約は、段階的進捗を測る指標を設定し、進行基準で認識するケースが多いです。契約内の複数のパフォーマンス義務(提供すべきサービスや商品の数)がある場合、それぞれの義務ごとに認識時期を分けることもあります。
こうした判断は「契約書の条項」「成果物が顧客にとって機能的に使える状態か」「支配の移転が完了しているか」を基準に行います。誤解を避けるためには、文書化されたポリシーを用意し、関係者間で共有することが重要です。
表で比較:進行基準 vs 完成基準
まとめとよくある誤解
進行基準は「進捗を測る指標があるか」が決め手、完成基準は「作業が完了して顧客へ移転が完了するか」が決め手です。誤解としては「長期契約は必ず進行基準」という前提や、「売上をいつ計上するかは必ず現金の受領時点で決まる」という認識があります。実際には契約の性質と業界の慣行、適用する会計基準(IFRS 15やASC 606)の要件に従って判断します。適切な基準を選ぶことは、財務報告の信頼性を高め、将来の意思決定にも役立ちます。
結論
収益認識の進行基準と完成基準は、売上をいつどのくらい認識するかを決める重要な考え方です。長期契約や段階的サービス提供の場合は進行基準の適用が多く、完成基準は契約全体が完了したときに大きく認識します。判断は契約の性質と成果物の移転タイミングを軸に行い、文書化されたポリシーを共有することが大切です。これを押さえておけば、財務報告の透明性と信頼性を高められます。
補足:実務のケーススタディ
ある建設プロジェクトでは、進行基準で進捗割合を見積もって売上を分割認識します。途中で追加工事が発生した場合には、追加分を別途見積もって認識します。別のソフトウェア開発契約では、機能が顧客に使われ始めた時点で一部を認識し、最終納品と承認後に残りを認識します。こうした具体的なケースを社内の会計マニュアルに落とし込み、担当者間で共有しておくと、判断のブレを防げます。
友達と昼休みの雑談のような雰囲気で話そう。ねえ、進行基準ってさ、長い工事みたいに時間がかかる取引で“今このくらい進んだ”って分かるときに、売上を少しずつ認識するって意味だよね。完成基準は、とにかく全部終わってからドカンと認識する感じ。僕の理解だと、進行基準は“進んだ分だけ出てくる梯子”みたい、完成基準は“最終ゴール地点での大きな一歩”みたい。授業では難しそうだけど、実際には契約の性質と成果物の移転タイミングで使い分けるんだ。おもしろいのは、同じ建設プロジェクトでも、契約の条項や顧客の承認状況で認識時点が変わること。つまり「待つべきか、進めて良いか」を判断するための基準を、現場の状況と照らし合わせて選ぶ必要があるんだ。進行基準のほうが、利益が早く見える一方で、完成基準は最終的な数字を強く示せる。どちらを採用するかは、企業の方針と業界ルールにも依存する。結局は、財務報告の透明性と正確さのために、契約の性質を丁寧に読み解く力が大事だと思う。





















