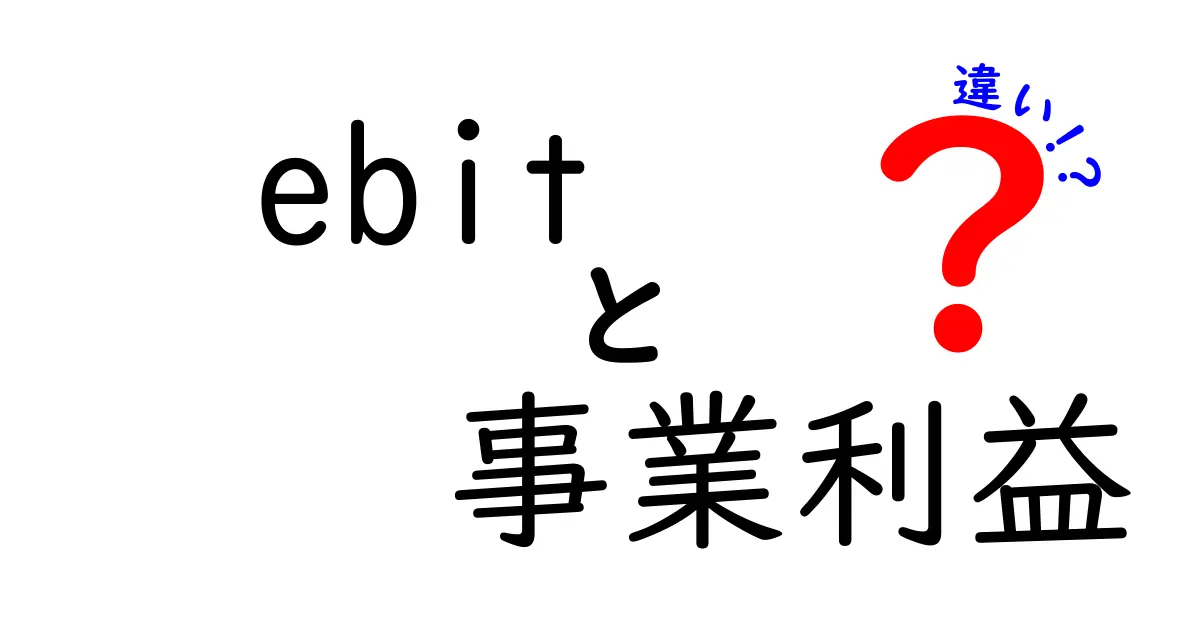

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ebitと事業利益の違いをわかりやすく解説
このセクションでは、ebitと事業利益の基本的な考え方を、難しくなく噛み砕いて紹介します。両方とも企業の「どれだけ利益を生み出しているか」を示す指標ですが、使われ方や表現の意味合いに微妙な違いがあります。まずは、EBITとは何かを明確にしましょう。EBITは earnings before interest and taxes の略で、日本語では「利息と税金を差し引く前の利益」と言います。つまり、利息の支払いと税金の影響を受ける前の、事業そのものの収益力を示す値です。EBITには、売上原価や販管費などの「通常の営業費用」に加え、減価償却費(在庫や設備の価値の低下を計上する費用)も含まれます。したがって、実務では減価償却を含む形での営業力を測る指標として使われることが多いのです。
一方、事業利益という言葉は、日本語でよく使われる表現の一つで「営業利益」とほぼ同じ意味で使われることがあります。つまり、本業の活動から得られる利益を指すものです。場合によっては「本業の利益をより強調する言い方」として使われることもあり、非本業の要素(例えば投資収益や為替差益、特別損益など)を含まない、本業の実力を示す指標として扱われることが多いのです。ただし会社ごとに表現の使い分けが異なるため、同じ会社の別資料でEBITと事業利益が同じ数値になる場合もあれば、別々に表示されている場合もあります。これを理解しておくと、決算資料を読んだときに「この会社はどの部分の利益を重視しているのか」が分かりやすくなります。
このように、EBITと事業利益は似た概念ですが、使われる場面や表現の重点に差があります。外部の分析レポートではEBITを使って「税金や借入の影響を受けない、純粋な事業力」を比較することが多いですが、社内資料や管理会計では「本業の安定性・成長性を評価する指標」として事業利益を重視する場合があります。結局のところ、どちらを見れば良いかは、目的と資料の出典に左右されます。決算を読み解く際は、同じ会社の中でEBITと事業利益がどのように定義されているのか、注釈を確認することが第一歩です。
この後のセクションでは、具体的な計算方法と、どう使い分けるのが良いかをさらに詳しく見ていきます。
ebitとは何か
EBITは、企業が本業でどれだけの利益を生み出しているかを示す基本的な指標です。税金の支払いと借入の利息をまだ考慮しない状態、つまり“税金・利息を差し引く前”の利益を表します。定義の要点は次の三つです。まず第一に、売上から原価( materials cost など)を引いた「売上総利益」から、さらに営業費用(販管費・人件費・広告費・減価償却費など)を引く点。第二に、ここには減価償却費も含まれるため、“現金の支出”としての減価償却と“会計上の費用”としての減価償却が混ざった状態になります。第三に、利息や税金はまだ引かれていません。これにより、企業の本業の力を外部要因に影響されずに比較しやすくなります。EBITは、企業の経営の「本質的な生産力」を測る基準として、投資家やアナリストに広く使われています。実務ではEBITの推移を見て、販売戦略やコスト構造の改善がどれだけ効果を上げているかを判断します。
事業利益とは何か
事業利益は、企業の「本業の利益」を指す表現です。日本の決算書ではしばしば「営業利益」と同義として用いられます。ここでのポイントは、非本業の収益・費用を除いた、いわゆる本業の実力を示す値であるという点です。計算の考え方としては、売上総利益から販売費及び一般管理費などの営業費用を引く形になります。つまり、原価を超える売上が出ていても、広告の投資が大きすぎると事業利益が落ちることがある、という現象も起こり得ます。EBITとの違いをよく問われますが、実務上は「EBIT=営業利益」として同じ意味で使われることが多いものの、資料の書き方次第で若干のニュアンスの差が生じます。いずれにせよ、本業の安定性・成長性を評価するには、事業利益の動向をしっかり追うことが大切です。
計算方法の違い
計算の観点から整理すると、まずEBITの計算式は次のようになります。
EBIT = 売上高 − 営業原価 − 販売費及び一般管理費 − 減価償却費(Depreciation and Amortization)
ここで減価償却費は“現金の支出”ではないが、会計上の費用として計上されるため、EBITには含まれます。つまり、設備投資の影響を含めた“資本的な消耗”を反映した利益です。次に事業利益(営業利益)の計算は、一般には次のように整理されます。
事業利益 = 売上総利益 − 販売費及び一般管理費 − その他の営業費用(もしある場合)
ここで注意したいのは、非本業の収益(例:投資収益、為替差益、特別損益など)は基本的に除外され、本業の収益力だけを切り出して評価するという点です。結果として、EBITと事業利益は“本業の力”という点で似た指標になりますが、扱われる費用項目の細かな定義の差によって数値が異なることがあります。企業ごとに表現の違いがあるため、決算資料の注記をチェックする癖をつけると良いでしょう。
実務での使い方と注意点
実務の現場では、EBITと事業利益をどう使い分けるかが重要です。外部の投資家向け資料や比較分析にはEBITを用いることが多く、これは「利息・税金の影響を受けずに事業の力を比較する」目的に適しています。一方、社内の管理会計や戦略策定では、事業利益を核心指標として使用するケースが多く、費用の内訳(販管費の削減、営業努力の強化、価格戦略の再考など)を具体的に見つけやすくなります。注目したい点は、用語の定義が企業ごとに異なることがある点です。決算短信や有価証券報告書には“EBIT”と“営業利益”の両方が使われることがあり、同じ語でも意味が違うことがあります。そのため、特に比較対象を選ぶときには、同じ指標で比較しているか、計算方法の注記を必ず確認してください。
さらに、時系列で見るときには、会計基準の変更や特別項目の有無で大きく動くことがある点にも注意が必要です。比較を行う際には、対象企業の事業モデルや資本構成、減価償却の前提などを同じ条件で揃えることが、正確な判断につながります。
最後に、中学生にもわかる結論を一つ挙げるとすれば、「EBITは“事業の力を税金・借金の影響を除いて見たいときの指標”、事業利益は“本業の力の安定性を直感的に掴みたいときの指標”」というイメージで覚えると、資料を読むときの混乱が少なくなるでしょう。
まとめと実務のコツ
ここまでで、EBITと事業利益の基本的な違い、計算の違い、使い分けのポイントを見てきました。実務でのコツは、まず同じ指標の定義を確認すること、次に比較対象の会計期間・前提条件を揃えること、最後に注記を読んで変動要因を把握することです。決算資料を読み解くスキルは、最初は難しく感じても、「本業の力をどう評価するか」という観点を軸にすれば迷わなくなるはずです。これを機に、あなたも自分なりの見方を1つ育ててみてください。
補足情報と実用例
以下は簡単な実務補足です。裏側の計算を理解することで、決算の数字が読めるようになります。実務でよく使われるのは、EBIT margin(EBITマージン)と呼ばれる指標で、売上高に対するEBITの割合を示します。これにより、規模が大きくても利益率が低い企業と、規模が小さくても利益率が高い企業を比較することができます。営業戦略を評価するうえでも、費用構造の改善がEBITにどれだけ効くかをチェックするのが効果的です。今後も財務諸表に触れる機会があるでしょう。落ち着いて、各指標の意味と計算方法を照らし合わせながら読み進めてください。
今日はebitについての小ネタです。友達に「EBITって何の略?」と聞かれたら、こう答えると分かりやすいですよ。EBITは Earnings Before Interest and Taxes の頭文字を取った言葉で、日本語に直すと「利息と税金を差し引く前の利益」です。でもここで大切なのは“税金と利息を引く前の利益”という点だけではありません。実はEBITには“企業が本来の営業力でどれだけの価値を生み出せるか”を測る力があります。たとえば、設備投資で減価償却費が増えても、現金の支出が増えたわけではない場面もあるので、EBITは「資本投資の影響を含めた本業の力」を見抜く道具にもなります。一方で、事業利益は本業の利益そのものを表す指標として、経営の安定性を知るヒントになります。こうやって両者を並べて考えると、決算書の数字が“誰の視点”で語られているのかが見えやすくなるんです。
次の記事: 営業外費用と経費の違いを今日からスッキリ理解する5つのポイント »





















