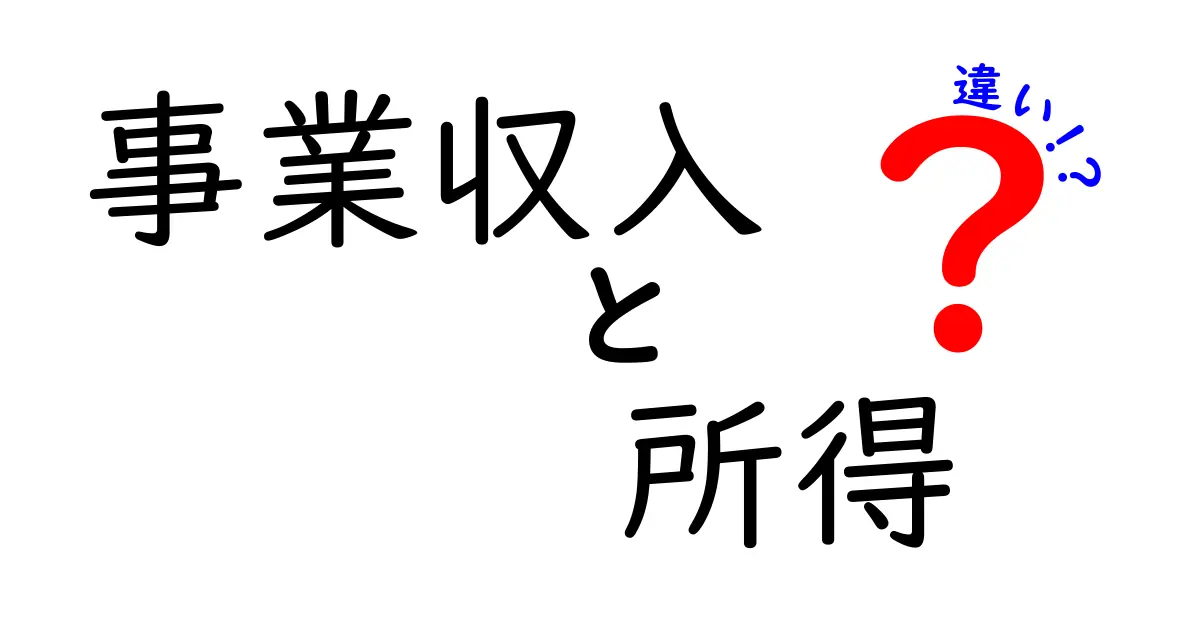

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに――事業収入と所得の違いを知る意味
「事業収入」と「所得」、この2つの言葉はよく似ていて混同されがちです。特に副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)を始めたり、会社を自分で運営したりすると、数字の見方が変わってきます。ここでのゴールは、お金の流れを正しく分けることと、税金がどう決まるかの仕組みを理解することです。事業をする人は「このお金はいくらの売上で、経費はいくら、最終的にいくらが所得になるのか」を意識する必要があります。現実には、家計とビジネスの両方を同時に回すケースが多く、複式簿記の考え方や科目名にも触れます。この記事では、難しい専門用語を避けつつ、日常の例を使って段階的に説明します。さらに、違いを理解することで、将来の資金計画や節税のヒントが見えてくることを目指します。読み进めるうちに「自分の数字を自分で観察する癖」がつくはずです。
これから見るポイントは、大きく分けて3つです。1つ目は定義の分離、2つ目は計算の仕組み、3つ目は実務での影響です。具体的には、事業収入は「売上の総額」、所得は「収入から経費を差し引いた額」と理解するのが近道です。さらに、法人と個人事業主の扱いの違い、給与所得との関係、そして課税のしくみがどう変わるかを順を追って見ていきます。これを押さえると、ニュースの解説記事を見たときにも「この表現は何を意味しているのか」がすぐ分かるようになります。
事業収入とは何か
事業収入とは、商品やサービスを販売して得るお金の総額のことです。経費を引く前の「売上高」に近い概念で、会計の世界では「売上」と呼ぶこともあります。個人事業主や法人が行うビジネスで得られる入金の総額で、ここから仕入れた材料費、従業員の給料、家賃、広告費などの経費を差し引く前の金額が表示されます。実務では、売上しか見えなくなると「本当にどれだけ利益があるのか」が分かりません。そこで、売上から経費を引いた「事業所得の素地」が次の段階で現れます。
事業収入の扱いは、事業を「継続的に行う意思」と「継続的な収益源」で評価される点が特徴です。ここには「単発のアルバイト収入」や「個人の副業としての収入」は含まれないケースがあり、事業としての活動かどうかを判断する基準が設けられています。法的には事業所得とされるかどうか、税務上の区分が重要です。これを誤ると、後で税額の計算が大きく変わってしまうことがあります。したがって、日常的な売上と「事業としての継続性」は別物として管理することが大切です。
実務的なポイントとしては、売上の管理と経費の管理を別々に行い、月次の決算で合算する習慣をつけることです。これにより、現金の流れが把握しやすくなり、資金繰りの計画もしやすくなります。売上高と利益の関係を知ることで、今後の事業戦略が見えやすくなります。
所得とは何か
所得とは、収入から必要経費や控除を差し引いた後に残る「手にすることができるお金の目安」です。個人の世界では、給与所得、事業所得、雑所得、不動産所得、譲渡所得などが分類され、これらを合算して総所得金額が決まります。その総所得金額に対して、基礎控除や各種扶養控除、社会保険料控除などを引いた金額が課税所得になります。つまり所得は「課税のベース」になる数字です。ここを間違うと、支払う税額が実際より多くなることがあります。なお、同じ言葉でも文脈によって意味が変わることがあり、例えば「事業所得」は所得の一種ですが、売上から経費を引いた後の金額を基に課税ルールが適用されます。これを理解すると、どのような控除が受けられるか、どう税額を抑える工夫ができるかが見えてきます。
注意点として、所得と収入は別物です。収入が大きくても、経費や控除が多いと所得は少なくなる場合があります。逆に、収入は小さくても経費が多くない場合には所得が大きくなることもあります。この点が、日常の家計と別に事業を運営する時に理解しておくべき大きなポイントです。
事業収入と所得の違いが生む影響
事業収入と所得の違いが生む影響は、主に税金と社会保険料の計算方法に現れます。まず、個人事業主やフリーランサーの場合、売上である事業収入が「所得」に変わるまでの道筋はこうです:事業収入から事業に関係する経費を引き、さらに基礎控除や各種控除を適用して所得を決定します。次に、所得からさらに配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などを差し引きます。結果として課税所得が決まり、所得税と住民税が算出されます。法人の場合は、法人税という別の税金が適用され、株主へ配当をする時には所得税とは別の課税が発生します。
友達と昼休みに「所得って何だろう?」と話していた。私たちはお金が入るときに“売上”という言葉が思い浮かぶけれど、それだけでは足りないことを知った。店で商品が売れて得たお金が“事業収入”として記録される一方で、そこから必要経費や控除を差し引いた額が“所得”になる。所得は税金の計算の基礎になるから、同じ収入でも経費が多いと所得が少なくなり、税金も安くなる。だから副業を始めるときは、売上だけを追わず「この経費は必要経費になるか」「どの控除を使えるか」を同時に考えることが大切だと思った。話をしているうちに、数字の扱いが現実の生活とつながっていることが深く理解できた。





















