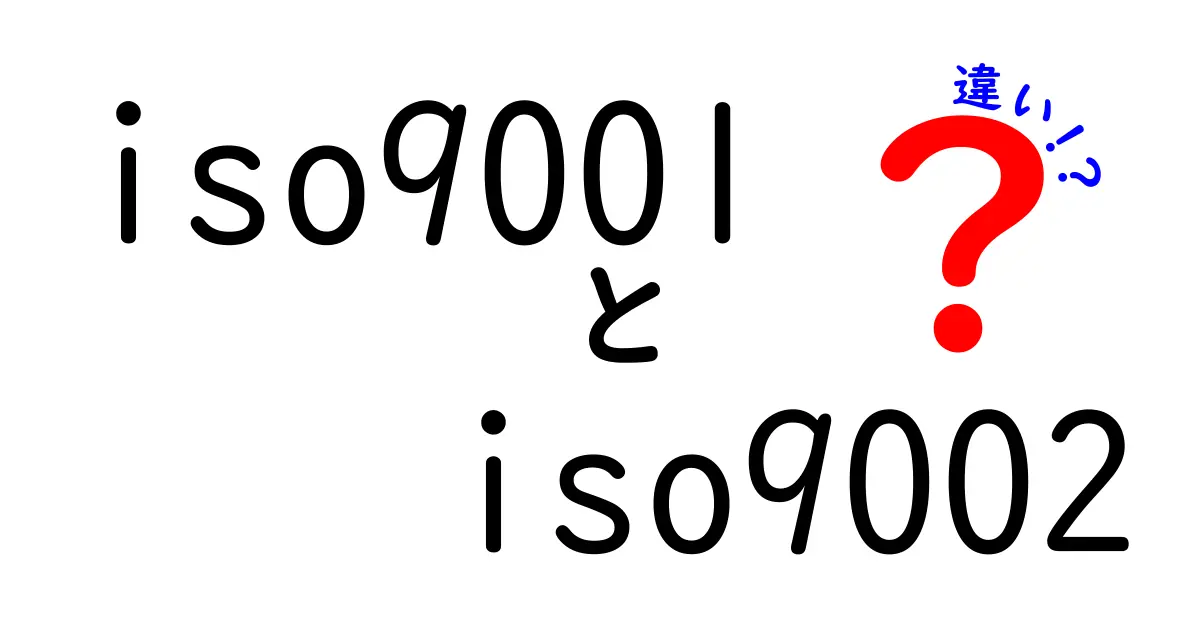

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに iso9001と iso9002 の基本を知ろう
ISO9001とISO9002は、品質を作る仕組みを決めるルールの名前です。難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「仕事のやり方をきちんと整える仕組みをどう作るか」という話です。9001は設計からサービスまで幅広い活動をカバーすることを目的としたルールであり、9002は主に製造と据え付け・サービスに焦点を当てたルールでした。いまは世界的に9001が主流となり、9002は過去の区分として整理されています。この記事では、昔の9002が何を対象としていたのか、9001との違いはどこにあるのかを、できるだけ分かりやすく解説します。
ポイントは「適用範囲の違い」「証明の意義の違い」「歴史的背景の違い」です。これを知れば、なぜ9001だけが現在も使われ続けているのかが自然と理解できます。
実務で役立つ違いを三つの観点から解説
この章では、現場でよく話題になる違いを三つの観点から詳しく見ていきます。各観点ごとに具体例を挙げ、現場でどう影響するのかをイメージできるようにします。読み終えるころには、9001と9002の「何がどう違うのか」がはっきりしているはずです。
この解説は、学校の課題やビジネスの基礎知識としても役立つ内容です。読み手にとって難しく感じる用語も、日常の例に置き換えて説明します。
観点1 適用範囲の違い
まず覚えておきたいのは、適用範囲の違いです。ISO9001は設計・開発・製造・据え付け・サービスまで、品質マネジメントシステム(QMS)の全体を対象にします。一方ISO9002は製造と据え付け・現場でのサービスまでの「現場に近い部分」に主に焦点を当て、設計や開発といった前段階の活動は含まれないのが基本でした。つまり9001は“作る前から終わりまでの全体像”を整える枠組み、9002は“現場での品質確保”を重視する枠組みと考えると分かりやすいです。
現場の例で言えば、製品の設計図を何度も見直して品質を高める活動が含まれるかどうかが大きな境界線になります。90XXの時代には、この差がプロジェクトの進め方や監査のチェック項目にも影響しました。
この観点を理解しておくと、企業がどのルールで認証を受けるべきかの判断がしやすくなります。
観点2 目的と証明の違い
次に重要なのは目的と証明の意味の違いです。ISO9001は“品質マネジメントシステムの適合性”を認証します。つまり、組織全体が品質を管理する仕組みを持ち、それを継続的に改善していることを示す証拠です。対して9002は“製品やサービスが要求事項を満たすことを証明する”ことに焦点を当てる場合が多く、現場での作業の信頼性や作業手順の適用性を重視します。言い換えれば、9001は組織の仕組みそのものを証明するのに対し、9002は製品やサービスの結果を証明する側面が強いのです。ただし実際には1990年代・2000年代の区分の整理に伴い、現在の認証は主に9001の適合性を示す形で行われています。
この違いを知っておくと、監査の準備をどう進めるべきか、どの部門をどのように巻き込むべきかが見えやすくなります。
観点3 歴史と現在の位置づけ
最後に歴史的な背景と現在の位置づけを整理します。旧来の区分として9001・9002・9003が併存していた時代には、それぞれの適用範囲が異なるため企業ごとに認証の取り方が変わっていました。しかし1994年版の導入以降、9001が設計・開発・製造・据え付け・サービス全般をカバーする形に進化し、
2000年版以降は9002・9003が統合され、9001だけを中心に品質マネジメントシステムの認証へと整理されています。
現在では9001が中心的な位置づけで用いられ、9002や9003のような旧区分は公式には廃止扱いとなっています。企業が国際標準に適合していることを示す際には、ほとんどの場合9001の適合性が問われます。歴史を通じて変化してきた背景を知ると、なぜ今の認証制度がそうなっているのか、納得感をもって理解できます。
この歴史理解は、将来の規格変更や運用の見直しを検討する際にも役立ちます。
まとめ 高校生にも伝えたい要点
要点はシンプルです。9001は組織の品質管理の仕組み全体を証明するもの、9002は現場の作業と製品・サービスの品質を証明するという考え方が基本でした。現在は9001が中心で、過去の区分は整理されています。この理解を持っていれば、企業がどの認証を目指すべきか、監査準備をどう進めるべきかを判断しやすくなります。
品質管理の話は難しそうに見えますが、現場での“正しい手順を守ること”と“継続的な改善”という基本に立ち返ると、誰にとっても身近な話です。
適用範囲という言葉は、ISO9001とISO9002の違いを理解する鍵です。私が以前、現場の作業手順を見直すとき、設計と製造の境界線がくっきりしていない場面に出会い、適用範囲の理解が不足していると品質の改善が遅れることを痛感しました。適用範囲を正しく捉えることで、どの部門がどのルールに従うべきかが明確になり、チーム全体の動きがスムーズになります。そんな日常の会話を想像すると、難しそうな規格の話もぐっと身近になります。





















