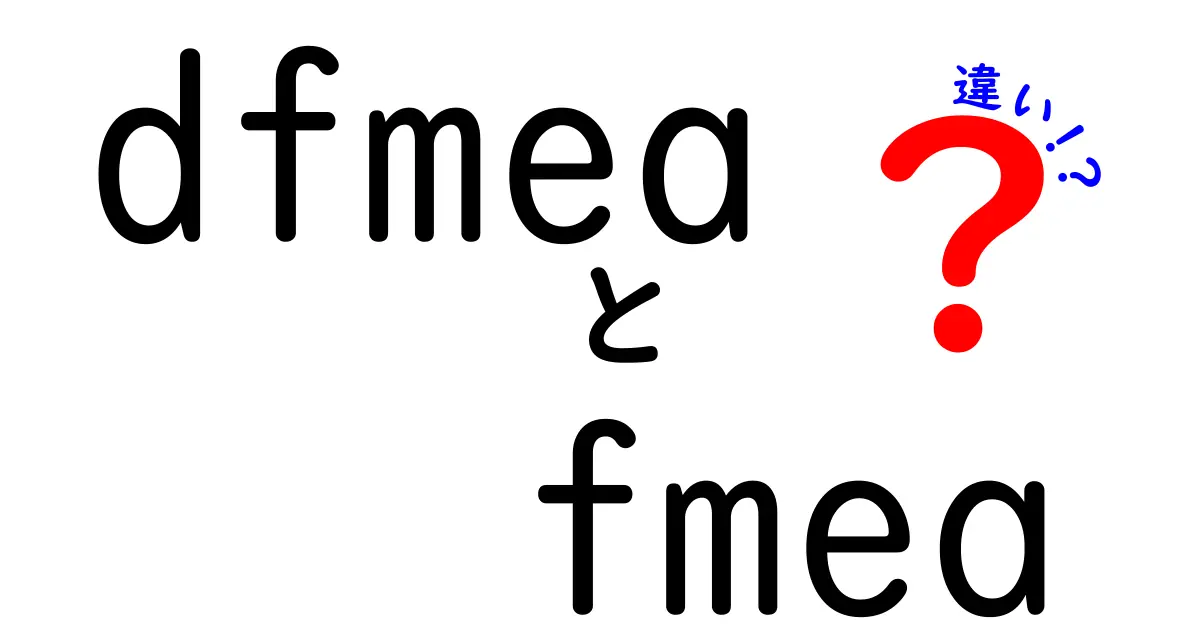

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
DFMEAとFMEAの違いを理解する基礎
ここではFMEAの基本的な考え方と、DFMEAとFMEAの違いを、初心者にも伝わる言葉で解説します。
FMEAはFailure Modes and Effects Analysisの略で、製品やプロセスがどのような故障モードを起こすか、それが引き起こす影響を予測する手法です。
設計段階でのFMEAはDFMEAと呼ばれ、設計の信頼性や機能要件の適合性を高めることを目的にします。
逆にPFMEAはProcess FMEAで、製造や検査などの工程でのリスクを対象にします。
この3つの視点は同じ分析手法を使いますが、対象範囲と目的が異なる点が大きな違いです。
DFMEAにおける分析は、部品の形状、材料、接合方法、公差などが壊れた場合の影響を想定します。
FMEAの共通要素として、故障モード、影響、原因、対策、そしてリスク優先度(RPN)があります。
RPNを使うと、どの故障モードを最初に直すべきかが分かり、資源を効率的に配分できます。
以下の表は、DFMEAとFMEAの代表的な違いを一目で比較できるようにまとめたものです。
実務での使い方とケーススタディ
現場での実務は、まずクロスファンクショナルチームを作ることから始まります。
設計担当、製造、品質、購買、サービス部門などのメンバーが協力して、設計案に対して可能性のある故障モードを列挙します。
DFMEAでは、最初の設計案が固まる前に、材料の特性、荷重条件、温度変化、振動などの要因を考慮して、各故障モードの発生確率と影響の深刻さを評価します。
評価にはチームの経験だけでなく、過去のデータや試験結果が使われ、優先順位の決定をサポートするRPNや新しいリスク指標を使います。
対策としては設計の変更、設計要件の追加、デザインフォールトトレランスの導入などが挙げられます。
実際のケーススタディとして、ある機械部品のDFMEAでネジの緩みが重要なリスクとして挙がり、ねじの固定方法を改善する設計変更が早期に提案され、試作段階での信頼性が大幅に向上した事例があります。
このような取り組みは、開発コストを抑えつつ市場への適合性を高め、リリース後の製品トラブルを減らす効果が期待できます。
昨日、友達とdfmea fmeaの話をしていて、DFMEAが設計段階のリスクを前もって見つける役割を果たすって理解したんだけど、話が進むにつれて“設計と実際の作業”の橋渡しの難しさも見えてきた。
DFMEAは理論的にもって考えがちだけど、実際には材料選択や部品形状、加工性、公差などの現実的要素をどれだけ設計に反映させられるかが勝負。
一方FMEAは製造やサービスの現場で起こりうるトラブルを洗い出して、作業手順・設備・教育の改善を促します。
このように、どちらもリスクを見つけて対応する点は同じでも、対象が異なるだけで、使い方やアウトプットが大きく変わるんだなと感じました。





















